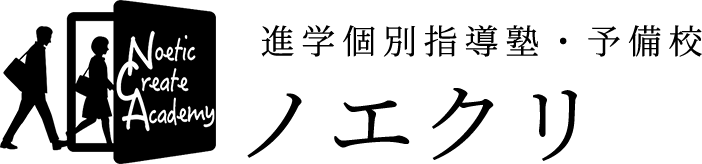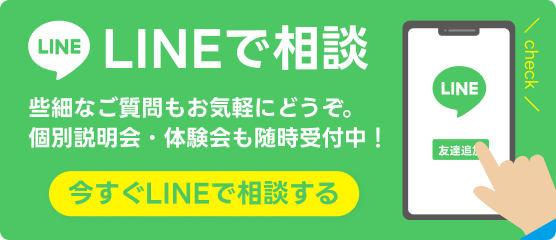2026年共通テスト 化学対策|時間配分・出題傾向・時短テクニック
2025.9.29 共通テスト対策講座 大学受験オススメ情報
ノエクリ公式
目次
1. はじめに|変わる化学、求められる力
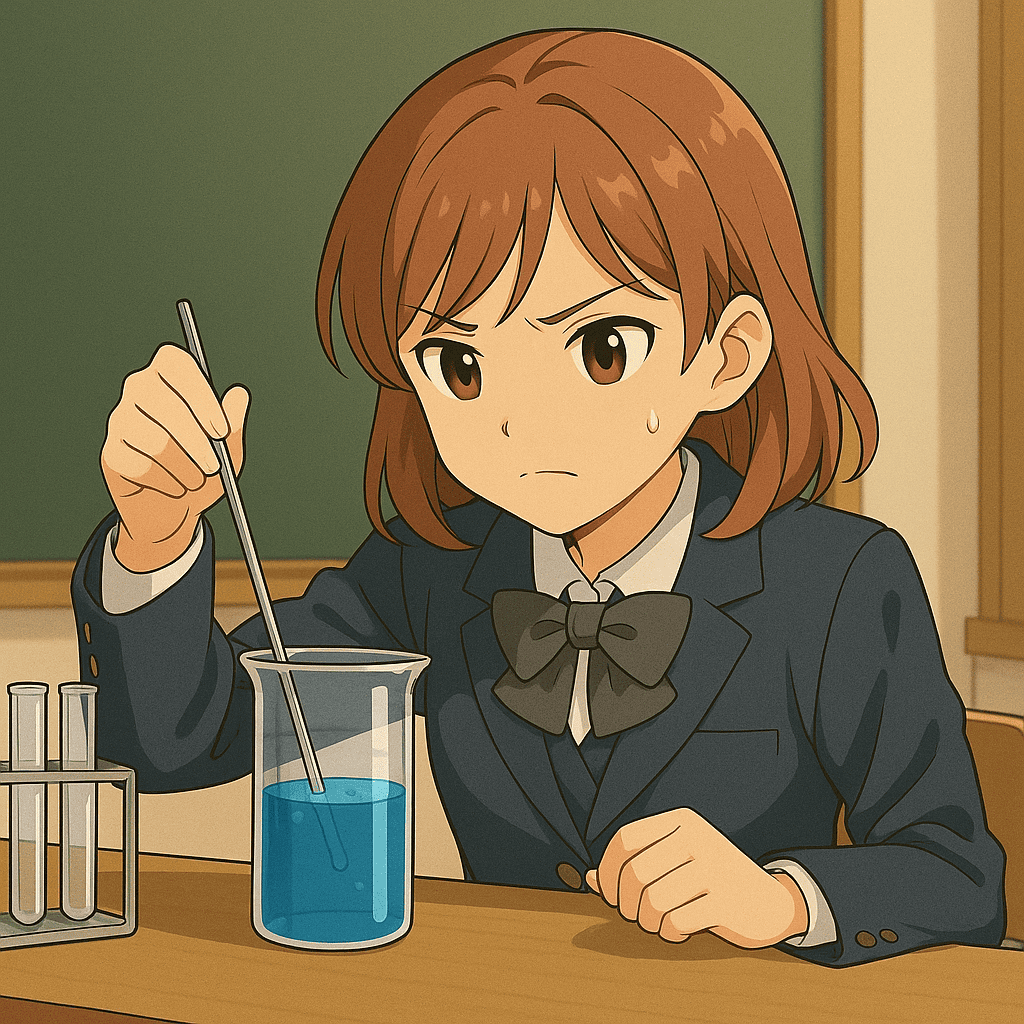
共通テストの化学は、暗記した公式や知識をそのまま当てはめるだけでは解けない問題が増えてきています。
一方で、2025年度は過去のセンター試験と近い典型的な問題も多く出題されました。そのため、全範囲を満遍なく学習し、基礎力をしっかり固めているかどうかが最大のポイントです。
また、グラフやデータの読み取りを中心とした問題が多く見られ、時間内に正確に解ききる計算力はもちろん必須ですが、「条件の整理」や「情報の読み取り」が重視される傾向です。
2026年度もこの方向性は継続すると考えられます。この記事では、試験の基本情報から時間配分、出題予想、時短テクニック、高得点を狙うための勉強法までを徹底解説していきます。
試験の基本情報|形式・配点・構成
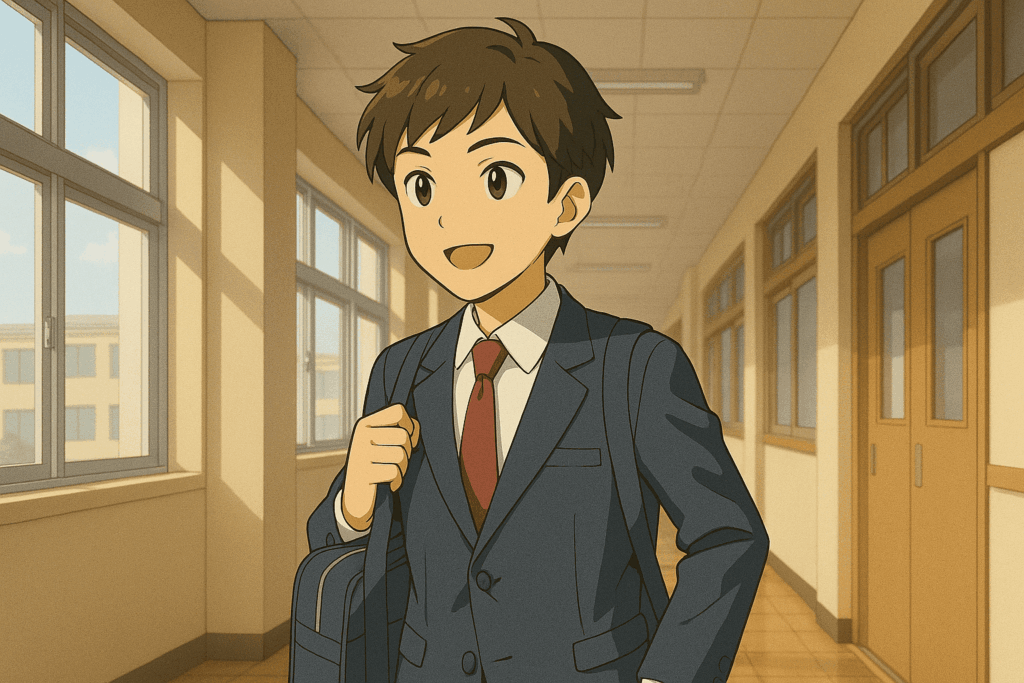
共通テスト化学はマーク式で60分、配点100点の試験です。
2025年度からは新課程と旧課程で一部の扱いが異なる構成が導入されました。
基本情報
| 試験時間 | 60分 |
| 出題形式 | マーク式 |
| 大問数 | 5題または6題 |
| 選択・必答 | 第1~4問は全員必答 新課程履修者は第5問も必答 旧課程履修者は第5問・第6問から1題を選択 |
大問ごとの出題内容(2025年度例)
| 問 | 出題分野 | 主なテーマ・内容 | 設問数/マーク数 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 物質の構成・状態 | 逆浸透法を利用した海水から淡水を得る方法、結晶構造・状態変化関連 | 5設問・6マーク(20点配分) |
| 第2問 | 物質の変化・平衡 | 化学反応の記述、反応平衡、酸化還元、反応熱など | 4設問・6マーク(20点配分) |
| 第3問 | 無機化学 | 遷移元素の性質、無機塩、錯体、金属結合・イオン化傾向 | 4設問・8マーク(20点配分) |
| 第4問 | 有機化合物・高分子化合物 | 有機化学反応、構造、重合・高分子の性質 | 4設問・8マーク(20点配分) |
| 第5問(選択必答) | 総合問題(反応エネルギー、構成分子、無機/有機混合) | 原油の分留、化合物の性質、反応エンタルピー問題等 | 3設問・5マーク(20点配分) |
| 第6問(選択対象) | 総合)旧課程向け/混合分野 | (選択出題)化学反応・物質構成など | 3設問・5マーク(20点配分) |
ポイント
センター試験時代と比べて、単なる暗記型ではなく「実験設定やデータ処理を含めた応用問題」が多くなっています。
特にグラフや表を読み取る問題が増えており、基礎知識とともに条件整理力が大きく試される形式となっています。
おすすめ時間配分と戦略
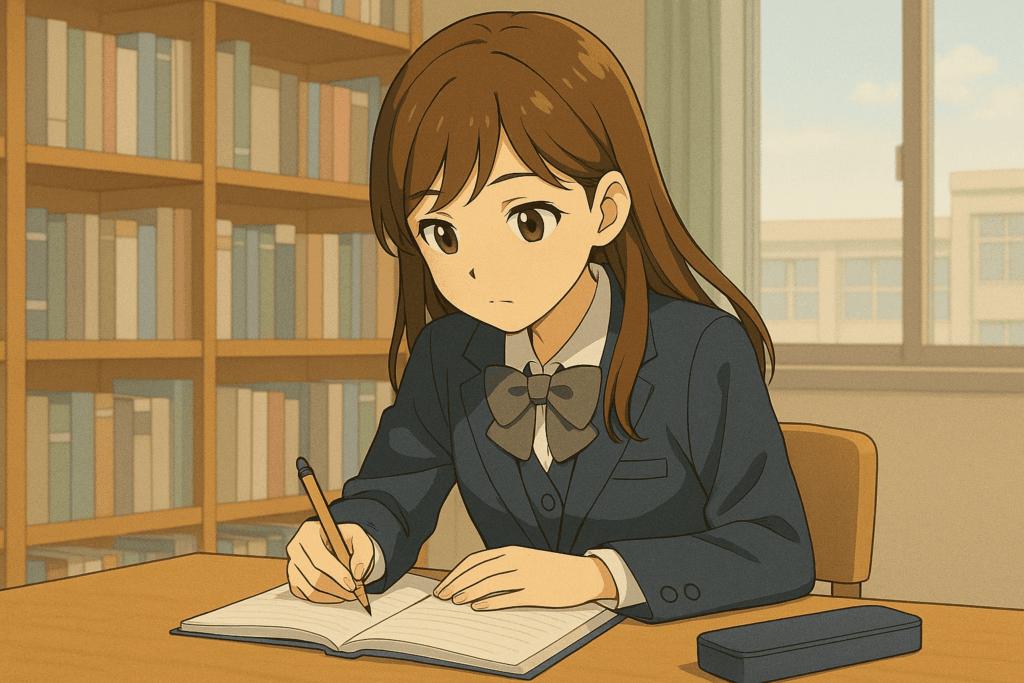
化学は大問ごとの難易度に差があり、時間をかけすぎると全体のバランスが崩れやすい科目です。60分をどう使うかが、得点の安定に直結します。
推奨時間配分(2025年度構成をもとに)
| 大問 | 推奨時間 | 攻略のポイント |
|---|---|---|
| 第1問 物質の構成・状態 | 8〜10分 | 基礎知識と簡単な計算が中心。確実に得点し、リズムをつくる。 |
| 第2問 理論化学(平衡・酸化還元など) | 12〜13分 | やや計算量が多い。与えられた条件を正確に整理してから計算開始。 |
| 第3問 無機化学 | 10〜12分 | 暗記の比重が高い分野。実験考察を含む設問もあるため、図や表に線を引きながら確認。 |
| 第4問 有機化学 | 12〜13分 | 構造決定や反応経路の推理が多い。パターンを素早く見抜く訓練が必要。 |
| 第5問 総合問題(新課程必答/旧課程選択) | 10〜12分 | データ処理や複合分野の融合。時間をかけすぎず、誘導に沿って解く。 |
| 第6問 総合問題(旧課程選択対象) | 10〜12分 | 出題内容は第5問と類似。旧課程受験生は比較して得点しやすい方を選ぶ。 |
| 見直し | 3〜5分 | マークずれや符号、数値計算の桁ミスを重点的に確認。 |
戦略のポイント
・序盤の第1問は確実に取り切る。ここで得点を安定させると後半も落ち着いて解ける。
・計算問題(第2問、第4問)では「情報や条件を図や式に整理してから」取りかかることで結果的に時間短縮が可能。
・無機・有機は知識量勝負になりがちだが、見慣れない題材でも基本反応パターンに落とし込むことができれば対応できる。
・総合問題(第5問・第6問)は実験などの長い問題の流れを追う必要があるため時間がかかる。誘導を素直に追うことで無駄な試行錯誤を防ぐ。
こう変わる!2026年 共通テスト化学の出題傾向予測
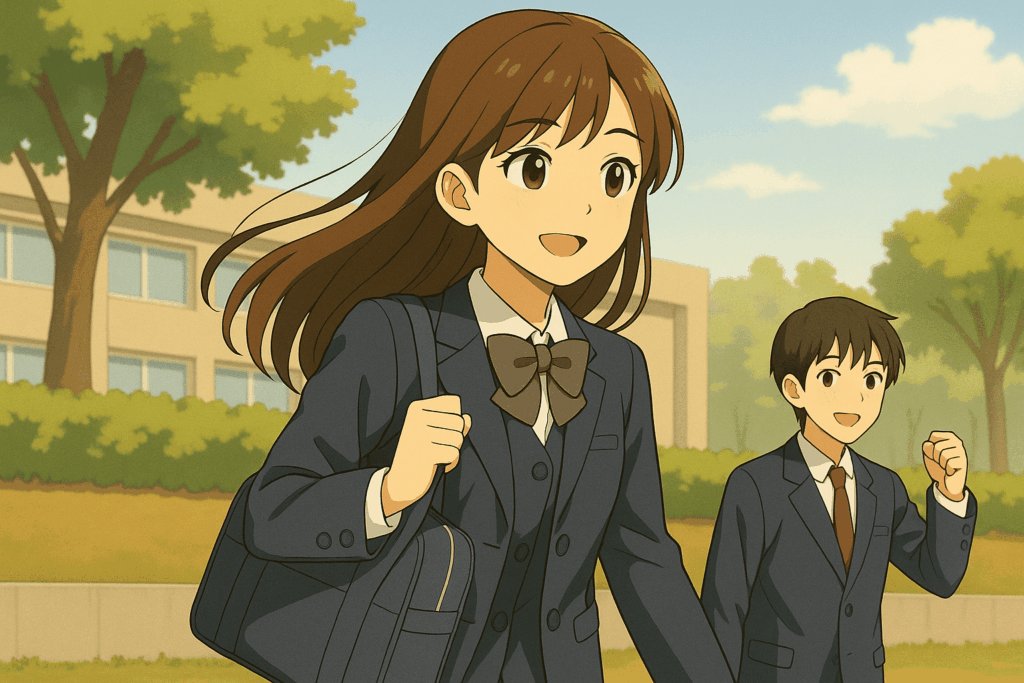
2025年度の共通テスト化学では、設問数やマーク数が増え、反応エンタルピーなど新課程要素も取り入れられました。
2026年度もこの流れを受けて、さらに次のような特徴が強まると考えられます。
出題傾向予測のポイント
・小問集合の比率維持とテーマの細分化
大問1から4では、これまで通り幅広い範囲からの小問集合が出題される見込みです。ただし、1問あたりのテーマがより細かくなり、知識を組み合わせて考える力が求められそうです。
👉おすすめ勉強法
朝やスキマ時間に「一問一答カード」を回す。暗記用カードアプリでも紙でもよい。特に無機の色・沈殿・炎色は毎日確認。短時間で毎日繰り返すことで記憶が安定する。
・グラフ・表・実験データの読み取り強化
化学でもグラフや表を読み取り、条件を整理して結論を導く設問が増えています。実験装置の説明やデータが提示され、それをどう読み解くかがカギになるでしょう。
👉おすすめ勉強法
教科書や問題集にあるグラフを「白紙に描き直す」練習を取り入れる。軸の意味や傾きの解釈を、自分の言葉でノートに書き出す。実際に手を動かすことで、グラフの変化を瞬時に判断できるようになる。
・未知化合物や新しい題材の登場
教科書にない化合物や分析法が題材として使われる傾向があります。問題文の情報を的確に読み取り、既存の知識と結びつける練習が必要です。
👉おすすめ勉強法
過去問や模試の「初見の化合物」をピックアップして、反応の流れを図にまとめる。たとえば「与えられた情報 → 推測できる官能基 → 予想される反応」と矢印で整理。これを数回繰り返すだけで応用力が伸びる。
・計算量と思考ステップの増加
単純な計算だけでなく、複数の条件を整理して段階的に解答する問題が増えると予想されます。特に反応エンタルピー、平衡定数、電池などで応用力が試されるでしょう。
👉おすすめ勉強法
平衡や電池の計算は「計算過程を途中式で3行以内にまとめる」練習をする。慣れてきたら電卓を使わず暗算で近似値を出すトレーニングを取り入れる。テスト本番でも時間を大幅に節約できる。
・選択形式から全問必答へ?
2025年度のように、新課程・旧課程で異なる必答・選択問題が設定されました。2026年度からは全問必答となる可能性があります。
どこで差がつく?高得点者が意識するポイント
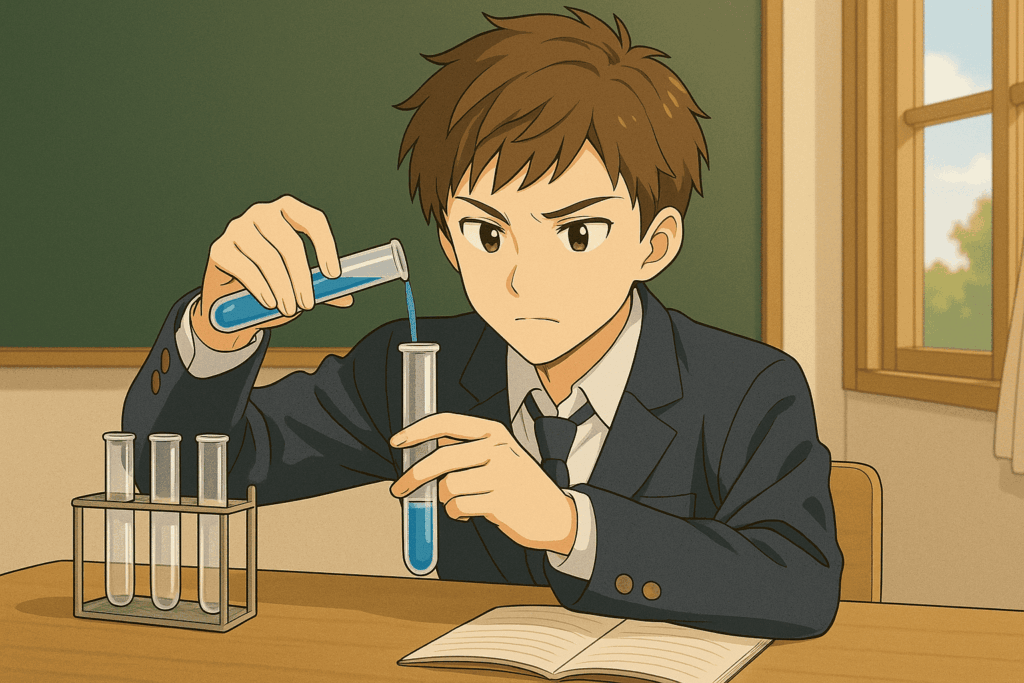
共通テスト化学で高得点を取る人と、平均点にとどまる人の違いは、単なる知識量ではありません。限られた時間の中で「正しく読み取り」「効率よく処理する」力に大きな差が出ます。
1. 問題文を読む順序
高得点者は、最初に「設問が何を求めているか」を確認してから本文を読むので、余計な情報に惑わされません。平均点層は、最初から全文を精読してしまい、必要な条件を見失いがちです。
2. 計算問題の進め方
平均点層は一から全ての式を立て直そうとしますが、高得点者は「公式や比例関係を使って省略できる部分」を瞬時に見抜きます。例えば、平衡定数や電池の起電力計算では、途中の近似やオーダー比較で一気に答えを絞ります。
3. データやグラフの扱い
高得点者は、与えられたグラフに直接メモを書き込み、縦軸・横軸の意味を明確にしてから判断します。平均点層は「グラフを眺めるだけ」で誤読し、符号や傾きの意味を間違えがちです。
4. 知識と応用のバランス
暗記を丸ごと頼るのではなく、基本知識を応用して「未知の題材」にも対応できるのが高得点層です。例えば教科書にない化合物でも、提示された官能基や実験条件から反応パターンを推測します。
5. ミス防止の習慣
高得点者は、必ず大問ごとにマークを済ませ、その場で確認します。平均点層は最後にまとめてマークしてしまい、ずれや塗り間違いで失点することが多いです。
まとめ|2026年度共通テスト化学で得点力をつけるには
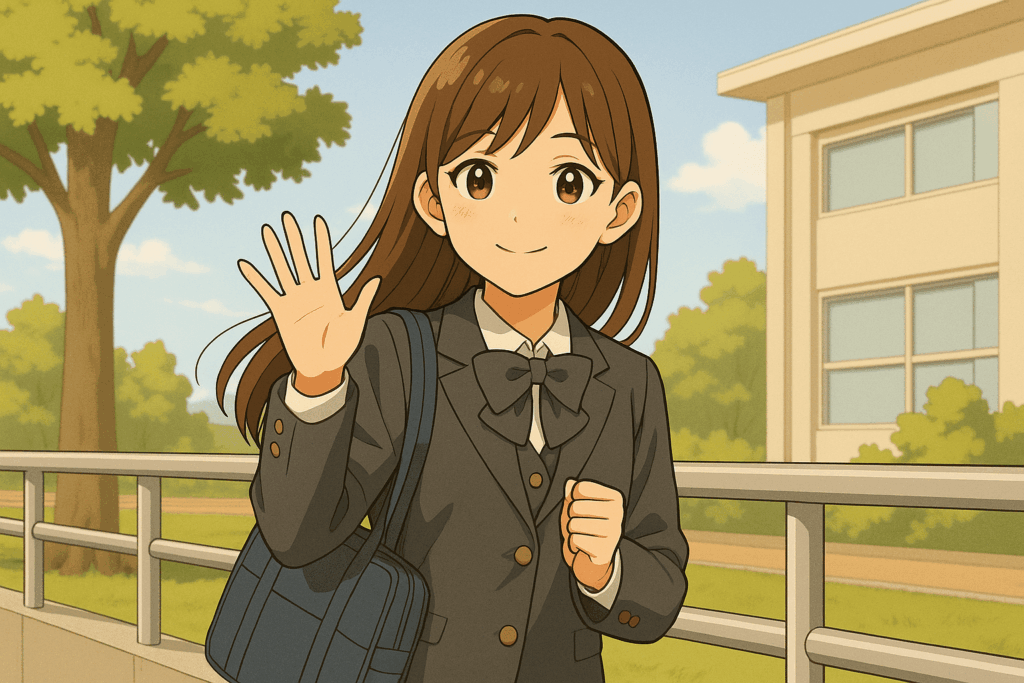
2026年度の共通テスト化学は、2025年度と同様に大問1〜4が必答、新課程と旧課程で異なる第5問・第6問の扱いが続く見込みです。出題形式は安定している一方で、問題文の長文化やデータ処理の複雑化により、難化傾向は続くと考えられます。
高得点を狙うには、次の3点が重要です。
・「基礎知識の抜けをなくす」こと。特に小問集合での取りこぼしは全体の得点を大きく左右する。
・「グラフや表を素早く整理できる力」を身につけること。数値や条件を図に書き込む習慣を演習で徹底する。
・「計算問題での省略・近似を使いこなす」こと。本番で時間切れにならないための必須スキルとなる。
暗記に偏るのではなく、知識を整理して「どう活用するか」を意識した学習を重ねることで、未知のテーマや新しい題材にも対応できる力がつきます。
直前期は「自分が得点源にできる分野」を明確にし、優先順位をつけた演習を重ねましょう。
2026年度の共通テスト化学で安定して高得点を取るための準備は、日々の小さな工夫から始まります。
投稿者
ノエクリ公式
進学個別指導塾ノエクリの公式アカウントです。
合格速報などのノエクリ最新の情報をお届けします。
▲▲クリックしてノエクリ公式のブログ一覧(108ブログ公開中)を見る