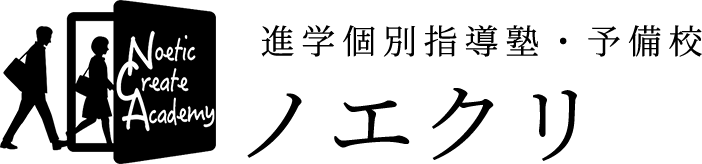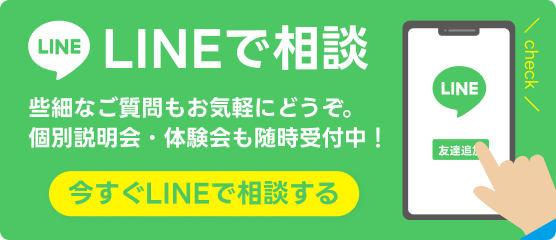富士高校の数学テスト対策|時間配分と得点戦略で安定点を取る方法【高1・高2向け】
2025.10.2
荷川取
富士市の進学校・富士高校の数学テストは「難しい」と感じる生徒が多い科目です。
「チャート式の例題なら解けるのに、時間が足りない…」
「最後の問題に挑戦できずに終わった…」
こうした声は、特に下位層から中間層の生徒に多く聞かれます。
実際のテストは 標準問題が中心なのに問題数が多く、さらに難関大レベルの難問も混じるため、解き方や時間配分を工夫しないと高得点は狙えません。
この記事では、富士高生が数学テストで安定して得点するための具体的な勉強法と戦略を紹介します。
目次
富士高校の数学テストの特徴
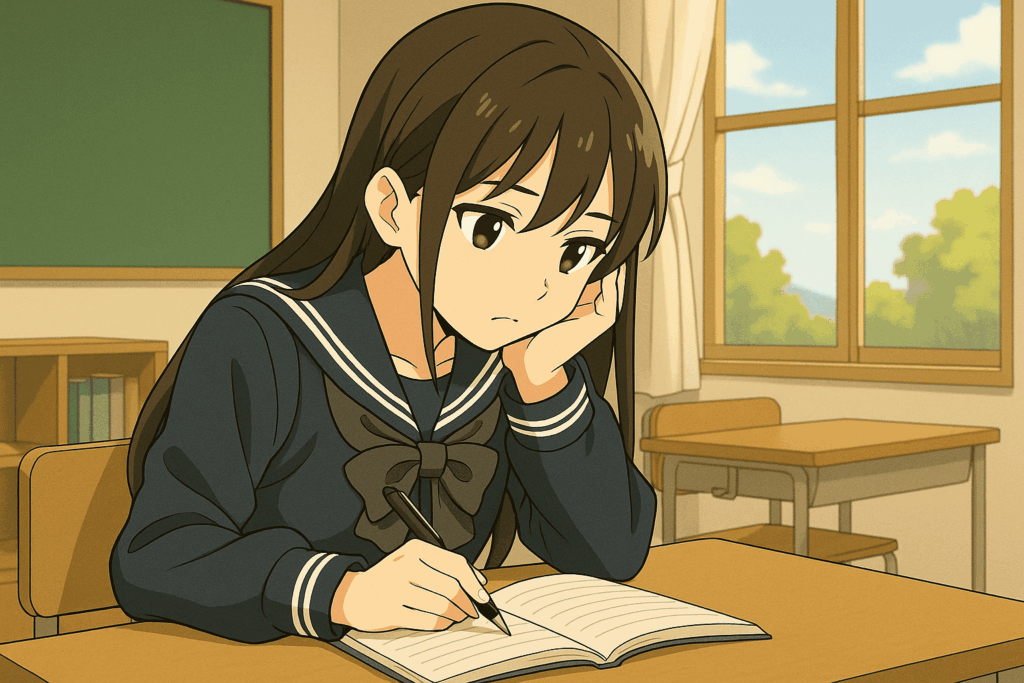
①1問1問は標準レベル
大部分の問題は「チャート式の例題レベル」。公式や典型解法を覚えていれば解ける。
②問題数が多く、時間が足りない
テスト時間内に全問をじっくり解くのはほぼ不可能。
→ 「処理スピード」を鍛えておかないと点数が伸びにくい。
③難関大レベルの問題が混じる
毎回1〜2問、発想力や応用力が試される問題が出題。大半の生徒が解けないため、実は差がつきにくい。
④範囲が広く、網羅できていないと失点
特定の単元だけでなく、テスト範囲全体からまんべんなく出題される。
→ 苦手単元を放置すると、その分野から出題された瞬間に大失点につながる。
👉 富士高の数学は 「解ける問題を速く・網羅的に拾い、難問で部分点を稼ぐ」 という戦略が必須です。
下位~中間層がまず目指すべき得点戦略
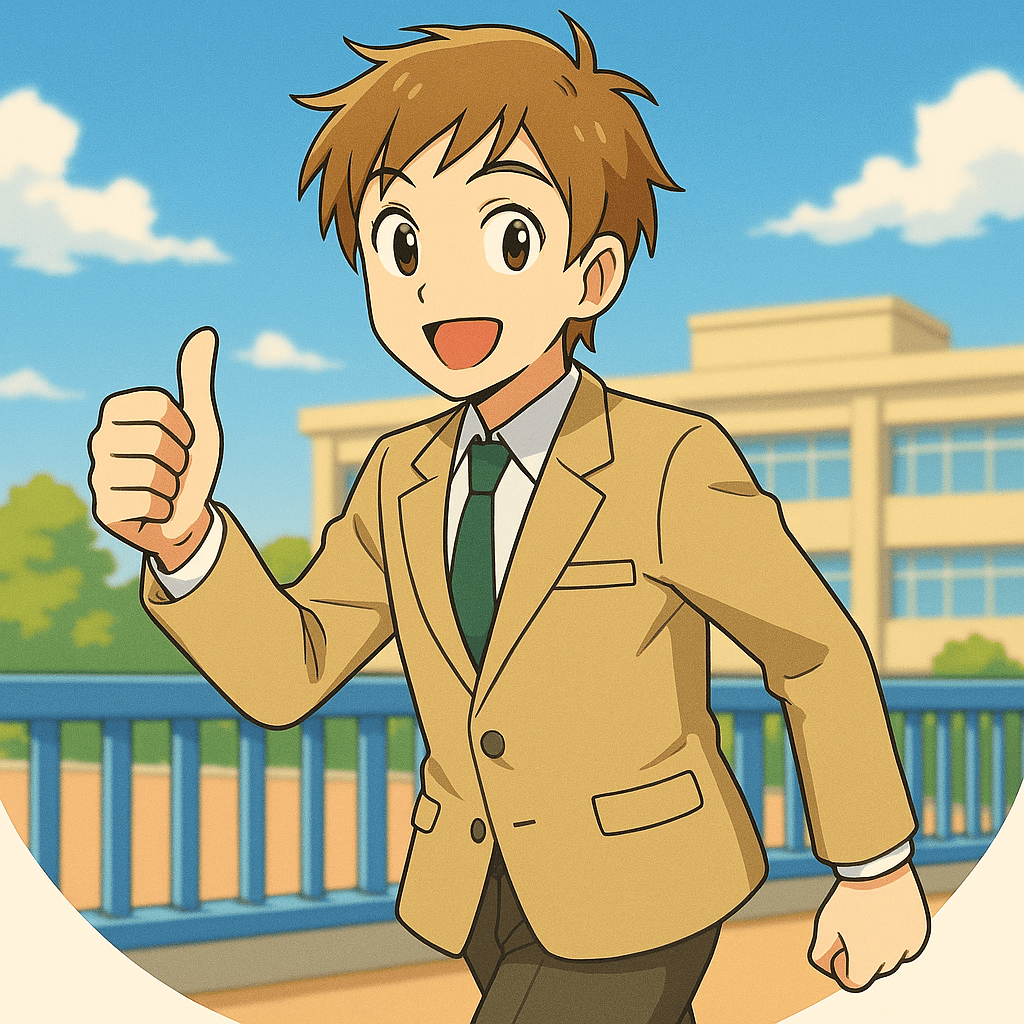
1. 標準問題を100%取り切る
富士高の数学テストは、実際には大部分が「チャート式例題レベル」。ここを落とすと一気に点数が下がります。
・狙い:大問前半や小問集合で「確実に得点する」こと。
・実践法:
学校ワークやチャート式の例題を、“すぐに答えが出るレベル”まで反復する。
「考えて解く」から「体が覚えているから解ける」に変える。
・イメージ:計算ドリルを何度も解いて、反射的に答えが出る感覚。
👉 これだけでテスト全体の 5〜6割は安定して得点可能。
2. 難問に固執しない
毎回1〜2問出題される難関大レベルの問題は、数学に苦手意識のある層にとって「勝負問題」ではありません。
・NG行動:
「ここで粘れば逆転できるかも」と10分以上かけて考え込む。
結果、標準問題に時間が足りず、大量失点する。
・正しい行動:
3分考えて手が動かないなら飛ばす。
後半で時間が余ったら再挑戦する。
👉 「難問は解けなくても当たり前」。まずは確実に取れる問題を取り切ることが優先です。
3. 苦手単元を「捨てない」
富士高のテストは範囲全体から幅広く出題されるため、「苦手だからやらない」は大きなリスクです。
・例:
「数列が苦手だから放置」→ もし数列が大問丸ごと出たら0点。
「図形が嫌い」→ 図形証明や応用で確実に失点。
・対策:
苦手単元でも、典型問題だけは演習しておく。
例題レベルでいいので「見たことがある」状態にする。
・意識:
苦手を「得点源」にしなくてもいい。
ただし「0点を防ぐ」だけでテスト全体の底上げになる。
👉 苦手を放置すると大失点、触れておくだけで +5〜10点の底上げが可能です。
4. 難問は“部分点狙い”
難問を最後まで解けなくても、答案に「途中までの考え方」を書くだけで点がもらえるケースは多いです。
・例:
三角関数の証明 → 定義式を書くだけで部分点。
ベクトルの応用 → 方程式を立てるところまでで部分点。
・実践法:
普段の演習から「途中式を答案に残す練習」をする。
テストでは白紙を避け、書けるところまで必ず書く。
・効果:
本来0点だった問題が、2〜3点加点されるだけで合計点が数%上がる。
👉 「難問は捨てる」のではなく「部分点を取りに行く」。これが中間層の賢い戦略です。もっと言えば、難問は完全に捨ててしまって、基本~標準問題に時間を使う手もあります。
戦略まとめ
数学で悩んでいる富士高生は、まず次の流れを徹底しましょう。
・標準問題を完答する力をつける(基礎で5〜6割安定)
・難問に執着しない(3分ルールで切り替える)
・苦手単元を最小限でも触れておく(0点を防ぎ点数を底上げ)
・難問は部分点狙い(白紙をなくし、得点を少しでも積み上げる)
👉 この4つを実行すれば、下位層から中間層でも 安定して合格ラインを超える点数 が狙えます。
効果的な勉強法
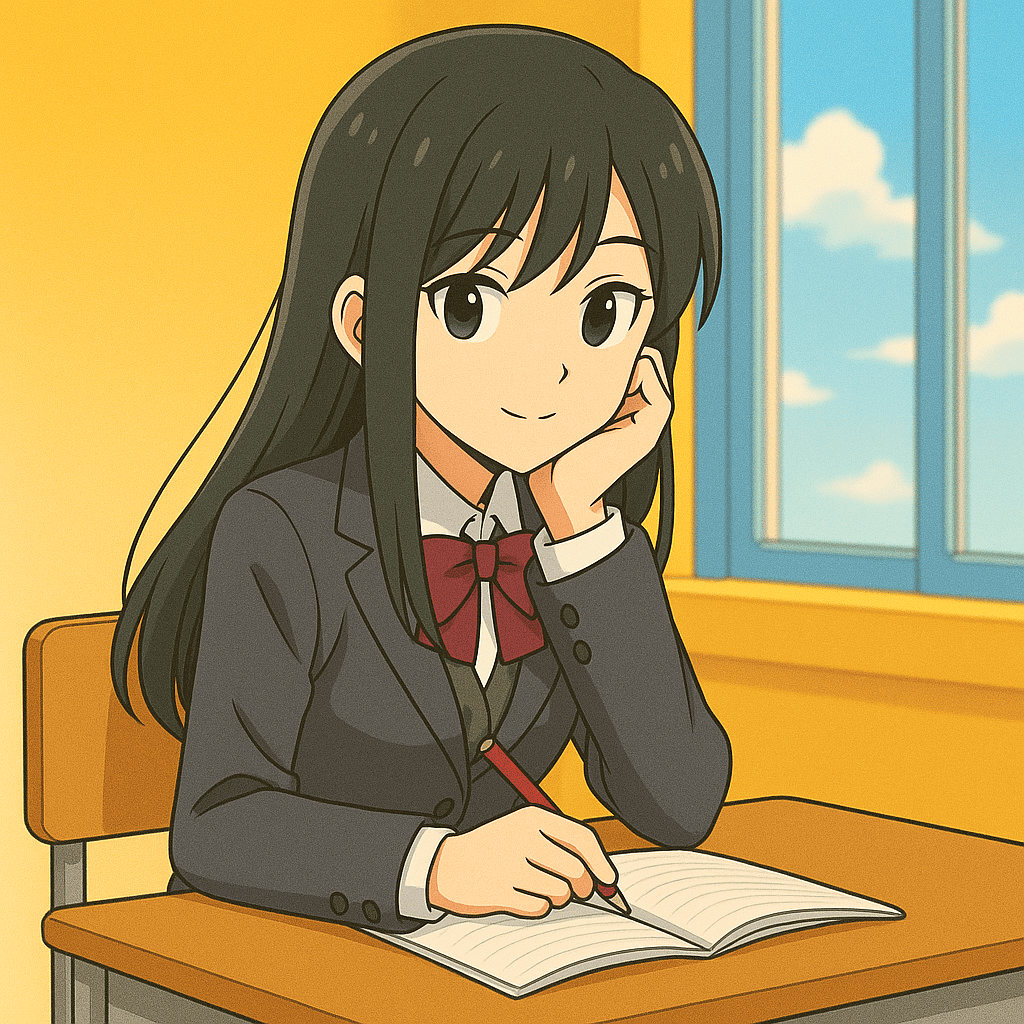
1. チャート式は「例題だけ3周」
1周目:解答を見ながら理解する(赤ペンでポイントを書き込み)。
2周目:解答を隠して自力で解く。間違えたらすぐ解答を確認。
3周目:時間を測って解く。1問あたり3分以内を目標に。
👉 このサイクルで、標準問題を「考えなくても手が動くレベル」に仕上げます。
2. 学校ワーク・プリントは「範囲を全部やる」
富士高のテストは範囲全体から幅広く出題される。
苦手だからと後回しにすると、その単元が出題されたときに大きく失点する。
最低限:各単元の基本問題だけでも必ず解く。
👉 「全く触れていない分野をなくす」ことが安定得点への第一歩です。
3. 難問は「途中まで解ける練習」
難関大二次レベルの問題は、解き切れなくても立式や条件整理まで到達すれば部分点が狙える。
例:「△ABCの外心を求めよ」なら、外心の定義を書くだけでも加点対象になる。
👉 「完答を目指すのではなく、途中式を残す」練習を普段から意識することが大切です。
4. 解答スピードを意識した演習
ノートに解いた時間を記録する。
同じ問題を2回、3回と解くことで処理時間が短縮される。
「最初に10分かかった問題が3分で解けるようになる」感覚を身につけると自信になる。
👉 富士高のテストは「スピード勝負」。普段の勉強から時間を意識しましょう。
まとめ
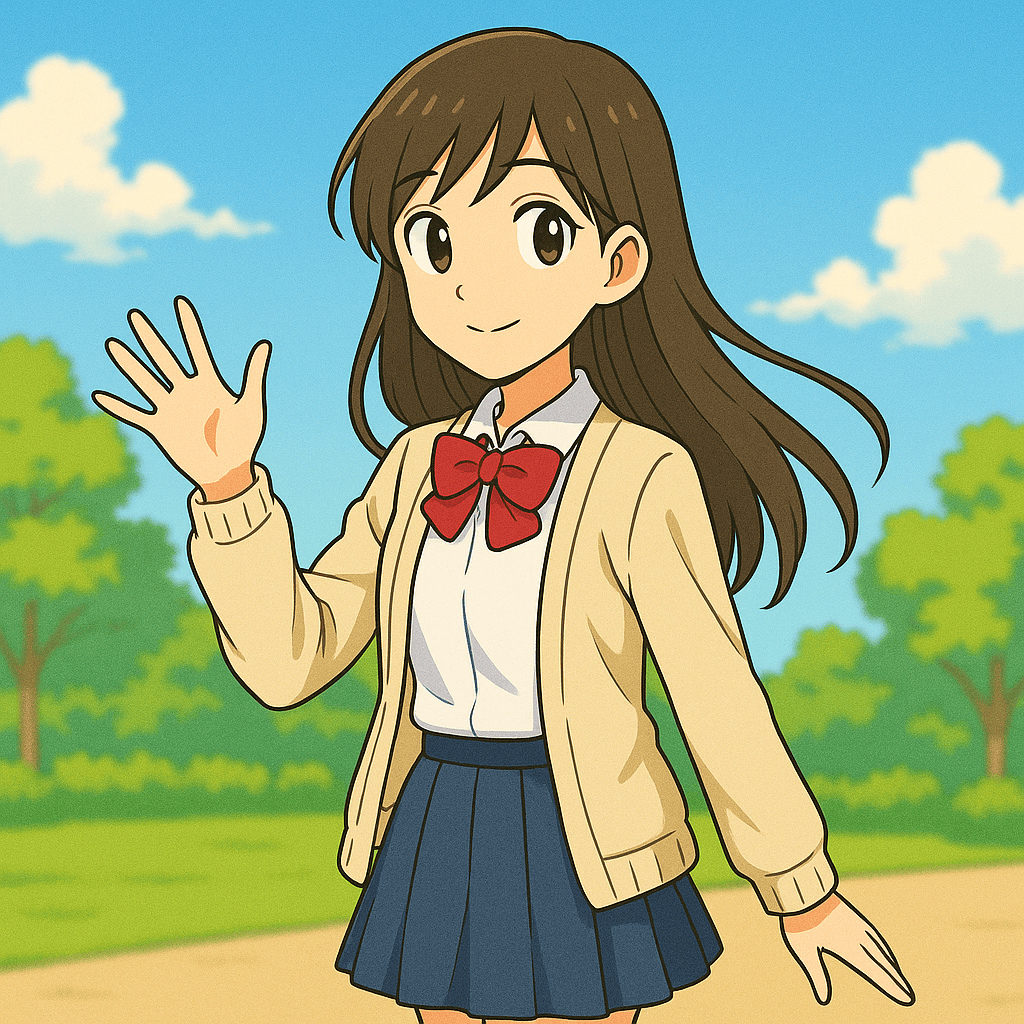
富士高校の数学テストは、
・標準問題を網羅的に素早く解く力
・範囲全体をカバーして穴を作らない対策
・難問は部分点狙いで無駄に時間を使わない姿勢
が求められます。
下位層~中間層の生徒はまず 「標準問題を完璧に」「範囲をすべて触る」 を徹底しましょう。
その上で、テスト本番は「時間配分を守り、部分点を取りに行く」。
これを実践すれば、「基礎力はあるのに点数が伸びない…」という壁を突破し、安定して平均点を超える力を身につけられます。
投稿者
荷川取
富士校舎の校舎長荷川取です!
▲▲クリックして荷川取のブログ一覧(85ブログ公開中)を見る