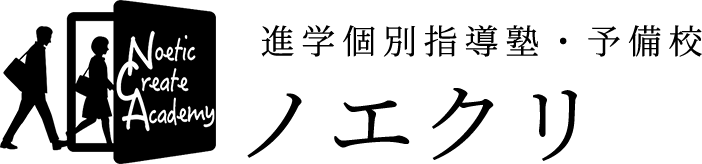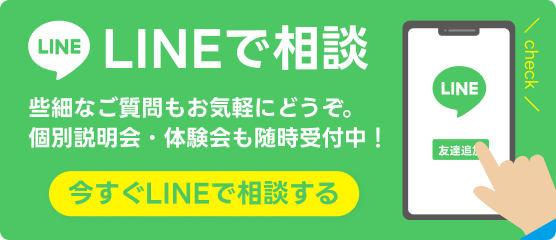集団授業で成績が上がらない人へ ―努力しているのに結果が出ない理由と、そこから抜け出す方法とは?
2025.10.7 有松校 鶴来校
窪田
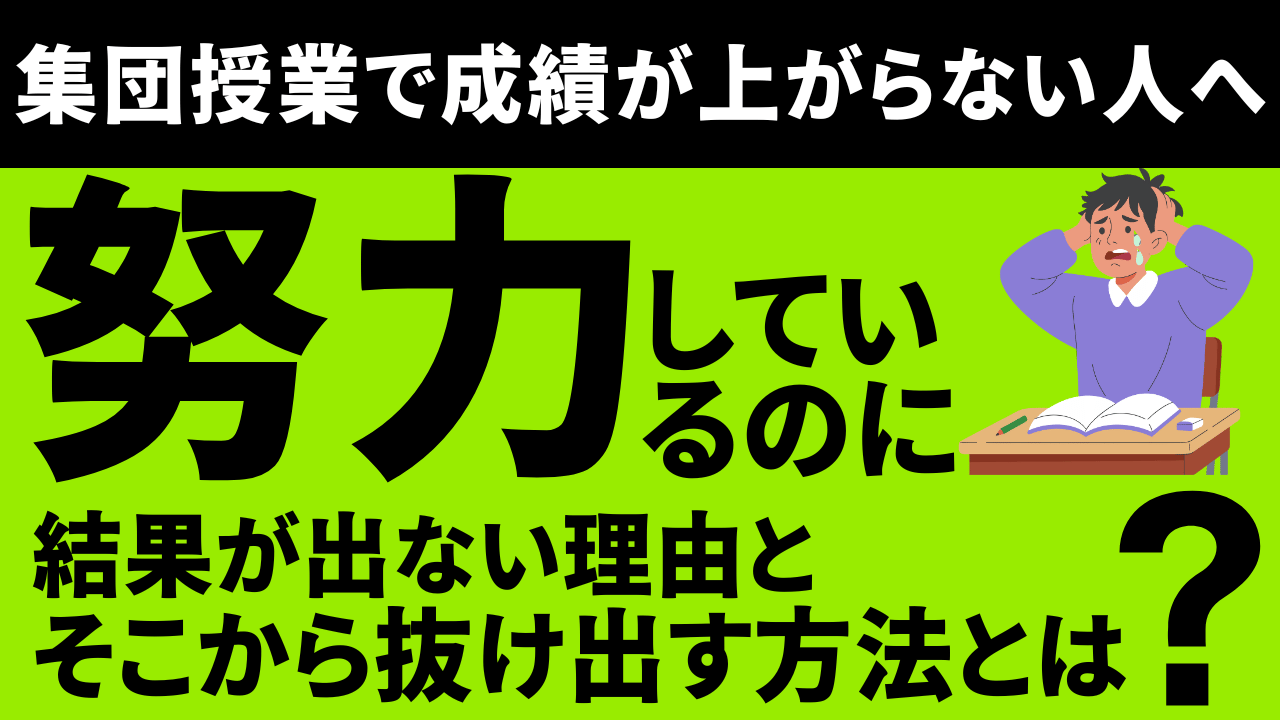
こんにちは、進学個別指導塾ノエクリ鶴来校・有松校の窪田です。
✅「授業中はわかっているつもりなのに、テストになるとできない。」
✅「ノートもちゃんと取ってるし、まじめに聞いてるのに、点数が上がらない。」
✅「みんなは伸びているのに、自分だけ置いていかれている気がする。」
そんな悩みを抱えている人いませんか?
実は、それは「あなたの努力が足りないから」ではありません。
むしろ、努力しているのに伸びないのは、「学び方の仕組み」が合っていないだけです。
中学生になると、学校や塾の授業スピードは一気に上がります。
その中で、集団授業のスタイルが自分に合わないと、どれだけ頑張っても成果につながりにくくなってしまいます。
この記事では、
✅「なぜ集団授業では成績が上がりにくいのか」
✅「どんなタイプの子が集団授業でつまずきやすいのか」
✅「どうすればできるようになるのか」
を解説します。
目次
まず知っておきたい、集団授業の「構造」
学校や大手進学塾の授業は、基本的に「クラス全員に同じ内容を教える」スタイルです。
これは効率が良く、一度に多くの生徒を指導できるという大きなメリットがあります。
しかし同時に、次のような構造的な欠点もあります。
① スピードが「平均」に合わせられている
授業のペースは、クラスの中間層に合わせて進みます。
なので、
・理解が速い子 → 「もうわかってる」と感じて退屈に。
・少し遅れ気味の子 → 「ついていけない」と焦って理解が浅くなる。
どちらも「授業を聞いているのに伸びない」状態に陥りやすいです。
② 質問しづらい雰囲気
集団授業では、先生の説明を止める勇気が必要です
「こんなこと聞いたら恥ずかしい」
「他の子はわかってるのに…」
そんな気持ちが働いて、わからない部分をそのままにしてしまう子がほとんどです。
③ 「わかったつもり」で終わる
授業を聞いているときは、「理解した気」になります。
でも、いざ自分で問題を解こうとすると手が止まる。
これは「受け身の理解」で、頭の中に「使える知識」として定着していない状態です。
つまり、集団授業は「教える効率」は高いけど、「身につく効率」は低くなりやすいのです。
努力しているのに上がらない人の共通点
ノエクリで多くの生徒を見てきましたが、「頑張ってるのに上がらない子」には共通点があります。
① ノートがきれいすぎる
一見よくできているように見えますが、「まとめること」が目的になっているケースが多いです。
ノートは「聞いた内容の記録」であり、「理解の証拠」ではありません。
本当に力がつくのは、「自分の言葉で説明できる」ようになったときです。
そしてもう一歩踏み込むなら、
「説明できる」=「頭の中でつながっている」ということ。
知識が「点」のままでは応用できませんが、自分の言葉で整理できると、「線」でつながり、別の問題でも使えるようになります。
つまり、勉強とは板書をきれいに写したり、聞いたことをそのまま覚えることではありません。
大切なのは、先生の言葉を自分の言葉・自分の思考に置きかえる力を育てることです。
先生の説明をそのまま受け取るのではなく、自分の頭で噛み砕き、理解した内容を「自分ならこう説明する」と言えるレベルまで落とし込めたとき、はじめて「理解が定着した」と言えます。
② 復習の「順番」が間違っている
授業後に復習をしていても、「できた問題」や「わかった内容」ばかりを繰り返している人が多いです。
それでは、時間をかけても“安心感”しか得られず、実力はなかなか伸びません。
本当に効果的な復習とは、
「できなかったところ」や「モヤモヤした部分」から先に潰していくことです。
たとえば、授業中に先生の解説を聞いて「なるほど!」と思った問題。
実はその直後にもう一度自力で解いてみると、意外と手が止まることがあります。
「なるほど」と思っただけで、まだ「自分の力」にはなっていません。
勉強は「わかった瞬間」より、「一人で再現できた瞬間」にこそ意味があります。
つまり復習とは、「昨日の自分ができなかったことを、今日できるようにする作業」なのです。
ところが、集団授業ではこの「できなかった部分」を先生が一人ひとり確認する時間がありません。
間違えた原因をその場で修正できず、「あとでやろう」と思っても、次の単元がすぐに始まってしまう。その繰り返しが、「努力しているのに伸びない」最大の要因になります。
ノエクリでは、生徒一人ひとりに「復習の順番」を教えています。
テスト前にただ範囲をやり直すのではなく、
「どこでミスしたか」「なぜ間違えたのか」を分析してから復習を始める。
この「順番の正しさ」が、成績を安定させる鍵になります。
③ 勉強法が「聞く中心」になっている
多くの中学生が、「授業を受ける=勉強している」と思い込んでいます。
確かに授業を聞くことは大切です。
しかし、「聞く」だけでは頭の中に情報が一方通行で流れ込み、「理解したつもり」だけが積み重なっていく状態になります。
勉強とは、本来「考える行為」です。
知識を自分の頭の中で整理し、「なぜそうなるのか」を自分で説明できるようになってはじめて、理解が定着します。
たとえば、英語の文法で「to+動詞の原形」と聞いたとき、「覚えたから書ける」ではなく、
「なぜ、toのあとが原形なのか?」
「この文で、to studyとstudyingの違いは?」
などと、自分の頭で問いを立てる習慣が必要です。
この「問いを立てる力」こそが、勉強の本質です。ノエクリでは、講師が一方的に解説する時間よりも、生徒が自分で考え、答えを導く時間を重視しています。
また、聞くだけの勉強は「インプット中心」ですが、成績を上げるためには「アウトプットの量」を増やさなければなりません。
・実際に手を動かして問題を解き、自分で説明してみる。
・その中で間違え、修正し、再び挑戦する
この反復の中でしか、本当の理解は育ちません。
つまり、勉強=「どれだけ聞いたか」ではなく、勉強=「どれだけ自分の頭で考えたか」です。
授業を「受ける時間」から「自分の脳を使う時間」に変えた瞬間、成績は確実に動き出します。
ノエクリ式「考える授業」──「聞く」から「考える」へ、学びを変える時間
多くの生徒は、授業を「受けるもの」だと思っています。
でも、成績が上がるのは「教わったあとに、自分で考えた時間」がある生徒です。
ノエクリでは、授業を「聞く時間」ではなく、「考える時間」に変えるための仕組みを設けています。
その中心にあるのが、「質問」と「説明」の習慣です。
授業中に必ず「質問」がある
・講師が問題を解いたあとに「なんでその答えになったの?」
・「もし数字が変わったら、どうなると思う?」
生徒はその質問に、自分の言葉で説明します。
口に出して話すことで、自分の理解度を“自分自身で”確認できます。
間違えたときも、講師がすぐに答えを教えるのではなく、
「どこで考えがズレたのか」を自分で言語化するよう促します。
このプロセスを繰り返すうちに、
「答えを覚える」から「答えの出し方を理解する」へと学びが変わります。
「わかった」から「できる」へ
授業を受けて「わかった気」になるのはスタートラインです。
本当に大事なのは、そこから「できるようになる」まで練習すること。
ノエクリの授業では、解き方を聞いて終わりではなく、
自分で解ききる時間を必ず設けています。
講師はその過程を横で見取り、思考のズレをその場で修正。
この一問一問の積み重ねが、「テストで使える本物の力」に変わっていきます。
勉強が嫌いな子ほど、変われる
勉強が嫌いになる一番の原因は、「頑張ってもできない」経験です。
それは甘えではなく、努力が報われない体験の積み重ねです。
ノエクリでは、
・苦手な単元を前の学年までさかのぼってやり直す
・小さな成功をその場でしっかり褒める
・次にやるべきことを一緒に決める
といったサポートを大切にしています。
こうして「できた!」という成功体験を一つずつ積み上げていくことで、勉強に対する自己肯定感が少しずつ戻っていきます。
この「考える → できる → 自信に変わる」サイクルこそ、ノエクリが最も大切にしている学び方です。
一夜漬けの暗記では身につかない「本物の学力」は、こうした日々の思考と努力の積み重ねから生まれます。
そして、その積み重ねが、「もう無理かも」を「やればできる」に変えていきます。
まとめ
ノエクリにも、集団塾から転塾してきた生徒がいます。
最初は「自分は頭が悪い」と思い込んでいた子が、半年後には「勉強が楽しい」「次は90点を狙う」と笑顔で言うようになります。
彼らが変わったのは、「わからない理由」を自分で理解できたから。
「自分には無理」ではなく、「こうすればできる」と思えるようになった瞬間、行動が変わります。
そしてその変化のきっかけを一緒に見つけることが、私たち講師の仕事です。
どれだけ努力しても、間違った方法で続ければ成果は出ません。
集団授業が悪いわけではありませんが、そこに合わない生徒がいるのも確かです。
・授業中はわかるのにテストで点が取れない
・質問できずにモヤモヤしたまま終わる
・一度つまずくと立て直せない
そんな子ほど、「自分専用の学び方」を持つことが必要です。
勉強は、「みんなと同じやり方」ではなく、「自分に合った方法」を見つけた瞬間に変わります。
ノエクリは、ただ点数を上げるだけの塾ではありません。
「わかる」「できる」「自信がつく」
その循環を一緒に育てていく場所です。
お子さまの努力が、しっかり実を結ぶように、私たちが伴走します!

投稿者
窪田
有松校・鶴来校の窪田です!
▲▲クリックして窪田のブログ一覧(158ブログ公開中)を見る