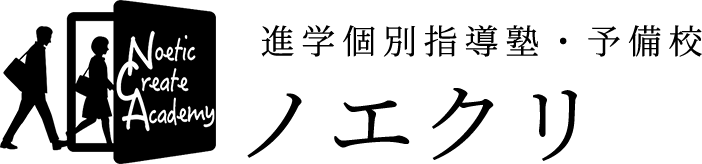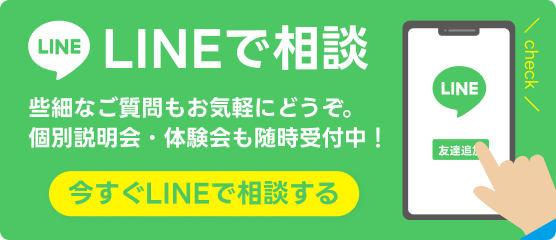数列が嫌いな人へ|群数列2大パターンを完答する3つの神ワザ
2025.11.4 富士校
荷川取
目次
群数列とは
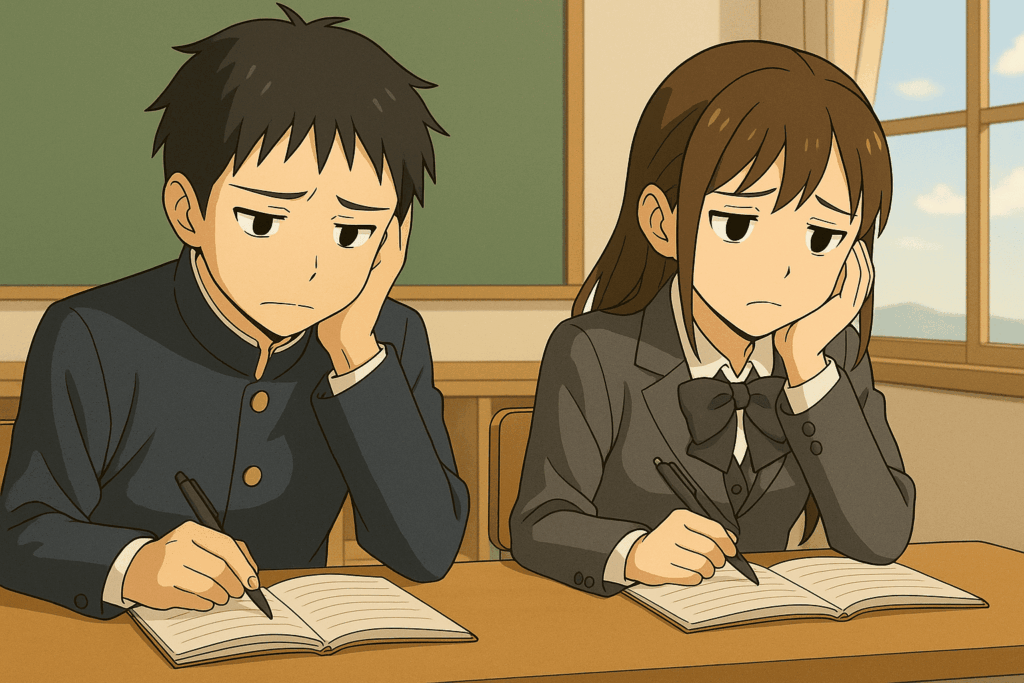
数列の並びを「第1群」「第2群」…のようにかたまり(群)で区切る問題です。
例:
第1群:1
第2群:2,2
第3群:3,3,3
第4群:4,4,4,4 …
→ 何個で1群か、各群の中身がどう決まるか、を最初に読み取ります。
群数列の2大パターン
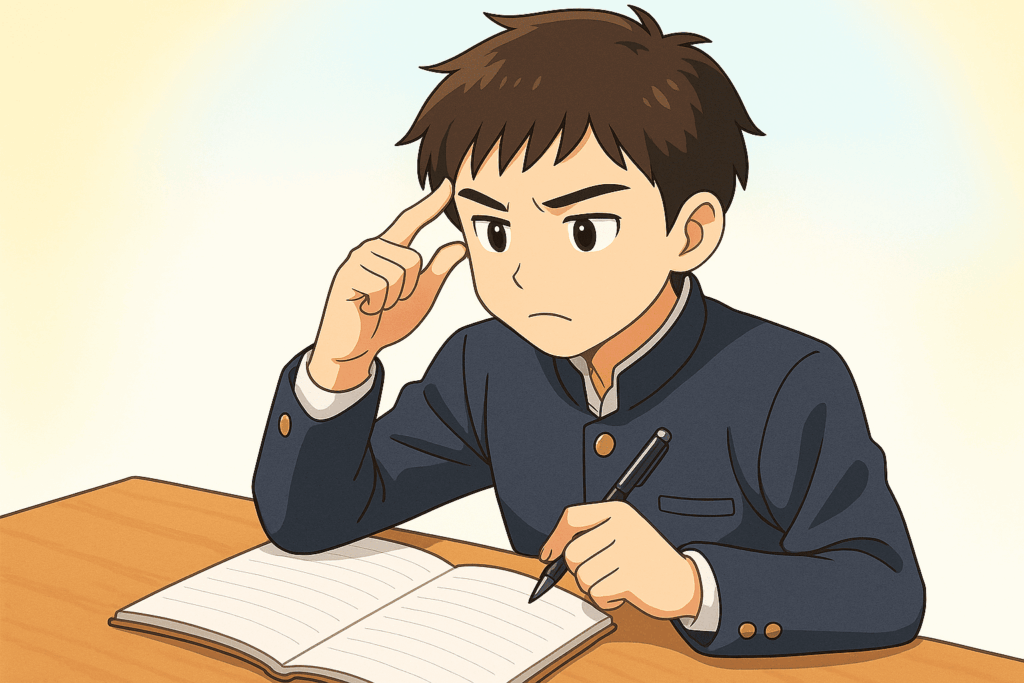
群数列の問題では、群(しきり)を取り去った数列を見抜くことが最初のポイントです。
パターンは大きく分けて2つあります。
| パターン | 読み取りポイント | よくある数列の例 |
|---|---|---|
| 等差・等比型 | 各群の中身が等差 or 等比になっている | 2,4|6,8,10|12,14,16,18… |
| 特殊並び型 | 「kをk個」など群ごとの規則で数を並べる | 1|2,2|3,3,3|4,4,4,4… |
※ どちらでも共通して行うのは
①第n群に含まれる項数
②累積項数(第n群の初項は、初めから数えて何番目か)
の2つの把握です。この『n群をつかまえる』のが2つ目のポイントです。
群数列の3つの神ワザ
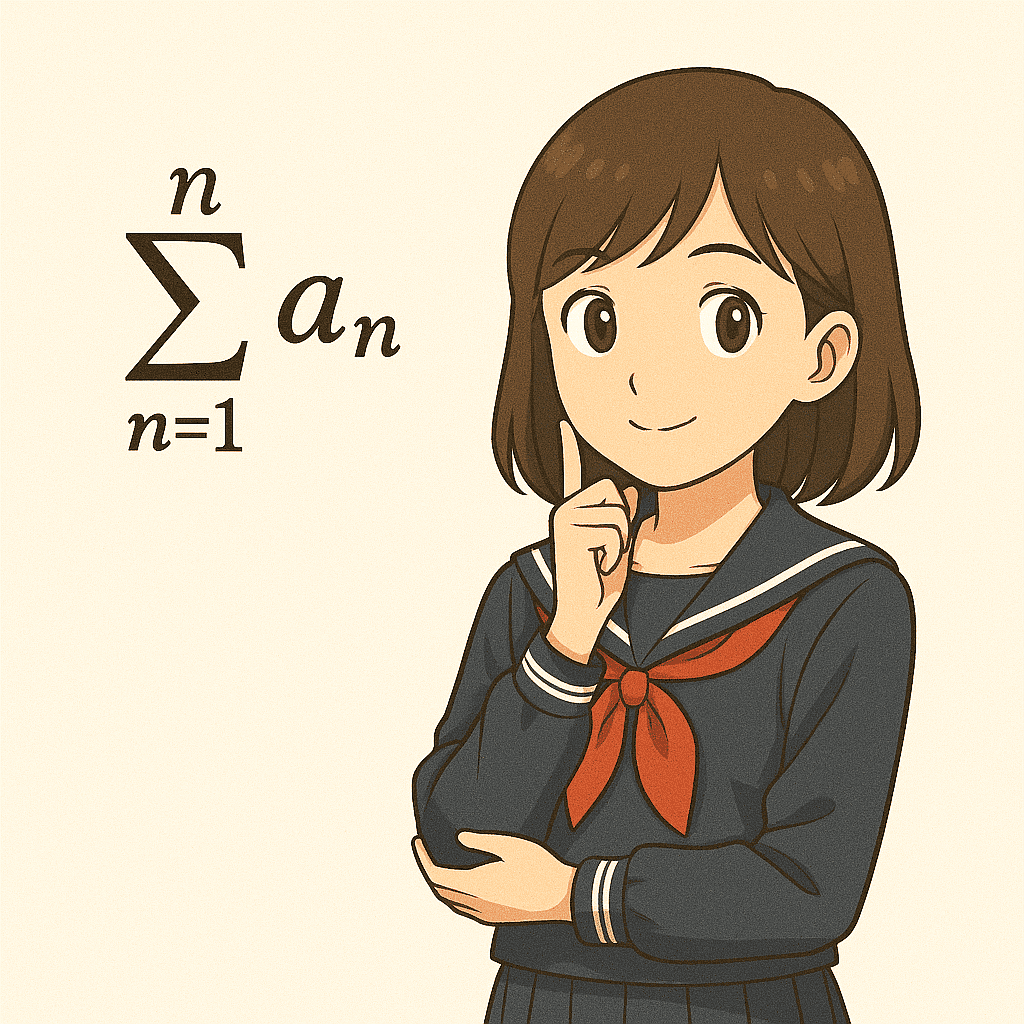
①初項の神ワザ:
1. 第(n−1)群までの累積項数 \(S_{n-1}\) を作る
→n-1群の末項が「初めから数えて何番目か」
2. 元の数列の一般項 \(a_m\) を用意
→あえて文字を変えておくと、それぞれの文字が表す「群」「何番目」を整理できる
3. \(m=S_{n-1}+1\) を aₙ に代入 →「第n群の初項」
②群数列の和の神ワザ:
1. 「第k群の和」を求める
2. 「第k群の和」を Σ(シグマ)で足し合わせる。順番は必ず 群内 → 全体。
③位置特定問題の神ワザ:
1. 第n群までの累積項数 \(S_n\) を作る\[(例:1+2+…+n =\frac{1}{2}n(n+1) など)\]
2. 「n群に含まれる」と仮定し、不等式を立てる
不等式 :n-1群までの累積項数\(S_{n-1} < n ≤ n群までの累積項数S_n \)
3. 具体的数値を代入して、不等式を満たすnを探し当てる
4. 3.で求めた群の中で、何番目にあるのかを数える
どの群数列でも必須!第n群の初項を求める
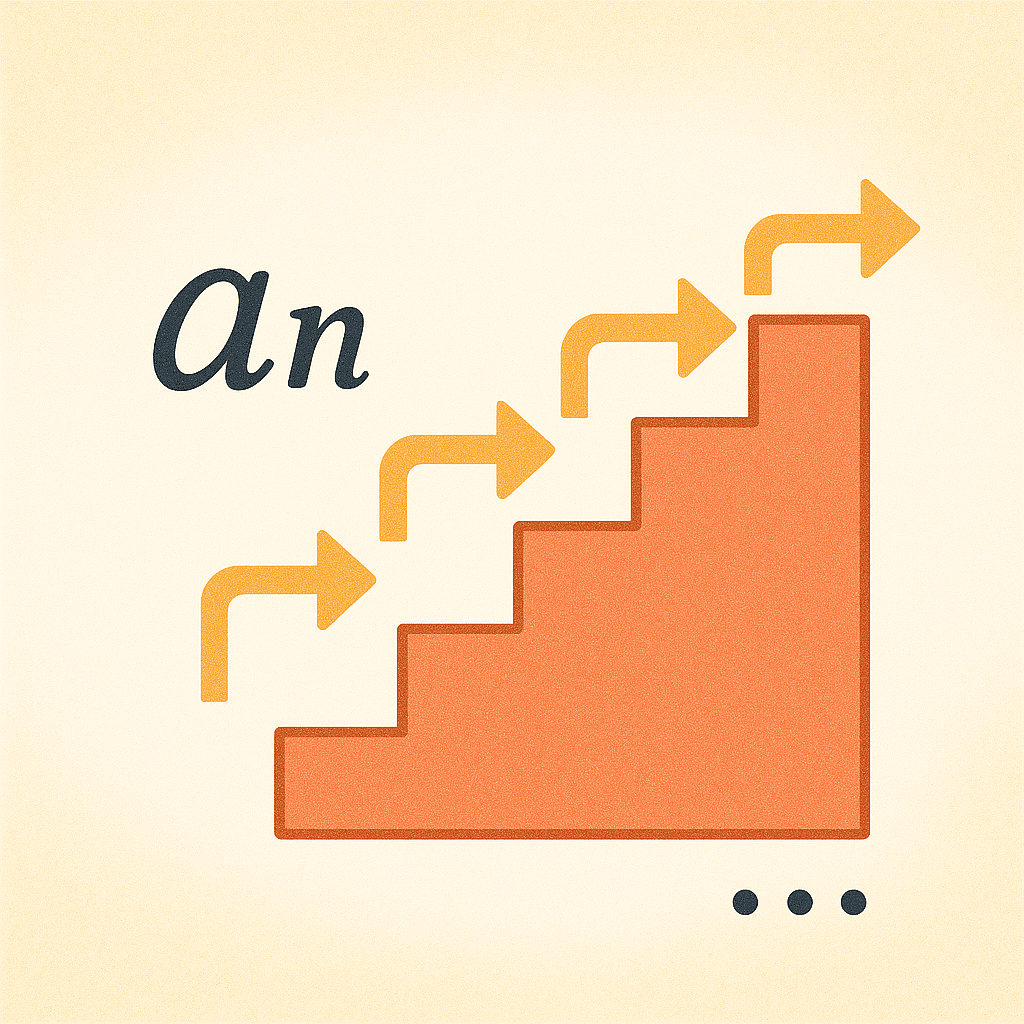
n群の初項の神ワザ
① 第(n−1)群までの累積項数 \(S_{n-1}\) を作る
→n-1群の末項が「初めから数えて何番目か」
② 元の数列の一般項 \(a_m\) を用意
→あえて文字を変えておくと、それぞれの文字が表す「群」「何番目」を整理できる
③ \(m=S_{n-1}+1\) を aₙ に代入 →「第n群の初項」
等比型の例
初項1、公比2 の等比数列:1,2,4,,16,…を
「第1群=2個,第2群=4個,第3群=6個…(第k群=2k 個)」に区切る。
→|1,2|4,8,16,32|64,128,256,512,1024,2048|…
第n群の初項を求めよ。
Step ①: 第(n−1)群までの累積項数 \(S_{n-1}\) を作る
→n-1群の末項が「初めから数えて何番目か」
(第1群〜第(n−1)群)
\[2 + 4 + \cdots + 2(n-1) = 2(1+2+\cdots+(n-1)) = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = n(n-1)\]
→ ここが 累積項数 \(S_{n-1}\) 。
Step ②:元の数列の一般項 \(a_m\) を用意
→あえて文字を変えておくと、それぞれの文字が表す「群」「何番目」を整理できる
等比: \(a_m = 1\cdot 2^{\,m-1} = 2^{\,m-1}\)
Step ③: \(m=S_{n-1}+1\) を aₙ に代入
→「第n群の初項」
\[a_{m} = 2^{\,\{\,n(n-1)+1\,\}-1} = 2^{\,n(n-1)}\]
第k群の初項:
\[2^{\,n(n-1)}\]
頻出問題①群数列の和の求め方

群数列の和の神ワザ
①「第k群の和」を求める
② 「第k群の和」を Σ(シグマ)で足し合わせる。順番は必ず 群内 → 全体。
例:1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,… の和
この数列は1群に項(1)が1個、2群は2が2個、3群は3が3個、…となっているので、「第k群には k が k 個並ぶ」。
第k群:k, k, …(k個)
↓
第k群の和:kがk個あるから、k × k = k²
第n群までの総和
\[\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\]
→ \(Σ\)の公式どおり!。
頻出問題②「○○は第何群の何番目?」
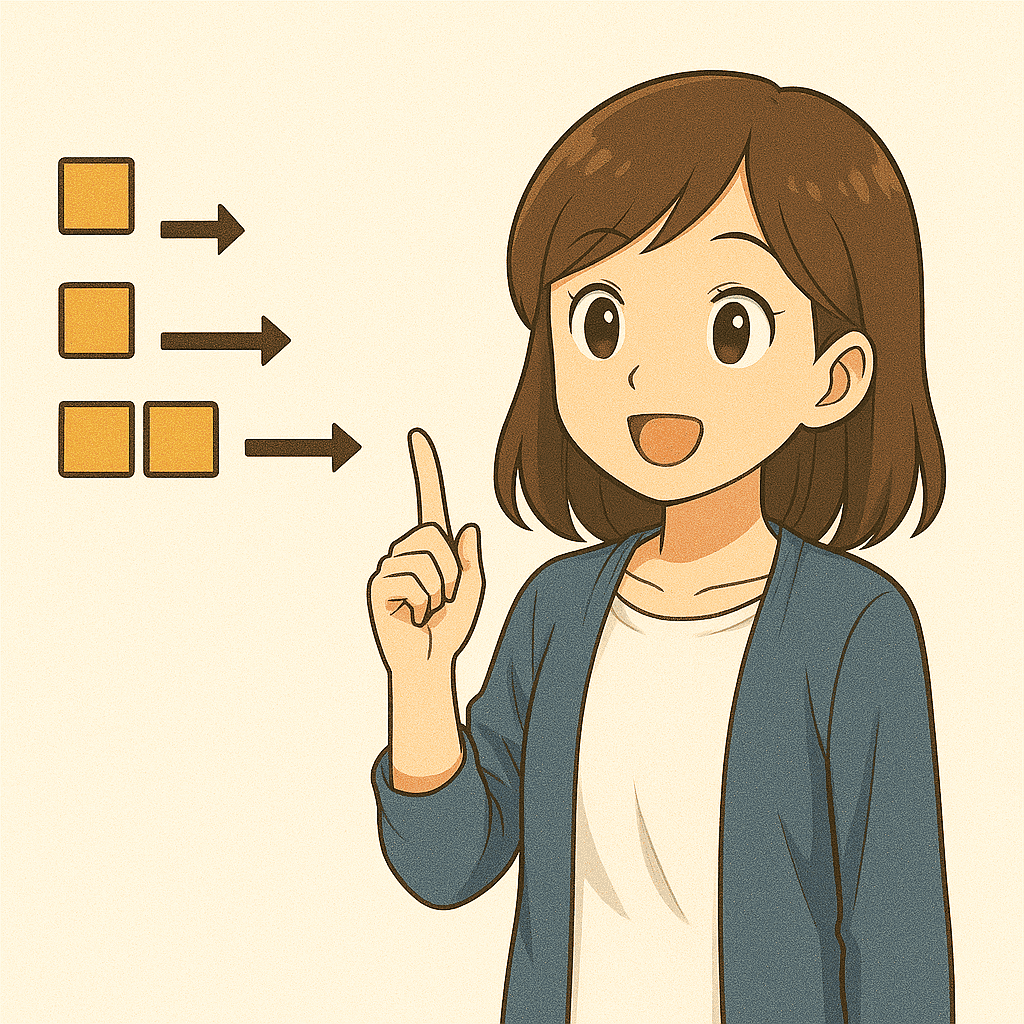
位置特定問題の神ワザ
① 第n群までの累積項数 \(S_n\) を作る\[(例:1+2+…+n =\frac{1}{2}n(n+1) など)\]
② 「n群に含まれる」と仮定し、不等式を立てる
不等式 :n-1群までの累積項数\(S_{n-1} < n ≤ n群までの累積項数S_n \)
③ 具体的数値を代入して、不等式を満たすnを探し当てる
④ ③で求めた群の中で、何番目にあるのかを数える
等差型の例
数列: 2|4,6|8,10,12|14,… を考える。
第k群に含まれる項数がk個になるように区切る。
このとき、32 は第何群の何番目の項か。
Step ①: 第n群までの累積項数 \(S_n\) を作る
\[(例:1+2+…+n =\frac{1}{2}n(n+1) など)\]
\[S_n=1+2+⋯+n= \frac{k(k+1)}{2}\]
Step ②:「n群に含まれる」と仮定し、不等式を立てる
不等式 :n-1群までの累積項数\(S_{n-1} < n ≤ n群までの累積項数S_n \)
等差数列の一般項: \(a_n = 2n\)(初項2、公差2)
\(32 = 2n → n=16\)
32 は第16項。よって、
Sₖ₋₁ < 16 ≤ Sₖ
Step ③:具体的数値を代入して、不等式を満たすnを探し当てる
n=5 のとき \[S_5 = \frac{5\cdot6}{2}=15 → 15 < 16\]
n=6 のとき \[S_6 = \frac{6\cdot7}{2}=21 → 16 ≤ 21\]
→ 第6群 に入る。
Step ④:③で求めた群の中で、何番目にあるのかを数える
16 − S₅ = 16 − 15 = 1番目。
答え:第6群の1番目の項。
確認用の並べ書き
第1群: 2
第2群: 4, 6
第3群: 8, 10, 12
第4群: 14, 16, 18, 20
第5群: 22, 24, 26, 28, 30
第6群: 32, 34, 36, 38, 40, 42
↑第16項=第6群の1番目つまずきやすい点と対処
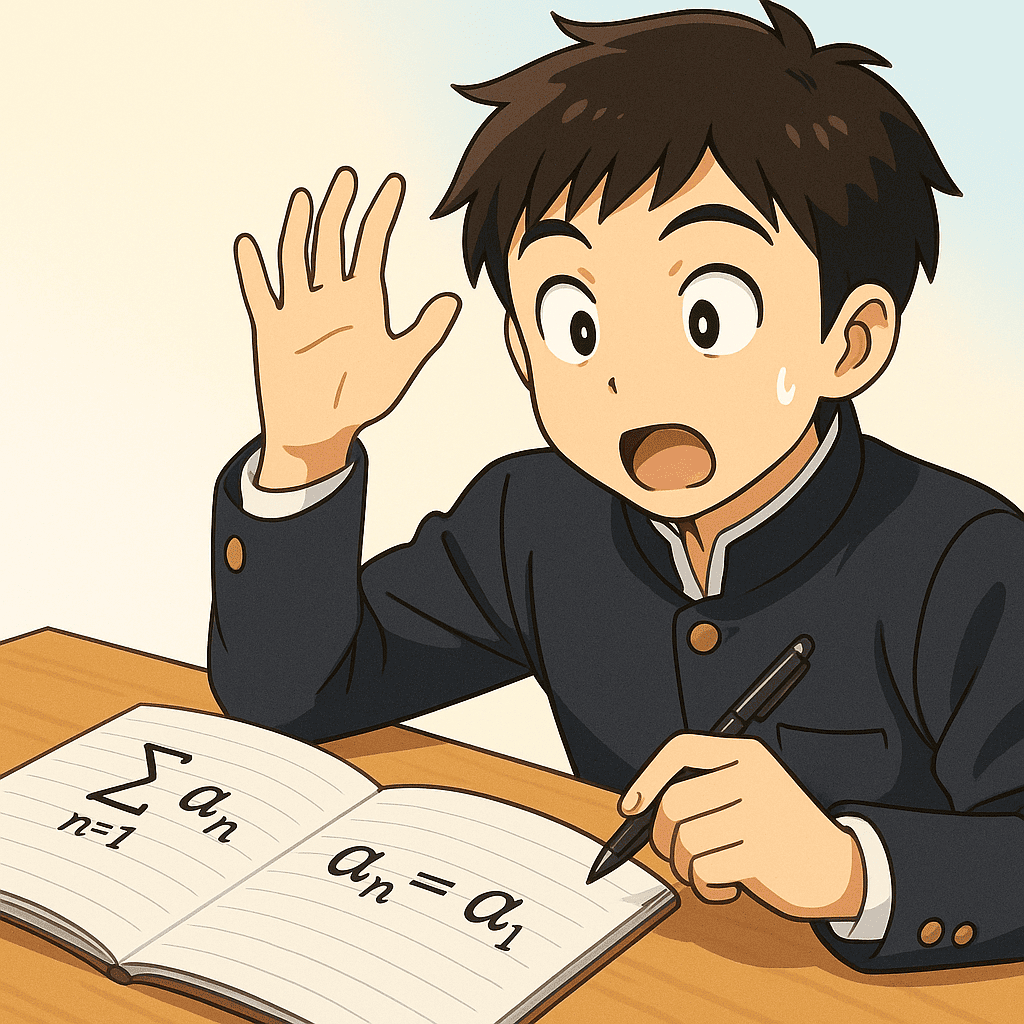
①群の長さを先に確定
第k群に何個あるかを書き出す。
②「項数の和」から、「k群の末項が初めから数えて何番目か」を求める
1,3,6,10,15,… や ½k(k+1) を毎回書く。
③不等式は初項(または初項が何番目か)と末項(または末項が何番目か)で挟む
Sₖ₋₁ < n ≤ Sₖ の形を崩さない。
④順序を守る
初項→群和→Σ、または n→不等式→差。
⑤図で補助
群の区切り線、累積の位置、群内番号を書き込む。
まとめ
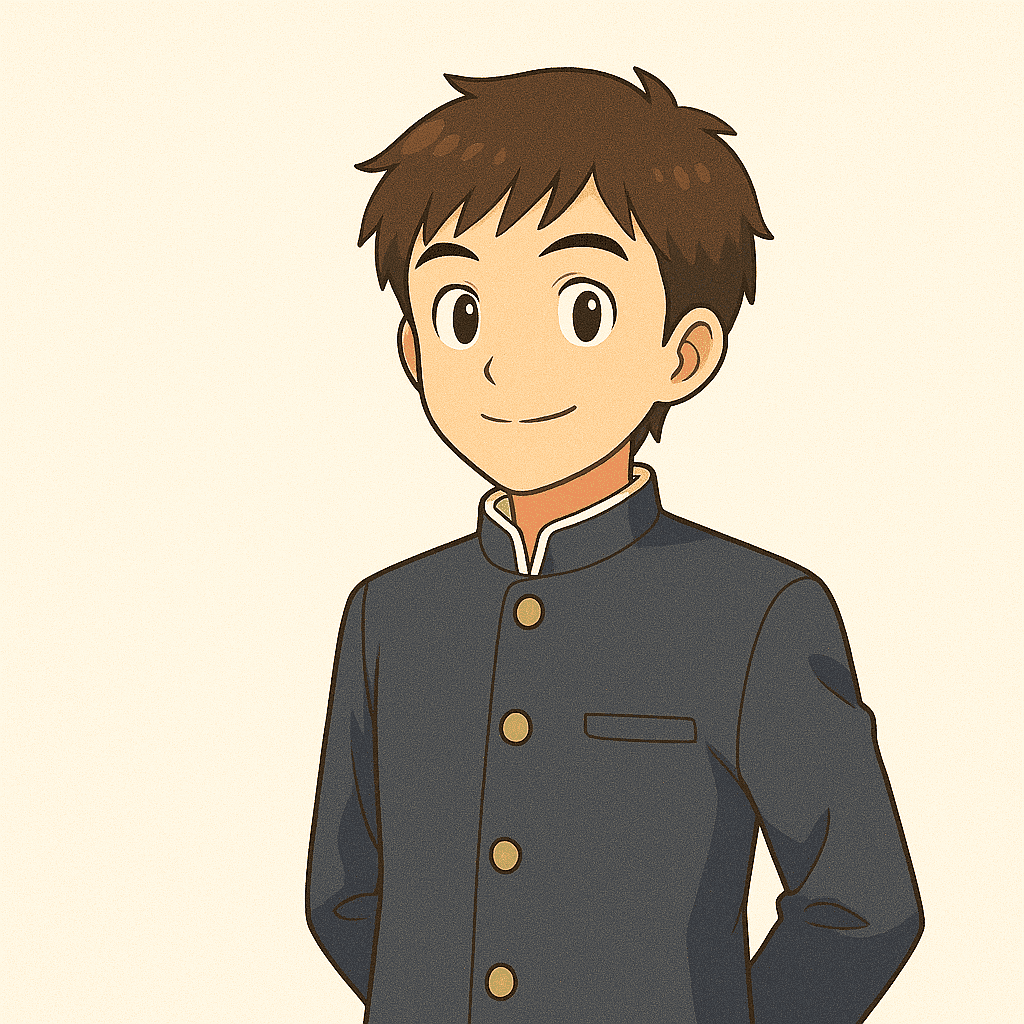
神ワザ3つのおさらい
①初項の神ワザ:
1. 第(n−1)群までの累積項数 \(S_{n-1}\) を作る
→n-1群の末項が「初めから数えて何番目か」
2. 元の数列の一般項 \(a_m\) を用意
→あえて文字を変えておくと、それぞれの文字が表す「群」「何番目」を整理できる
3. \(m=S_{n-1}+1\) を aₙ に代入 →「第n群の初項」
②群数列の和の神ワザ:
1. 「第k群の和」を求める
2. 「第k群の和」を Σ(シグマ)で足し合わせる。順番は必ず 群内 → 全体。
③位置特定問題の神ワザ:
1. 第n群までの累積項数 \(S_n\) を作る\[(例:1+2+…+n =\frac{1}{2}n(n+1) など)\]
2. 「n群に含まれる」と仮定し、不等式を立てる
不等式 :n-1群までの累積項数\(S_{n-1} < n ≤ n群までの累積項数S_n \)
3. 具体的数値を代入して、不等式を満たすnを探し当てる
4. 3.で求めた群の中で、何番目にあるのかを数える
このテクニック3つを習得すれば…
・青チャートの群数列の問題がすべて解ける!
・模試や入試での群数列の問題がすべて解ける!
入試最頻出問題の1つ、『群数列』をノエクリでできるようにしませんか?
ノエクリの授業なら、この群数列が1回60分の授業でできるようになる!
さらに、60分×10回の授業で『数列』の解法すべてを習得できる!
共通テストで必出、二次試験でも頻出の『数列』を冬で得点源にしたい人はこちらから。
投稿者
荷川取
富士校舎の校舎長荷川取です!
▲▲クリックして荷川取のブログ一覧(85ブログ公開中)を見る