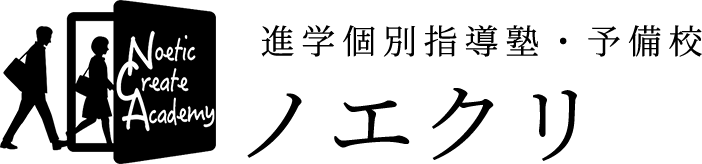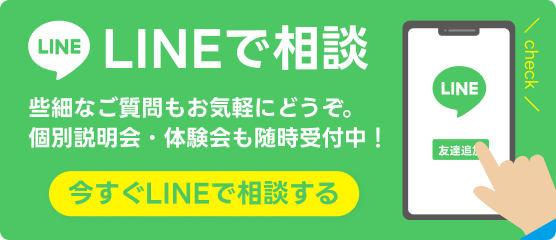【旧帝志望必見】現代文攻略への道
2025.9.30 小松校 松任校
清水
【旧帝志望必見】現代文攻略への道

「旧帝大の現代文は、文章が難解で、何が言いたいのか掴みきれないまま時間が過ぎてしまう…。」
そんな悩みを抱えていませんか。多くの受験生が、現代文を「センス」や「読書量」で決まる科目だと誤解しています。また、勉強しても点数があまり伸びないと思っています。
しかし、それは大きな間違いです!旧帝大が求めるのは、文学的な感受性ではなく、複雑な情報の中から筆者の主張の論理構造を正確に読み取り、設問の要求に応じて状況を把握する力です!この能力は、才能ではなく、正しいトレーニングによって誰でも身につけることができます。
この記事では、感覚的な読解から脱却し、旧帝現代文をクリアするための具体的な思考プロセスを解説していきます。もう「なんとなく」で選択肢を選んだり、記述の解答欄を埋めたりするのは終わりにしましょう。
全ての始まりは「設問分析」にあり
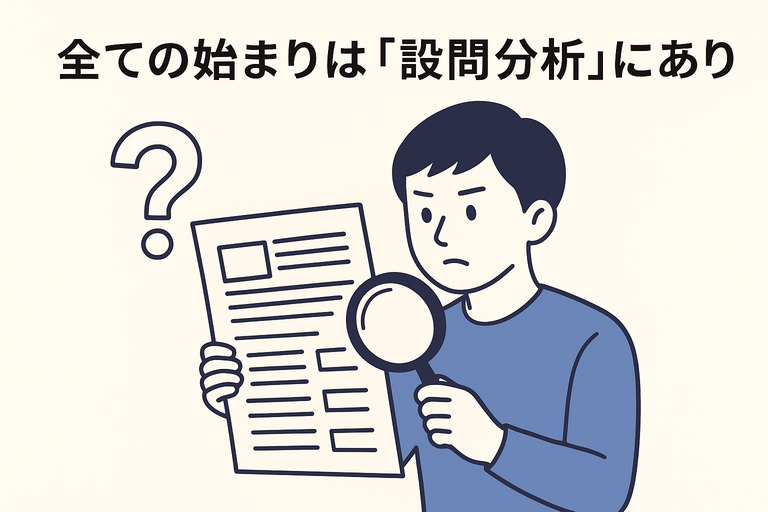
多くの受験生が、試験開始の合図と共にいきなり本文を読み始めますが、これは羅針盤を持たずに航海に出るようなものです。目的地を知らずに進んでも、必要な情報を見つけることはできません。旧帝現代文の攻略は、本文を読む前に「設問を徹底的に分析する」ことから始まります。なぜなら、設問こそが、これから読むべき文章のどこに注目し、どのような情報を集めればよいのかを教えてくれる「地図」そのものだからです。
例えば、「傍線部Aについて、どういうことか説明せよ」という問いと、「傍線部Bについて、なぜそう言えるのか説明せよ」という問いでは、解答に盛り込むべき要素が全く異なります。前者は傍線部の内容を分かりやすく言い換えること(What?)が求められ、後者はその理由や根拠(Why?)を明確にすることが求められます。この設問の要求を最初に把握することで、本文を読む際の意識が劇的に変わります。ただ漫然と文字を追うのではなく、「言い換えられている部分を探そう」「理由を述べている箇所に印をつけよう」という目的を持った読解が可能になるのです。
また、大学毎に問われ方はもちろん、文字数や行数がある程度決まっていますので、自分の受ける大学について知らない人は、今すぐに確認しましょう!
本文は「構造」で読む
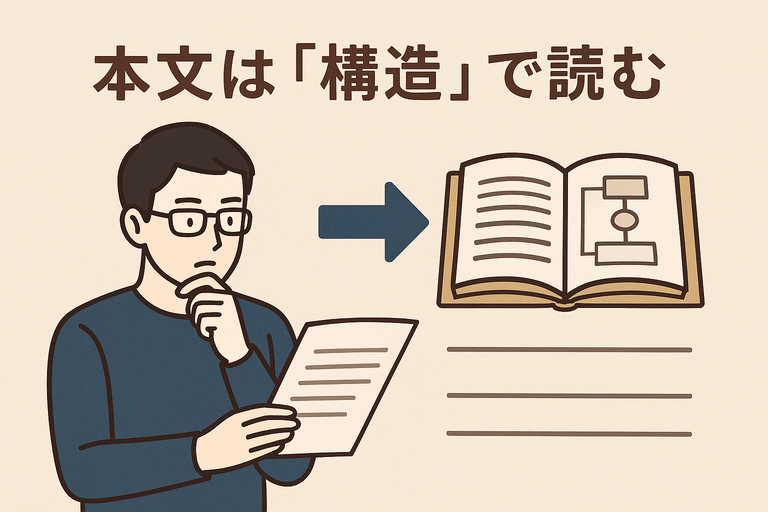
設問という名の地図を手に入れたら、いよいよ本文という名のフィールドに入っていきます。ここでの目的は、文章全体の意味を完璧に理解することではありません。設問が要求する情報を、効率よく、かつ正確に探し出すことです。そのために有効なのが、文章を「論理構造」で捉える読み方です。特に意識すべきなのは、「対比」「言い換え」「因果関係」の三つの関係性です。ただし、文章全体の意味をとれる力をとれる人の方が点数は取れます!
対比は、筆者が最も主張したいことを際立たせるために使われる論理の型です。例えば「西洋の個人主義」と「日本の集団主義」のように、二つの概念を比較しながら論が進む文章は非常に多く見られます。このAとBの対立構造を意識し、どちらの要素が筆者の主張に近いのかを把握することで、文章の大きな幹を見失うことがなくなります。
次に言い換えです。難解な文章ほど、筆者は抽象的な概念や専門用語を、より具体的な言葉や身近な例えを用いて繰り返し説明しようとします。「つまり」「すなわち」「要するに」といった接続詞は、言い換えの明確なサインです。この言い換えられている部分こそ、筆者の主張の核心であり、設問で問われる「どういうことか」の直接的な解答根拠になる場合がほとんどです。
そして因果関係。「なぜなら」「したがって」「〜のため」といった言葉で結ばれる、原因と結果の流れを正確に捉えることは、「なぜか」を問う設問に答えるための必須作業です。この関係性を見つけることで、単なる事象の羅列ではなく、論理的な繋がりとして文章を立体的に理解できるようになります。
本文を読む際には、対比関係にある語句を線で囲んで対立させたり、言い換え関係にある部分を矢印で結んだり、因果関係を矢印で示したりと、自分なりのルールで情報を視覚的に整理していくことが極めて重要です。この作業によって、頭の中だけで処理していた複雑な情報が整理され、解答の根拠となる部分が一目でわかるようになります。
解答は「本文の言葉」で組み立てるジグソーパズル
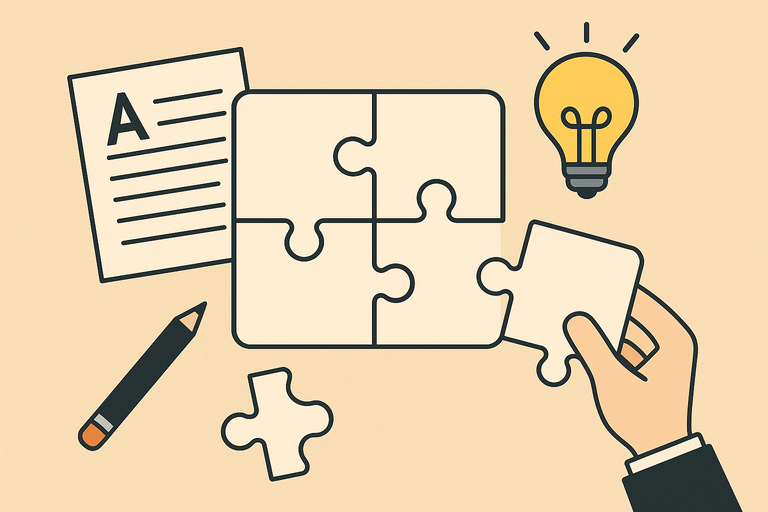
設問分析で解答の設計図を作り、構造的な読解で必要な情報(ピース)を集めたら、最後の工程は解答作成です。記述問題で多くの受験生が陥るのが、「自分の言葉でまとめよう」として、本文からかけ離れた内容を書いてしまうことです。旧帝現代文の採点基準は非常に厳格であり、「本文に書かれている内容を、設問の要求に合わせて論理的に再構成できるか」ということが非常に重要です!
もちろん、本文に直接書かれていないことを要求されることもありますが、その話はまた別の機会に!
解答作成は、ジグソーパズルに似ています。本文から集めてきた解答の根拠という名の「ピース」を、設問分析で作った設計図(解答の枠組み)に、過不足なく当てはめていく作業です。
具体的な手順としては、まず、設問の要求(「〜はどういうことか」)に答えるために必要だと判断した本文中のキーワードやキーフレーズを抜き出します。次に、それらの要素を、意味が通じるように、かつ論理的な順序になるように並べ替えます。最後に、「〜は、〜という点と、〜という点から、〜ということ。」のように、必要最小限の助詞や接続詞を補い、一つの完成された文章に仕上げます。このプロセスにおいて、自分の主観的な言葉を差し挟む余地は一切ありません。あくまで本文にある言葉を素材として、客観的に解答を組み立てることが高得点の鍵です。
私が指導している中で、「日本語とし正しい」と生徒に問いかけることがよくあります。多くの学生が記述の際に陥ることは、「主語と述語が一致していないこと」、また、「日本語として文章が成り立っていないこと」です。自分の書いた文章を客観的に振り返ることもとても大切なことですね。
最後に
旧帝現代文を攻略するために必要なのは、曖昧なセンスではなく、設問分析・構造読解・論理的解答構成という、一連の明確な技術です。これらの技術は、正しい読み方・解き方を意識して過去問演習を繰り返すことで、必ず上達します。今日から、本文を読む前に設問をじっくりと眺めること、文章の中の対比や言い換えに印をつけながら読むことを始めてみてください。一つ一つの作業を丁寧に行うことが、難攻不落に見えた旧帝現代文という巨大な壁を乗り越える、最も確実な一歩となるはずです。
正しい読み方・解き方を身に付けたい方は、是非ノエクリの国語の授業を受けて下さい。国語の力を劇的に変えます!
ノエクリの授業を受けることで、国語の偏差値を10以上上げた生徒がたくさんいます!
以下のURLからお問い合わせLINEへご連絡頂ければと思います!
投稿者
清水
小松校舎の清水です!
▲▲クリックして清水のブログ一覧(45ブログ公開中)を見る