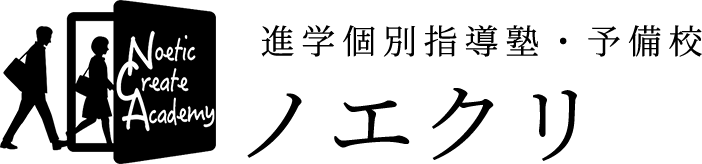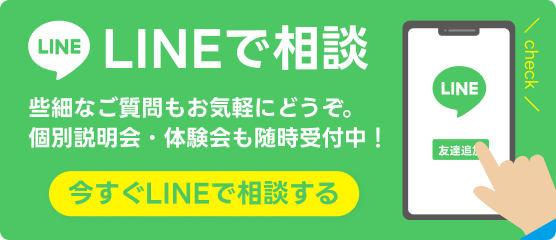富士市の高校1~2年生がMARCHを狙う勉強法|今から始める合格戦略
2025.10.14
荷川取
目次
はじめに
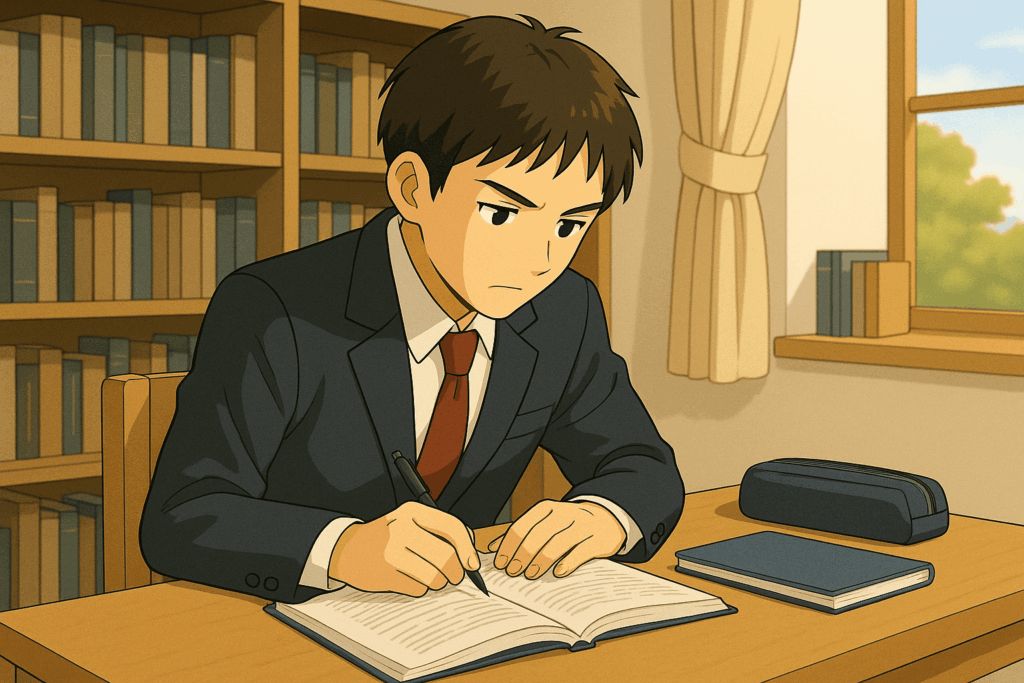
「MARCHに行きたいけど、どこから始めたらいいのかわからない」
「まだ高2だけど、このままで間に合うのかな…」
そんな声を、富士高校や富士市内の進学校に通う生徒からよく聞きます。
MARCH(明治・青学・立教・中央・法政)は、難関私大の中でも高難易度の問題が出る実力校。
だからこそ、高1・高2のうちに「基礎力+思考力」を鍛えておくことが合格のカギになります。
この記事では、富士市の高校1〜2年生がMARCH合格をつかむための、科目別・時期別の勉強法を具体的に紹介します。
MARCH合格に必要な学力の目安
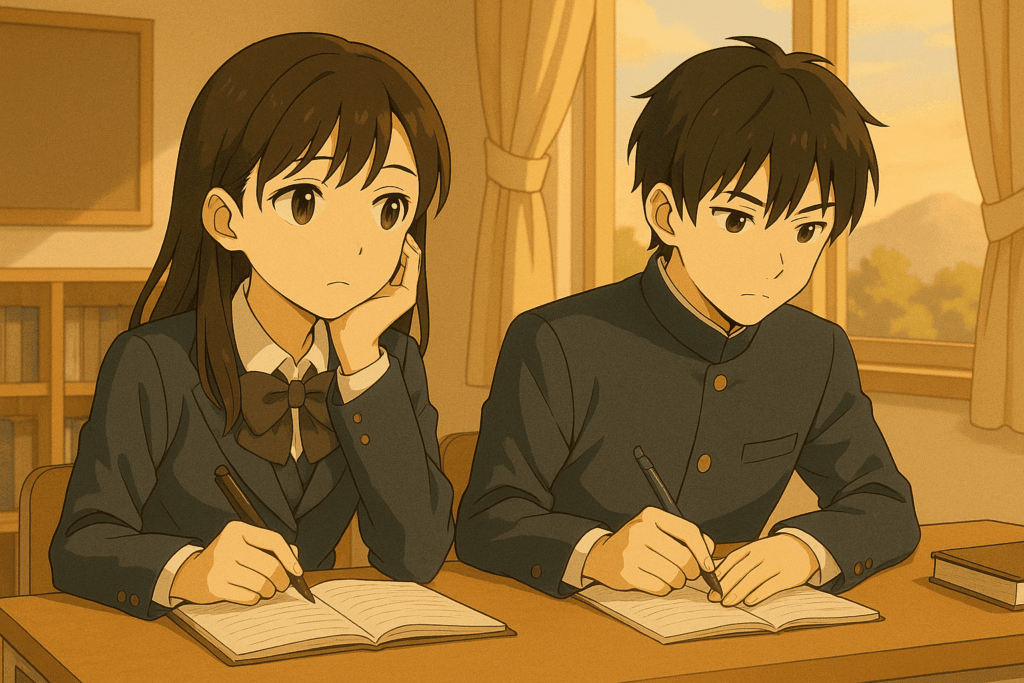
MARCHは全国でも人気が高く、合格ラインは年々上昇しています。
おおよその目安は以下の通りです:
| 大学名 | 共通テスト得点率の目安 | 偏差値帯(一般入試) |
|---|---|---|
| 明治大学 | 約80〜83% | 62〜65 |
| 青山学院大学 | 約80% | 61〜64 |
| 立教大学 | 約78〜82% | 60〜63 |
| 中央大学 | 約78〜82% | 59〜63 |
| 法政大学 | 約75〜80% | 57〜61 |
つまり、共通テストで8割前後を安定して取れる基礎力+応用力が必要。
「高3になってから頑張る」では間に合わないレベルです。
高1・高2の冬から積み上げていけば、まだ十分に狙えます。
MARCHを狙うおすすめ勉強法
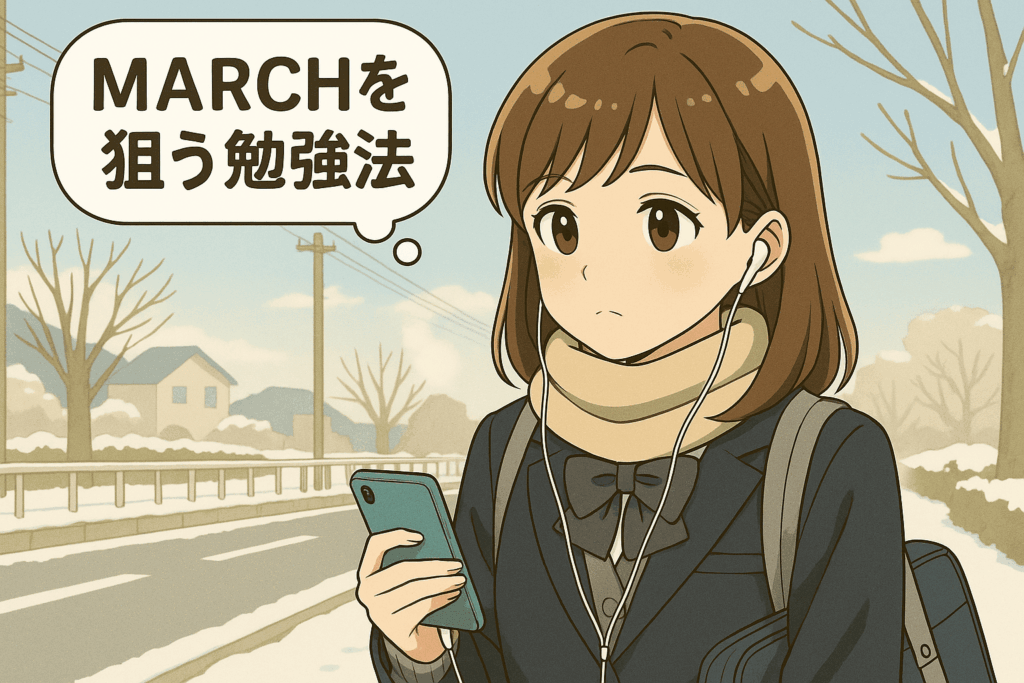
富士高校をはじめ、富士市内の進学校ではこの冬から内容が一気に難化します。
- 数学ⅡBでは「数列」「ベクトル」など抽象的な内容へ
- 英語では「構文」「長文」中心に、単語量・精読力が問われる
さらに、11月の進研模試や学年末テストで“伸び悩み”を感じやすい季節でもあります。
でも、ここでやめずに「今から積み上げ直す」ことができる人が、春には一気に伸びます。
英語:文構造の理解+論理的読解が命
MARCHの英語は、語彙・文法はもちろん、文構造をスパッと見抜ける英文解釈力・筆者の主張を的確に追える論理的読解のすべてが必要。
まずは「語彙」と「英文法」から徹底的に固めましょう。
ステップ1:単語帳は1冊を完璧に
・『ターゲット1900』『システム英単語』など定番でOK
・“覚える”より“何度も見返す”を意識
ステップ2:文法を「使える形」で復習
・問題集を繰り返すより、「なぜそうなるか」を説明できるレベルに
・『Next Stage』『Vintage』などを週ごとに1章進める
ステップ3:長文は「1日1題」習慣に
・最初は共通テストレベルの短文からでOK
・量よりも、1文ずつ意味を追って正確に読む練習を
👉 MARCH英語は“スピード×正確さ”が必要。基礎のミスをなくすことが、得点アップの近道です。
数学:定期テスト+模試のバランスがカギ
MARCHの数学は、基礎〜標準問題をどれだけ確実に取れるかが合否を左右します。
難問に時間をかけるより、「解けるはずの問題を取りこぼさない」姿勢が最重要です。
高1のうちにやるべきこと:ⅠAの基礎を完璧に
共通テスト・MARCHレベルの計算問題を“自動化”することが狙いです。
【具体的にやること】
・計算・関数を徹底復習
数と式、2次関数、集合と命題、三角比などをすぐに手が動くレベルに仕上げる。
定期テストや模試で「見たことがある問題」は全問正解を目指す。
・チャート式は“例題だけ”完璧に
青チャートやFocus Goldなどは、例題だけを繰り返すのが効率的。
応用問題よりも「典型パターンを瞬時に処理できる力」を重視する。
・時間を計って問題を解く練習
模試は時間との戦い。10分1題ペースを意識し、途中計算を丁寧に残す癖をつける。
👉 高1の冬までに「基本問題で失点しない」状態を作ること。
これが高2で一気に伸びる生徒の共通点です。
高2のうちにやるべきこと:ⅡBの得点源を固める
ⅡBは難しく見えますが、実は出題傾向が安定しており、得点しやすい単元です。
【数列(漸化式・和の公式)】
・「一般項を出す」「和の公式を使う」などの典型パターンを完璧にする。
・階差数列・等比数列などの応用では、「変形の型」を覚えると得点が安定する。
・青チャートでは【重要例題★★★】を中心に学習する。
【ベクトル(内積・座標表現)】
・図を描く習慣をつけ、問題文を読んで“図が浮かぶ”状態まで反復練習する。
・計算で詰まる場合は、座標設定の基礎(始点を原点に置くなど)を再確認。
・MARCHの入試では、ベクトルの証明・面積比・垂線関係などが頻出。
【定期テスト+模試の使い分け】
・定期テスト:授業内容を理解できているかの確認の場。
・模試:時間配分・初見問題への対応力を磨く練習の場。
👉 模試後は「どの単元で時間を使いすぎたか」「どの分野で計算ミスが出たか」を記録しておくと、弱点が明確になります。
国語・社会:差がつくのは「基礎語彙」と「論理整理力」
文系のMARCH入試では、英語と国語で合否が決まると言っても過言ではありません。
特に国語・社会は、“暗記+構造理解”の両立がカギです。
現代文:「論理的に読む」力を鍛える
・読む前の準備:「接続語」「指示語」「段落構成」に注目して読む。
・読む最中の意識:「筆者の主張」「対比構造」「例の使われ方」を意識する。
・読む後の確認:「設問がどこを根拠にしているか」を明確にする。
💡おすすめ練習:
河合塾『現代文キーワード読解』で用語を覚える+『現代文のアクセス』を使い、
“論理的に読む”練習をする。
古文:「単語+文法」暗記の早期完成が最優先
・遅くとも高2冬までに『古文単語315』レベルの単語と古典文法を暗記完了。
・助動詞・敬語・接続助詞などをまとめノートに整理し、品詞分解の訓練を行う。
・読解問題は「文法的に読める文」を増やすことを意識する。
💡ポイント:
MARCHレベルでは“単語+助動詞”が読解の8割を決める。
文学史や和歌の背景は後回しでも問題ありません。
社会(日本史・世界史):2周目で“理解を深める”
・1周目(高2前半):通史をスピード重視で一気に通す。
使用教材は教科書や『実況中継シリーズ』などでOK。
・2周目(高2後半〜冬):用語の因果関係・背景を整理する。
「なぜ起こったか」「何と関係するか」を意識しながら学ぶ。
💡勉強サイクル例:
- 平日:30分で1テーマを進める。
- 休日:復習+一問一答で定着を確認。
- 週1回:通史のつながりをノートでまとめ直す。
👉 暗記量は多いですが、“理解と関連づけ”を意識すれば忘れにくくなり、定着が早まります。
MARCH入試で差をつける3つのポイント
設問分析を必ず行う。
→ どの設問形式で間違えるかを把握することで、得点が安定する。
用語・語彙を「理解して使える」形にする。
→ ただ覚えるのではなく、例文・文脈で確認する。
復習間隔を決めて繰り返す。
→ 1週間・1か月後に見直すスケジュールを組むことで定着度が段違いに。
模試の活用法:伸び悩みは「原因分析」で変わる
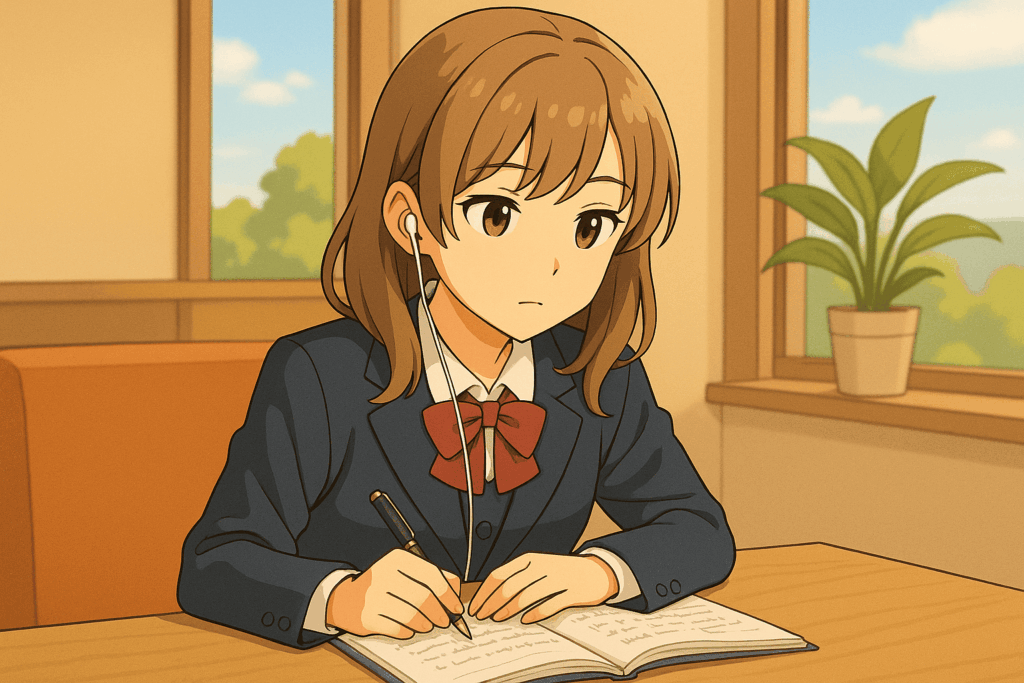
進研模試や駿台模試など、結果に一喜一憂するのではなく、分析を学習計画に反映しましょう。
・正答率50%以上の問題を落としていないか
・ケアレスミスと知識不足の区別がついているか
・時間配分・マークミスの確認
👉 模試は“点数の報告書”ではなく、“成績を上げるための診断書”です。
MARCH合格への現実的スケジュール
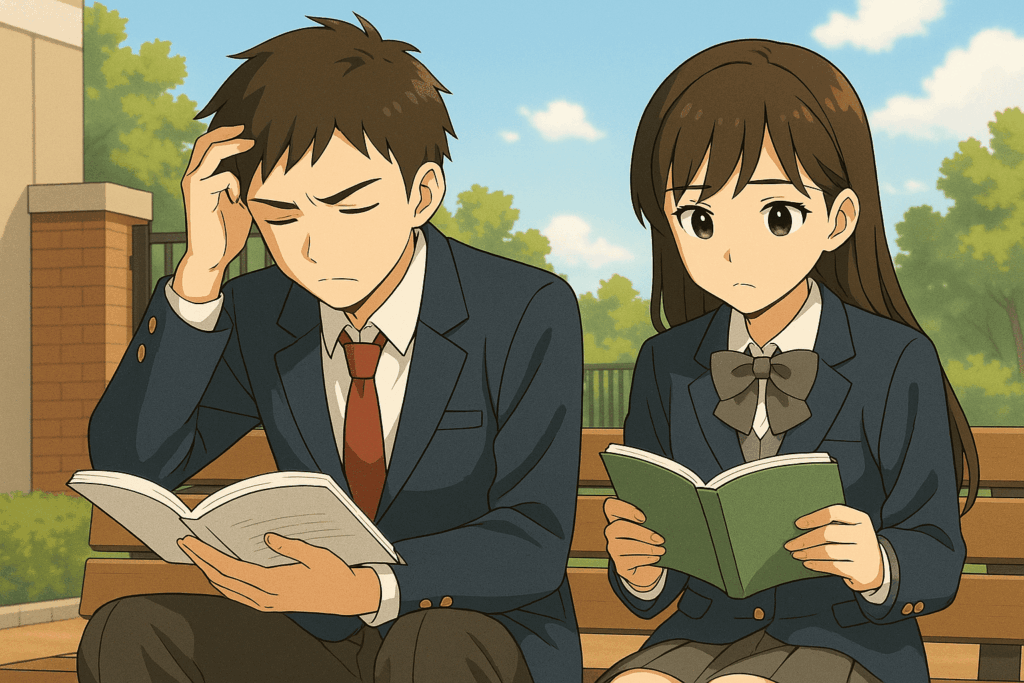
MARCH合格への現実的スケジュール(英語・数学中心)
| 学年・時期 | 英語でやること | 数学でやること | 模試での到達ライン(偏差値) |
|---|---|---|---|
| 高1冬 | ・英単語帳1冊を通しで暗記(ターゲット1900など) ・文法書(Next Stage等)を1週間1章ペースで進める ・短い英文を音読して文構造を意識する | ・ⅠAの2次関数・三角比・確率を反復 ・定期テストの復習で「手が止まる箇所」をリスト化 ・青チャートの例題を1日3問解く | 偏差値58以上 |
| 高2春〜夏 | ・英文法の総復習を完了させ、英文解釈の勉強へ ・共通テストレベルの長文に慣れる(共テ過去問または『やっておきたい英語長文300』) ・語彙2,000語レベルを完成 | ・ⅡBの主要単元(数列・三角関数・指数対数関数)を完了 ・模試・定期テストでのミスを分野別に整理 | 偏差値60 |
| 高2秋〜冬 | ・共通テスト模試で時間配分を意識した演習 ・MARCH過去問レベルの長文に挑戦(1週間に2〜3題) ・文構造を正確にとる練習を継続 | ・ⅡBの復習+応用問題に取り組む ・図形・数列・ベクトルの融合問題を解く ・模試後の分析ノートで弱点を明確化 | 偏差値62〜63 |
| 高3春〜夏 | ・志望校過去問を分析し、頻出テーマを整理 ・英作文・要約練習を週1回取り入れる ・共テ型+MARCH型のハイブリッド演習 | ・ⅠAⅡB総復習+MARCH過去問演習開始 ・典型パターンを短時間で処理する練習 ・記述型問題にも慣れる | 偏差値63〜65 |
スケジュールの使い方
・目標は「高3夏までに英語65・数学60前後」。
・スタートが遅れた人も、高2冬の時点で、偏差値55~60に到達していれば、MARCHレベルに十分間に合います。
・模試結果は「平均点との距離」ではなく、「どの単元で得点できていないか」を見ること。
ワンポイントアドバイス
- 英語は「語彙・文法→構文→読解」の順で積み上げること。逆順は効率が悪い。
- 数学は「ⅠA・ⅡBの例題完全習得」までが基礎。Ⅲは出題が限られるため、時間配分は慎重に。
- 模試を“テスト”ではなく“練習試合”と考え、毎回「課題を1つ減らす」意識で取り組む。
富士市の高校生へ:できることから少しずつ始めよう
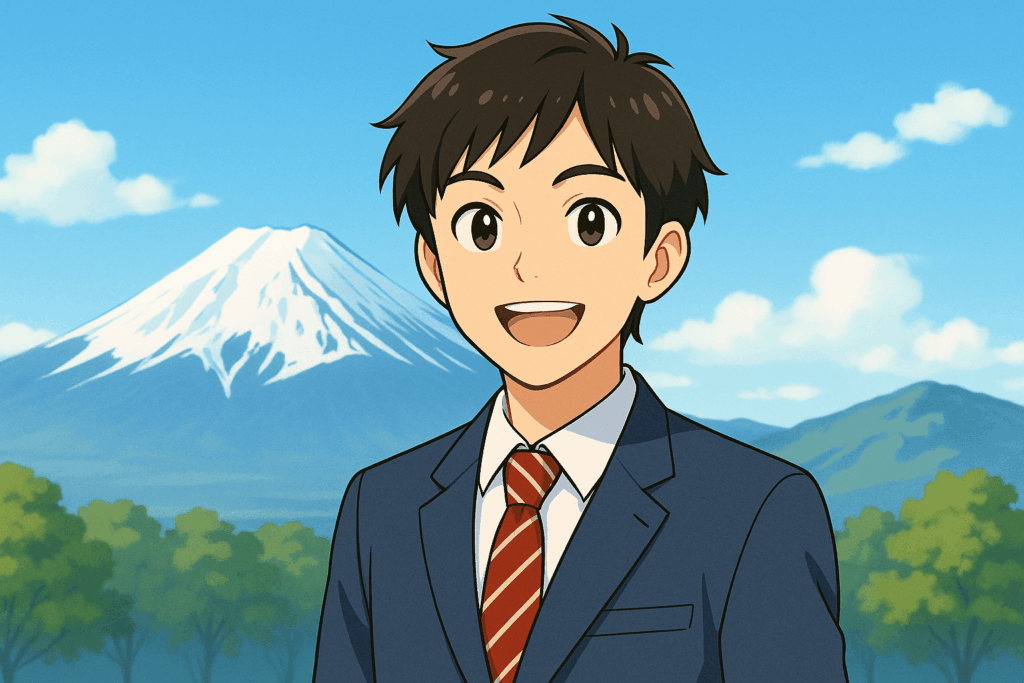
MARCHを目指す勉強は、特別なことをする必要はありません。
ただ、基礎を早く固めて、勉強のリズムを止めないことが大切です。
英単語を少しずつ覚える。
模試で間違えた問題をその日のうちに見直す。
このような小さな積み重ねが、春以降の力になります。
もし今、何から始めたらいいか分からないなら、
「1日30分、英語か数学の復習を続ける」ことからでも十分です。
焦らず、自分のペースで。
高1・高2の冬は、その一歩を踏み出すのにちょうどいい時期です。
地元からでも、全国のライバルに勝てる学び方があります。
投稿者
荷川取
富士校舎の校舎長荷川取です!
▲▲クリックして荷川取のブログ一覧(85ブログ公開中)を見る