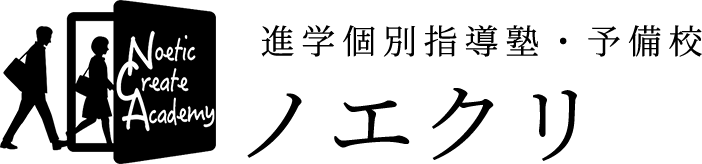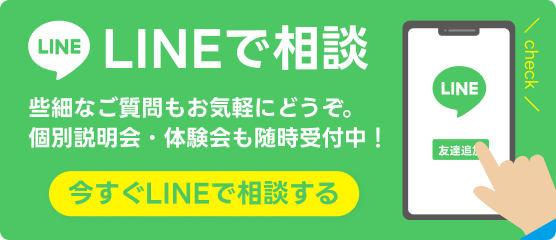分からない問題が出た時の心構えと対処法
2025.11.4 小松校 有松校 松任校
清水
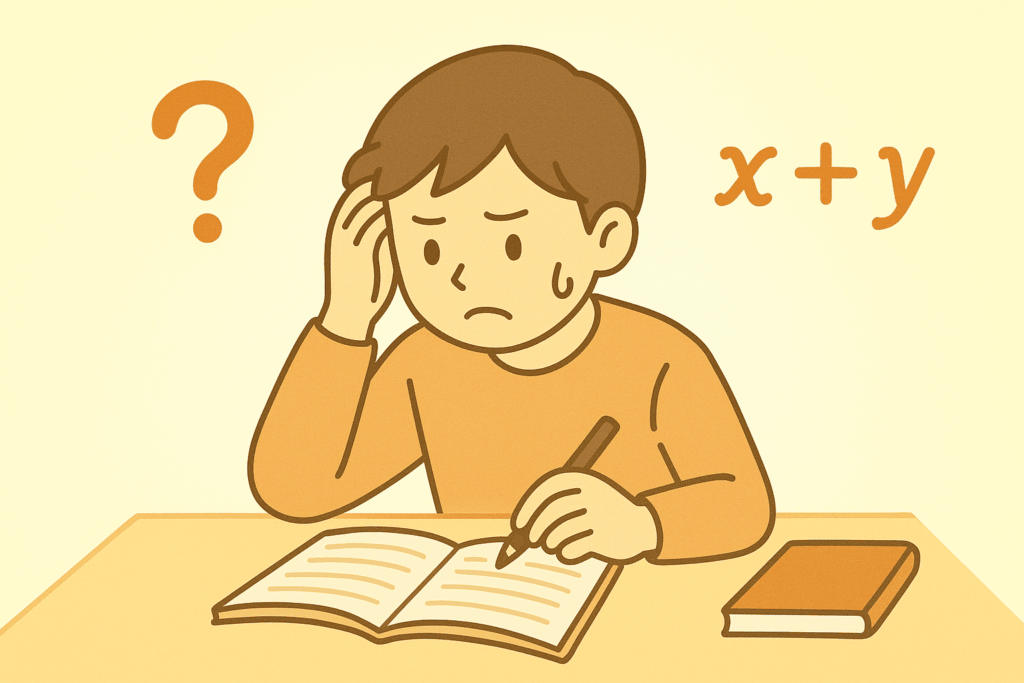
目次
テスト本番で分からない問題に出会った時の心構え
①:分からない問題は、分からないで大丈夫
テスト中に分からない問題に遭遇すると、頭が真っ白になってパニックになることがあります。しかし、ここで焦ってしまうと時間を無駄にしてしまいます。まず深呼吸をして、「この問題は後で戻ってくる」と自分に言い聞かせましょう。
完璧主義になる必要はありません。
全ての問題を解けなくても、解ける問題で確実に点数を取ることが大切です。
受験に合格するために大切なことは、「満点をとることではなく、合格点をとるということです!」
②:問題パターンを把握しておく
テスト中にパニックになる原因の一つは、問題パターンを把握出来ていないからではないかと考えています。どういうことかといいますと、例えば、数列の問題で、どんな問題が出るかを、分かっていないということです。漸化式の問題や群数列の問題が来れば解けているのですが、少し形が変わると解けないのです。「漸化式の解ける状態」とは、「群数列のパターン」とはと、問題を1対1で考えるのではなく、俯瞰して問題パターンを把握する必要があるということです!
つまり、問題を「解かされている」のではなく、「解いている」という状態に移行することが大切です!
テスト本番で分からない問題が出た時の対処法
時間配分を最優先に考える
テストが始まったら、まず全体をざっと見渡して、どの問題にどれくらい時間をかけるか計画を立てましょう。
例えば100分の数学のテストで大問4がつあったとします。
最初の10分~15分を使って、各大問の問題概要の把握と解法を簡単に考えます。そして、解く順番とどの設問までを解くかの基準を考えます。今回は例ですので、解く順番は1から順とします。
大問1:15分で完答/解法まで全て浮かんから落ち着いて最後まで解き切る
大問2:25分で完答/もう少し手を動かして考えたら解けそう
大問3:20分で最後の問題以外/最後はたぶん解けないだろう
大問4:10分で最初の(1)は解ききる/この大問を考えるぐらいなら他の問題の見直しに時間を使おう
残った時間で見直しに使おう
もちろん、実際に手を動かしてみると、多少変わる部分もあると思いますが、どの大問で点数を確実に取り、部分点を稼ぎにいくというのを最初に決めておくことで、時間の使い方や時間をかけるべき大問が分かり、落ち着いて解いていくことが出来ます!
試験本番では、自分の持っている実力を出し切り、点数を取ることが大切です!そのためには、得点の最大化がとても大切です!分からない問題は最後の最後に考えるで大丈夫です!
問題の型を意識する
時間配分について、話をしましたが、その中でも、解く瞬間が訪れるのも事実です。
その時に、この問題どうやって解こうと考えると思います。もちろん手を動かして解法や方針を立てることもありますが、大切なことは、「考える思考」を常に同じにするということです!
ベクトルの問題を解く時に、解法をいくつ持っていますか?
そして、その解法という引き出しの使い方を決めていますか?
普段何となくで決めていると思いますが、この引き出しの使い方を、常に同じにしておくことで、分からない問題のアプローチの仕方を一つ一つ確認しながら、解き進めていくことが出来ます!
数学を例に説明しましたが、物理化学はもちろん英語や国語の文系科目にも同じことが出来ます!
焦れば焦るほど、解ける問題も解けなくなるので、「考える思考」を同じにすることはとても大切です!
次のブログでは、今回をどのようにしているのかの細かい実践例について、2次試験の問題を使いながら話をしていこうと思います!
投稿者
清水
小松校舎の清水です!
▲▲クリックして清水のブログ一覧(45ブログ公開中)を見る