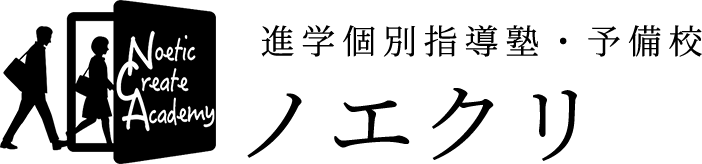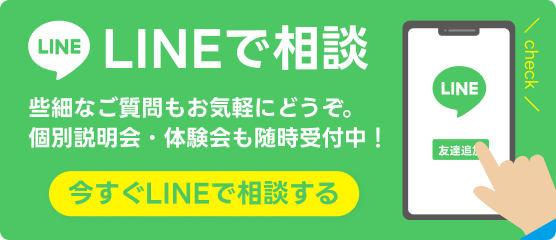【受験勉強が遅れている中3生へ】高校入試に本気で間に合わせる「逆転計画」
2025.10.28 有松校 鶴来校
窪田
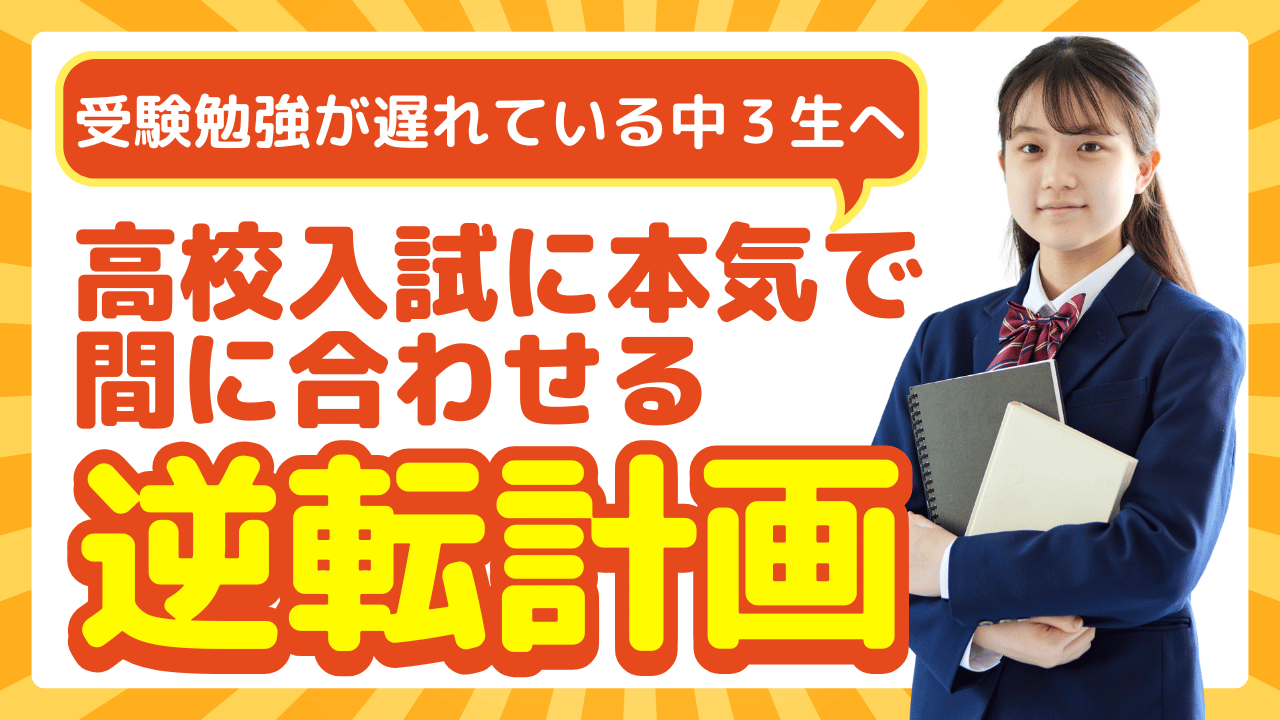
こんにちは、進学個別指導塾ノエクリ 鶴来校・有松校の窪田です。
「うちの子、まだ受験モードじゃないんだけど、どうしたらいいの?」
こんな悩みを抱えている方いらっしゃいませんか?
「模試の結果が返ってきたけど、全然やる気が出ていない」
「夏休みが終わっても、まだ本格的に勉強できていない」
「周りが焦ってきているのに、うちは…」
焦りますよね。
でも、安心してください。今からでも十分に間に合います。
ただし、今からやるべきは「根性論」ではありません。大切なのは、「環境」と「戦略」と「テクニック」です。
石川県の公立高校入試は、全国でもレベルが高く、今の時期に何をするかで、結果が大きく変わります。
ノエクリでは、これまで多くの中3生を「秋からの逆転合格」へ導いてきました。
共通していたのは、正しい順番で、正しい勉強を始めたということです。
この記事では、「まだ本格的に受験勉強を始めていない中3生が、ここから間に合わせるための現実的な方法」をお伝えします。
目次
石川県公立高校入試は「全員同じ問題」で勝負

石川県の公立高校入試は、どの高校を受けても全員同じ問題です。
つまり、泉丘高校を受ける生徒も、明倫高校を受ける生徒も、鶴来高校を受ける生徒も同じテストを解きます。
一見すると「公平」で「シンプル」な仕組みに思えますが、実はここが入試の最大の落とし穴です。なぜなら、誰もが同じ問題を解くということは、例えば、「全問解けなくても合格できる」ということでもあるからです。
「満点を狙う勉強」はムダが多い
入試本番で満点を取る必要はありません。高校ごとに合格ライン(ボーダー)は決まっています。
たとえば、
・泉丘高校 → 370点前後
・二水高校 → 325点前後
・錦丘高校 → 290点前後
・野々市明倫高校 → 200点前後
つまり、泉丘を受ける生徒と明倫高校を受ける生徒が同じ問題を解いても、目標点が違います。
「配点が高い問題」より「確実に取れる問題」から攻める
「配点が高い問題を優先して解こう」と考える人もいますが、それは上位層向けの戦略です。
実際は、配点が高い問題ほど難易度も高く、安定して得点するのが難しいです。
本当に点を伸ばしたいなら、得点しやすい問題から先に仕上げる方が確実です。
【数学】得点しやすいのは「処理が決まっている」問題
たとえば、石川県の公立入試の数学は全国的にも難しい部類ですが、必ず出る基本パターンの中に安定得点ゾーンがあります。
・計算問題(大問1):
毎年数字を変えて同じような計算問題が5題出題されます。(15点)ここでのミス1問は、合否に直結します。
・連立方程式の利用:
式の立て方がパターン化されていて(個数、割合、速さ、食塩水)、練習すれば確実に取れようになります。
・確率問題:
難しそうに見えるのですが、考え方が決まっています。
樹形図・表・サイコロなど「型」を覚えれば安定して得点できます。
一方で、関数の応用・平面図形・空間図形などは、思考力が必要で得点の安定性が低いため、今から間に合わせるなら後回しにするほうが効率的です。
【英語】得点しやすいのは「短時間で確実に取れる」問題
石川県の英語はリスニング(30点)が大きな割合を占めます。
リスニングは配点が高い上に、出題形式が毎年ほぼ同じで、努力が点に直結する分野です。
また、大問2も、短文で文法問題が出題されるため「覚えれば点になる」範囲です。
逆に、長文読解・英作文などは配点は高いけど、短期間で安定させるのは難しいです。
合格点から逆算して、効率よく積み上げる
ノエクリでは、まず模試データと過去問から、志望校の合格点と現在の得点差を分析します。
その上で、
・今からでも得点しやすい単元
・時間をかけてもリターンが大きい範囲
を優先的に学習スケジュールに組み込みます。
「全部やる」ではなく、「合格に必要な部分をピンポイントで取る」ことこそが、残り数ヶ月で結果を出す最短ルートです。
次回のブログでは、実際に高校別に「どの問題をやるべきか」「どの問題は後回しにしていいか」を具体的に紹介します。
「時間がない中で、何を取って、何を切るか」それを正しく見極めることが、合格を決める最も現実的な戦略です。
学校では教えてくれない、入試で点を取るテクニック
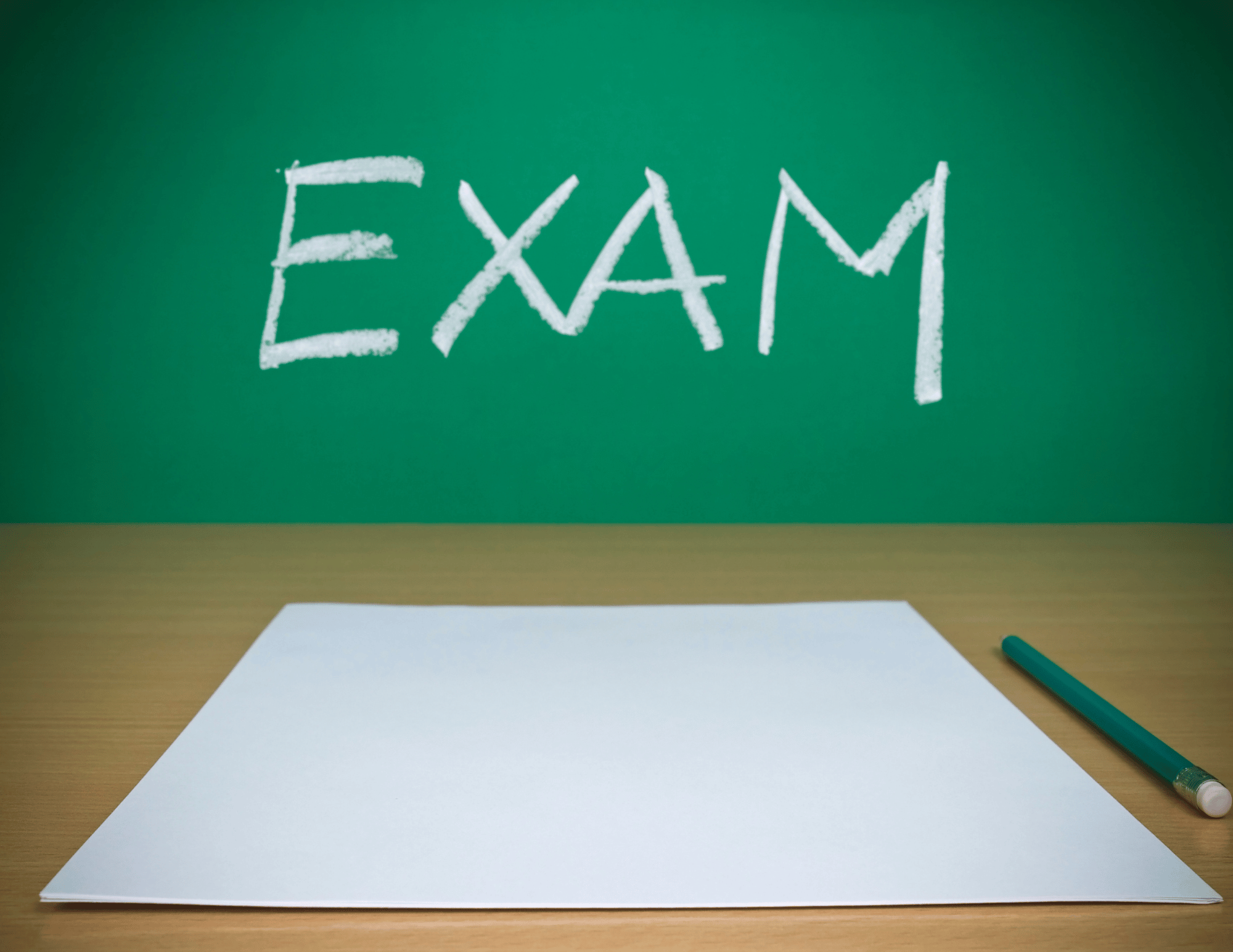
学校の授業は、ほとんど教科書通りです。
でも入試は「それをどう使うか」が問われます。
たとえば、
・二次関数のグラフで面積を求める問題
・平面図形の面積の問題
これらは、学校で習った知識だけではなかなか解けません。時間が足りなくなる生徒が多くいます。
必要なのは、「どう考えれば早く正確にたどり着けるか」という入試専用の裏技です。
ノエクリの授業では、このテクニックを徹底的に叩き込みます。
たとえば、
・関数で「平行」「面積」という言葉が出てきたら→ 等積変形を疑え
・関数で「出会う」「追い越す」は→2直線の交点を求めよ
・記述問題は「原因→理由→結果」の型を1文で書く
・英作文は「主語+動詞+that節」で書いてみる
こういう「得点の近道」を知らないまま時間をかけるのは、遠回りでしかありません。
「環境」が変わらないと、「意識」は変わらない
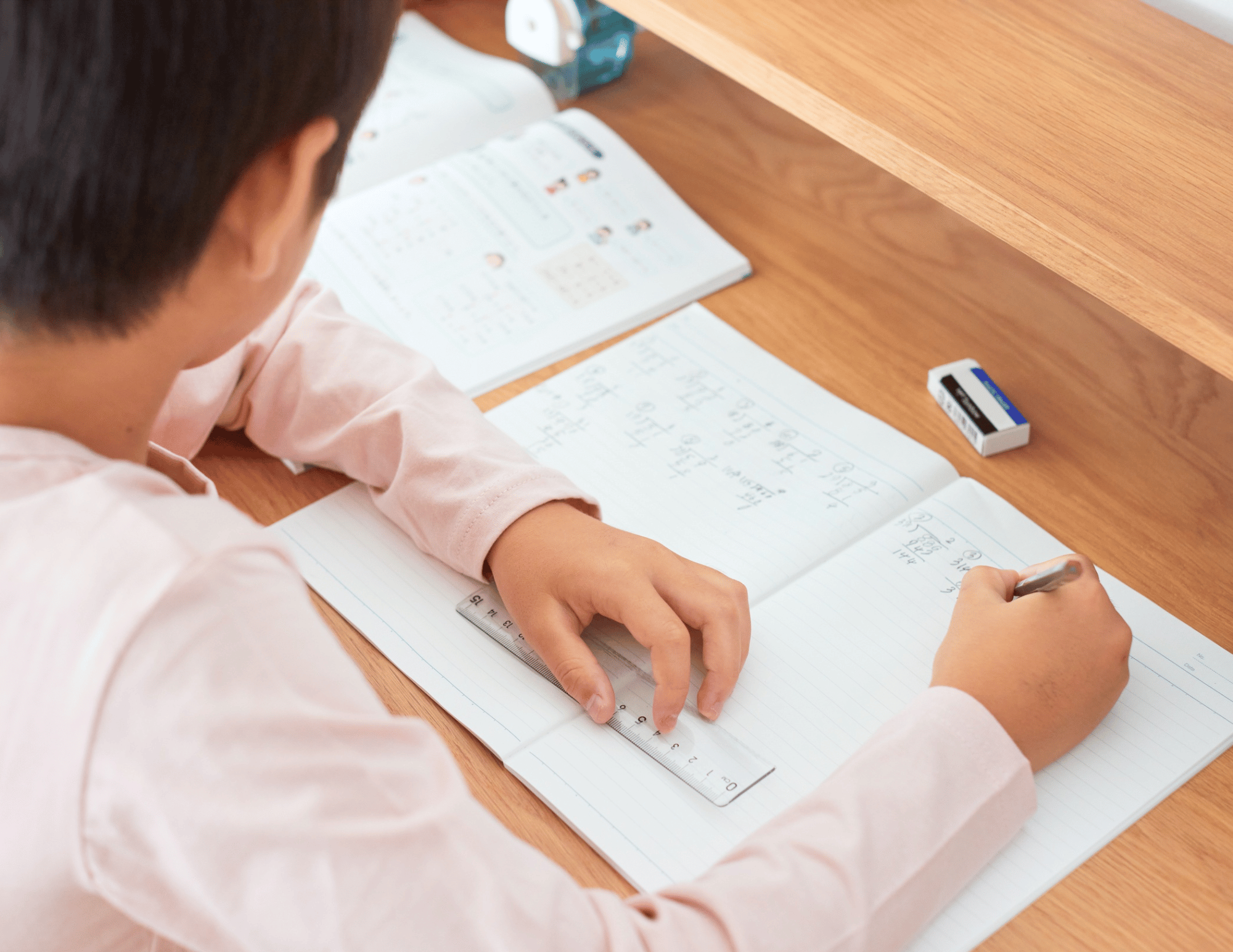
どれだけ「勉強しなさい」と言っても、家ではなかなか集中できない子も少なくありません。
それは意志が弱いからだけではありません。環境が、勉強モードになっていないからです。
家には、スマホ、YouTube、ゲーム、ベッド・・・気が散るものがいくらでもあります。
「5分だけ休憩しよう」が、あっという間に1時間、2時間・・・。
でも、場所を変えるだけで人は変わることができます。
ノエクリには、集中力が続く仕組みがあります。「やる気が出ない子」ほど、環境で変われます。
ノエクリには、最初は「家では全然できない」と言っていた生徒がたくさんいます。でも、通ううちに、ほとんどの生徒が勉強できるようになります。
① 集中できる自習室
一人ひとりの机が区切られているので、周囲の視線を気にせず集中できます。
講師が巡回しているので、サボれない空気があります。
周りの生徒が、集中しているので、自分もやらないといけないという雰囲気になります。
② 質問しやすい講師配置
「分からないところをそのままにしない」ことが、最大の集中サイクルです。
分からないまま放置すると、モチベーションは一気に下がります。
ノエクリでは、
・自習中でも講師にすぐ質問できる
・「次に何をすればいいか」をその場で指示してもらえる
だから、何をやればいいか迷うことはありません。
③ 個別面談での勉強管理
2週ごとの面談で、「やること」「次の模試で狙う点数」「時間の使い方」まで具体化します。
ただ「頑張ろうね」と声をかける場ではありません。次の模試・入試までを見据えた作戦会議です。
・「点数目標」が現実的になる
「次の模試で何点取るか?」を決め、そこから逆算して、何をどの順番でやるかを決めます。
例:「連立方程式の問題が取れれば+10点上がる」
→ 次の2週間は連立方程式の利用の問題を練習しよう。
点数という「数字」で目標を示すので、生徒が納得して動けるようになります。
・「時間の使い方」まで落とし込む
どんなにやる気があっても、「時間の使い方」が間違っていると成果は出ません。
だからノエクリの面談では、
「朝30分早く起きて30分は英単語練習」
「土曜の午前は、模試復習をしよう」
などといった生活リズムごとの勉強時間の設計まで一緒に考えます。
④ モチベーションが上がる個別授業
ノエクリの授業は、「ただ解説して終わり」ではありません。
授業のたびに、「やる気が上がる仕掛け」を入れています。
・一人ひとりの「課題」に合わせた作戦授業
「何を」「どの順番で」「どのレベルまで」やるかを、講師が一緒に設計。
「今の自分に合った勉強」が分かるから、ムダがなく、自信をもって進めます。
分からないところを放置せず、「できた!」を積み重ねることで、モチベーションが上がります。
・「できた」を一緒に喜ぶ講師
生徒が1問できるたびに、講師がしっかり反応します。
「ここ成長してるね」「その考え方、めっちゃいいよ」などと声をかけます。
一人で黙々とやる勉強ではなく、「伴走してくれる先生がいる」安心感が、継続の原動力になります。
ノエクリの受験カリキュラムは、「全員一律」ではない

ノエクリの授業は、「全員が同じペースで同じ教材をやる」ような授業ではありません。
入試までの残り時間も、苦手単元も、目標とする高校も、生徒一人ひとりまったく違います。
だからこそ、カリキュラムも全員違います。
一人ひとりを「今の位置」から分析する
まず、
・今どこで止まっているか
・どの単元で点を落としているか
・志望校まであと何点必要か
を、模試や定期テストの解答などから細かく分析します。
「あと何点」から逆算した戦略
「とりあえず頑張ろう」ではなく、「合格点との差」から逆算して、やることを決めます。
・模試の結果から「あと◯点足りない」
・「どの単元をやればその点が上がる」
・「それに必要な勉強時間はどれくらいか」
を全部「見える化」して、一人ひとりのスケジュールに落とし込見ます。
だから、同じ努力量でも結果が出るスピードが全く違います。
「もうダメかも」から逆転する生徒たち
実際、ノエクリには毎年、10月、11月に入ってから駆け込んでくる生徒がいます。
「もう間に合わないかもしれない」
「何からやればいいかわからない」
そう言っていた生徒たちが、春には第一志望校に合格しています。
それは、「正しい順番で努力した」結果です。
「高校につながる勉強」こそ、今やるべきこと
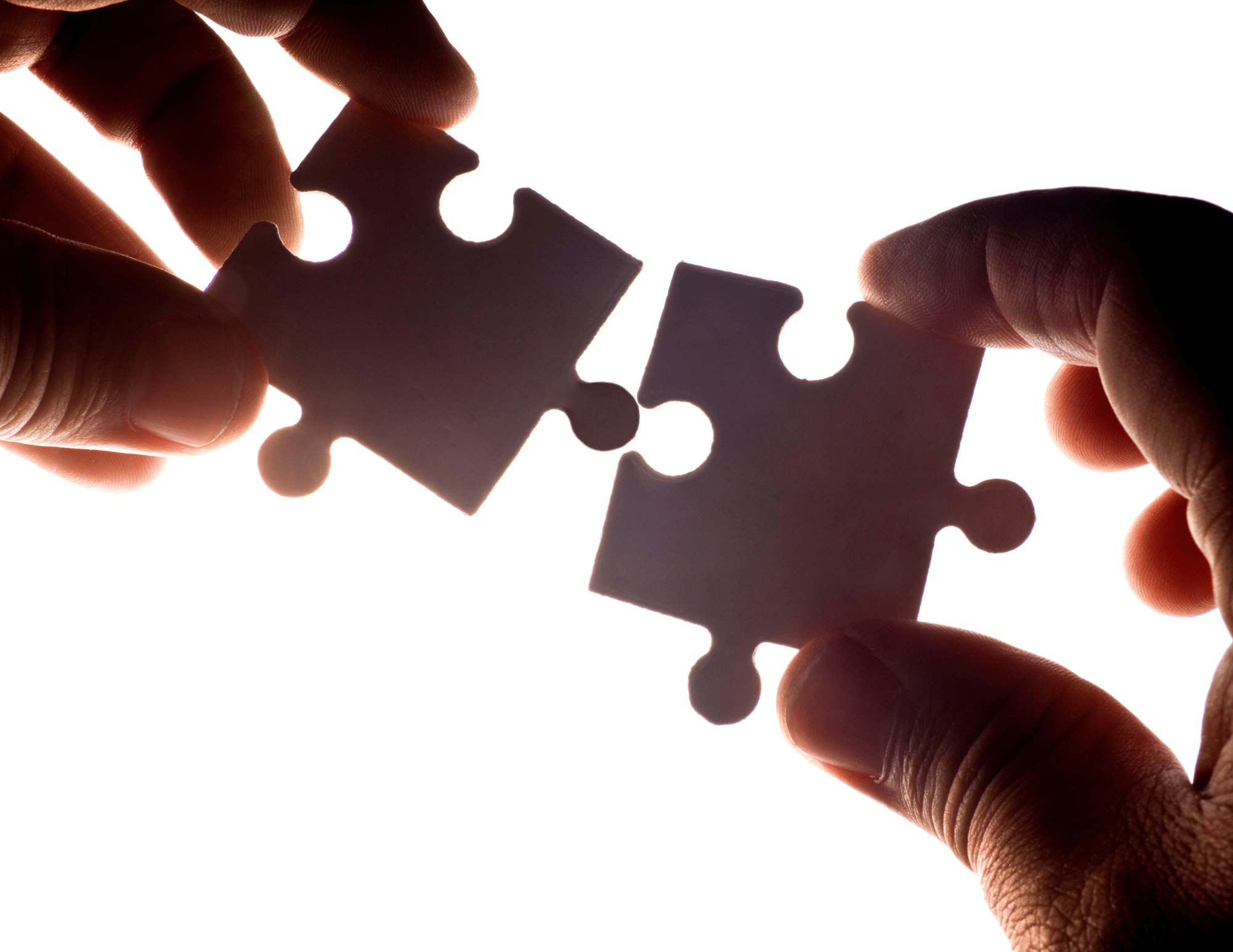
多くの中3が見落としているのが、「受験勉強は高校の勉強へも繋がる」という視点です。
たとえば:
・数学の展開・因数分解・二次関数
→ 高校数学Ⅰ「式と証明」「二次関数」の基礎。
ここは高1の1学期に習う範囲です。ここを曖昧にしたまま高校に行くと、最初のテストでつまずき、高校生活が嫌になる可能性があります。
・英語の文法・単語・文型の型
→ 高校英語の最初は、ほぼ「中学文法の徹底復習」。
中3までに文法の型を正確に理解している生徒ほど、高校に入ってからも英語の授業でつまずきません。
つまり今やっている勉強は、入試のためだけではなく「高校1学期を楽にするための準備」でもあります。
「高校につながる勉強」を今やるメリット
- 入試の得点にも直結する
→ 高校内容の基礎=中3入試問題の核心。
- 高校の授業に余裕が生まれる
→ 入学後に「わからない」をゼロから復習しなくて済みます。
最初のテストで好スタートが切れます。 - 「勉強が続く」生徒になる
→ 入試で燃え尽きず、「できる」状態で高校に入るから、モチベーションが続きます。
「1人では間に合わない」と思う人こそ来てほしい
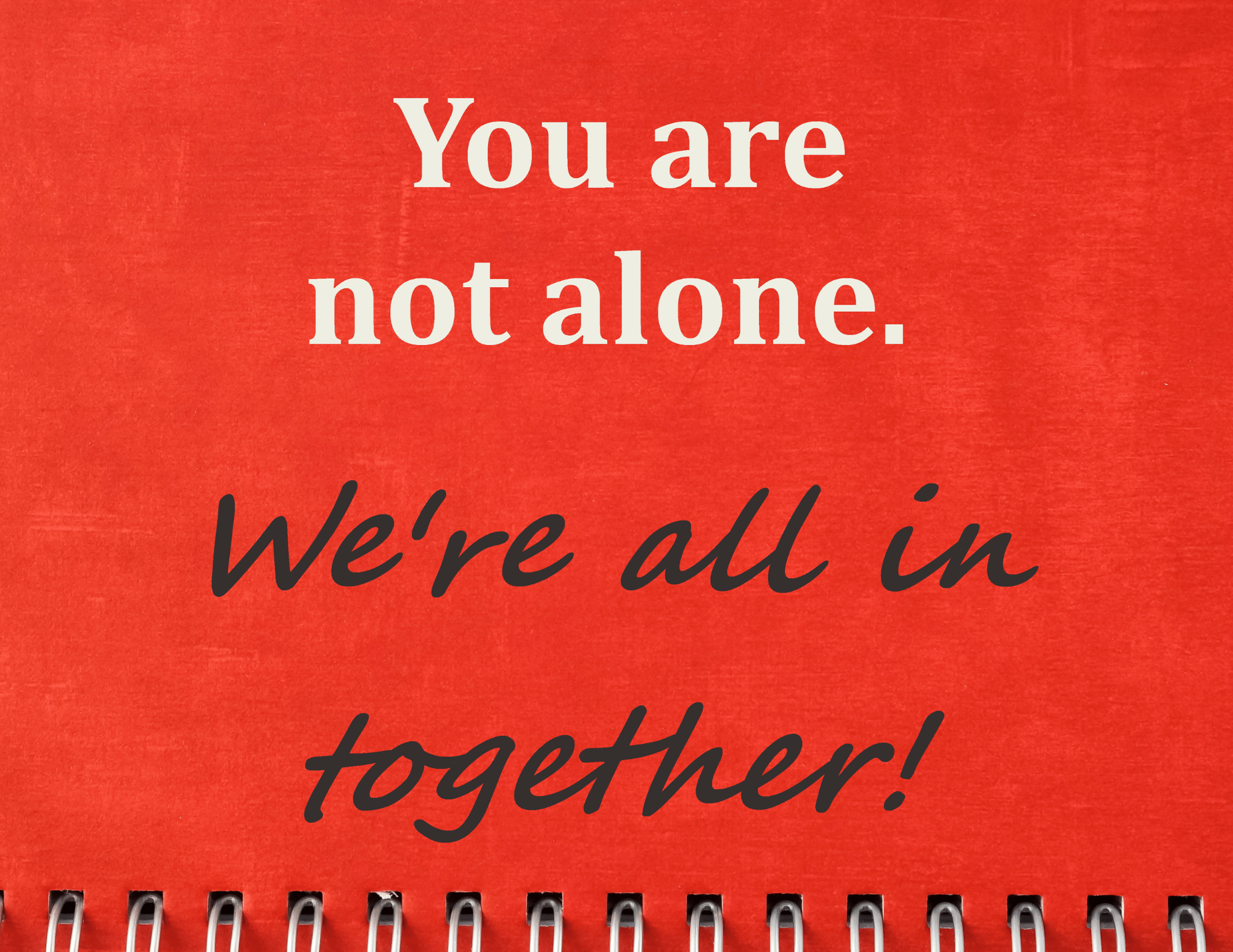
この時期に1人で受験勉強をやり切るのは、難しいです。
・何をどこまで復習すればいいかわからない
・勉強しても成果が見えない
・やっているのに模試で点が上がらない
それは「努力不足」ではなく、戦略不足です。
ノエクリでは、模試結果・過去問分析・生徒の進捗をもとに、一人ひとりの「次の一手」を決めています。
「あと何点」「どこで取る」まで明確にします。やることが見えるから、やる気が出ます。これが、伸びる生徒の共通点です。
📞 無料体験・学習相談受付中
「このままじゃ間に合わないかも」「でも、合格したい」
その気持ちがあるなら、十分間に合います。
ノエクリが「環境・戦略・テクニック」で、受験本番までを最短距離で走り切るサポートをします!
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者
窪田
有松校・鶴来校の窪田です!
▲▲クリックして窪田のブログ一覧(156ブログ公開中)を見る