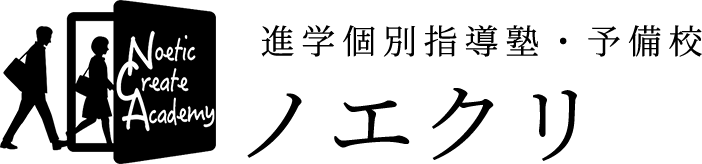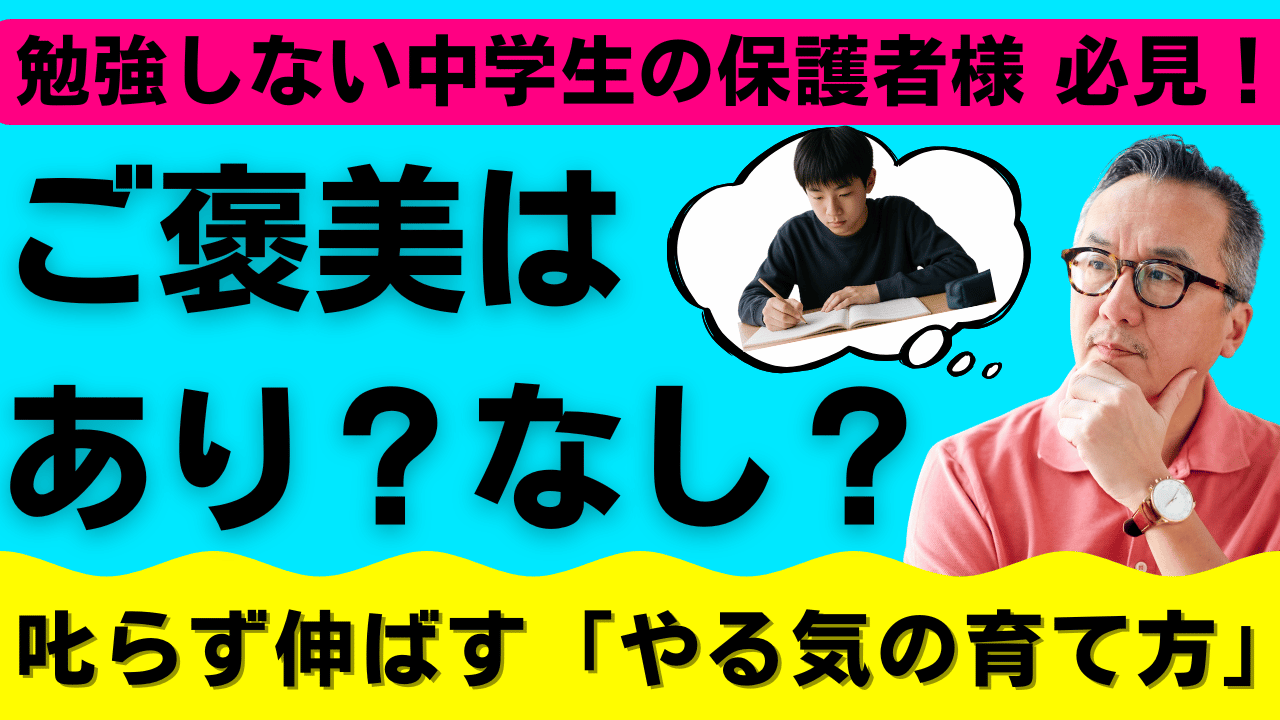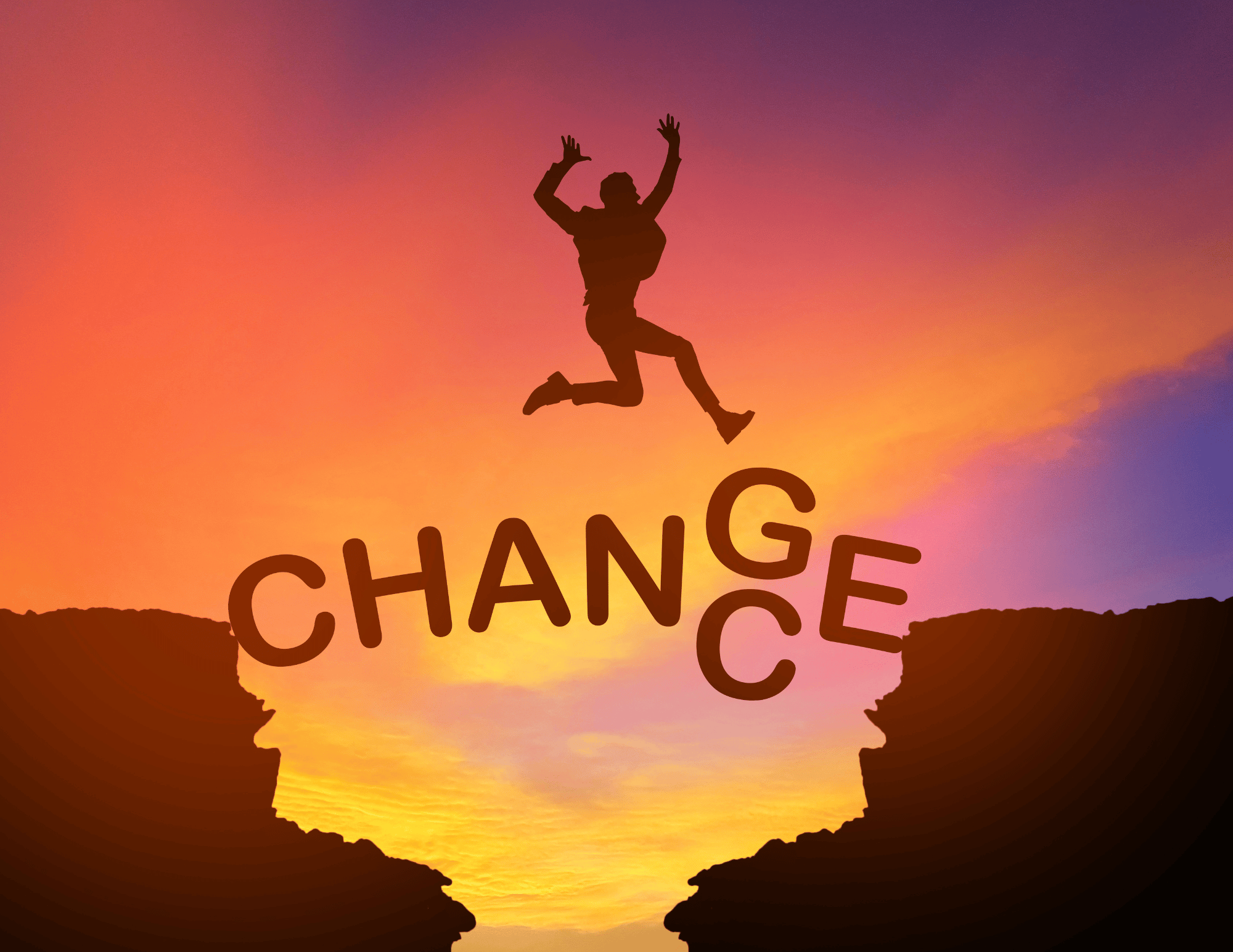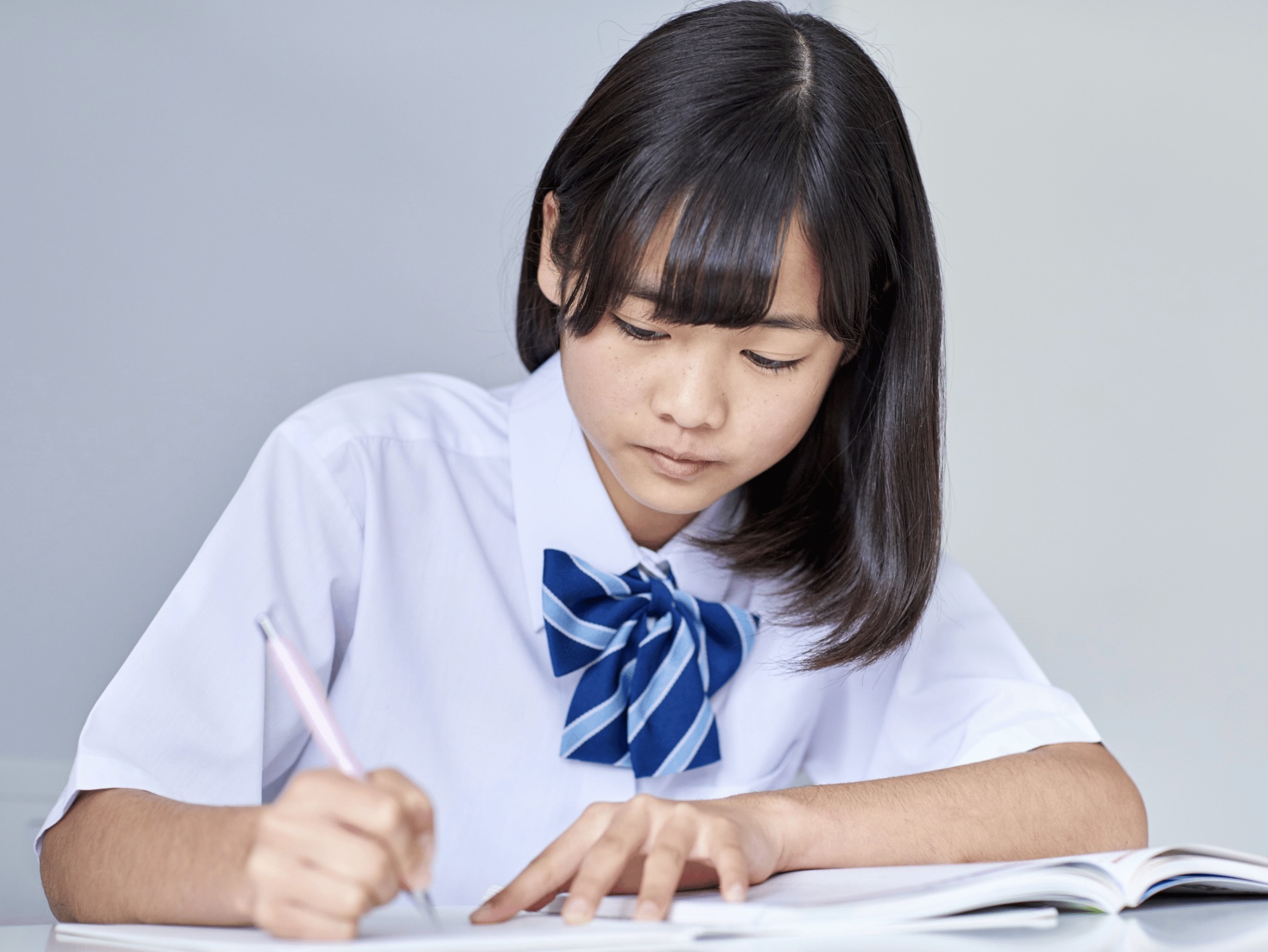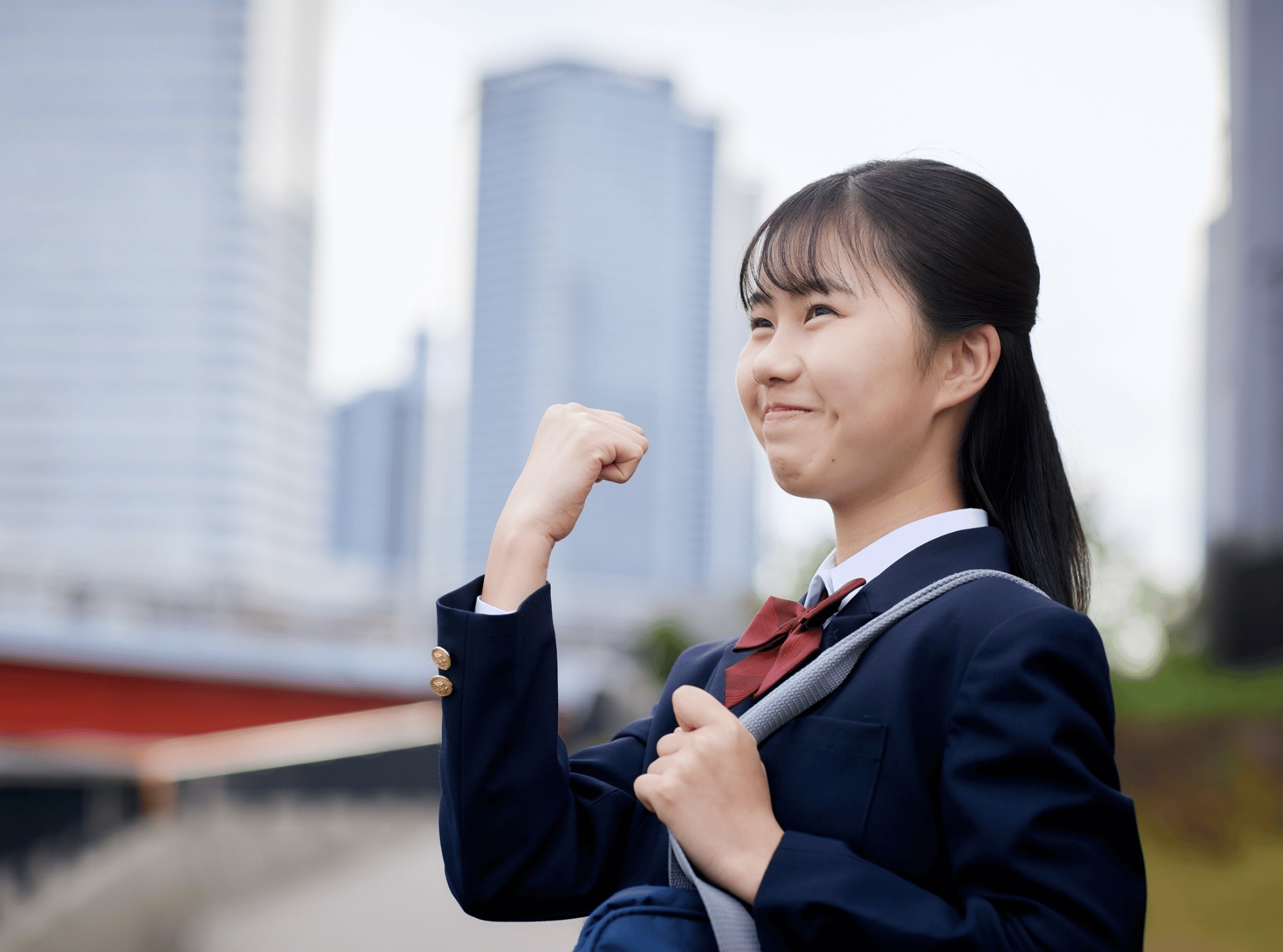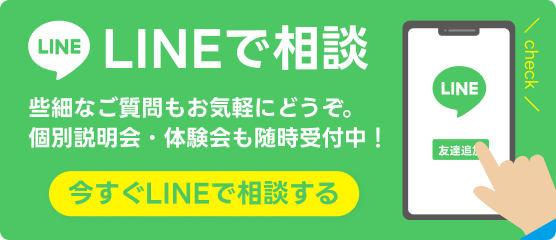私自身も、「ご褒美」が原点だった

正直に言うと、私は昔、勉強が大嫌いでした。
小学生のころは外で遊ぶ方がずっと楽しくて、宿題もギリギリ(出さない日もあったかもしれません)、テストも「まあいいか」で済ませるタイプでした。
私には3歳年上の兄と同じ歳(双子)の姉がいますが、兄がテストでいい点を取ってそのご褒美にCDコンポを買ってもらっていたのがきっかけで、私も何か買ってほしいとお願いしました。
当時、CDコンポが流行っていて、兄のを見て「いいな」と思い、私もそれを買ってもらうために初めて進んで勉強しました。
けれど、それが私にとっての「最初のやる気の火種」でした。
最初は「欲しいもののために」机に向かっていたのに、気づけば、「褒められた」「できた」が嬉しくて、少しずつ自分から勉強するようになりました。
今振り返ると、環境に恵まれていたのもありますが、一番大きかったのは「頑張った自分を認めてもらえた経験」です。
「やった自分をきちんと見てくれた」
それが原動力になったのだと思います。
ご褒美が生み出す「やる気の連鎖」
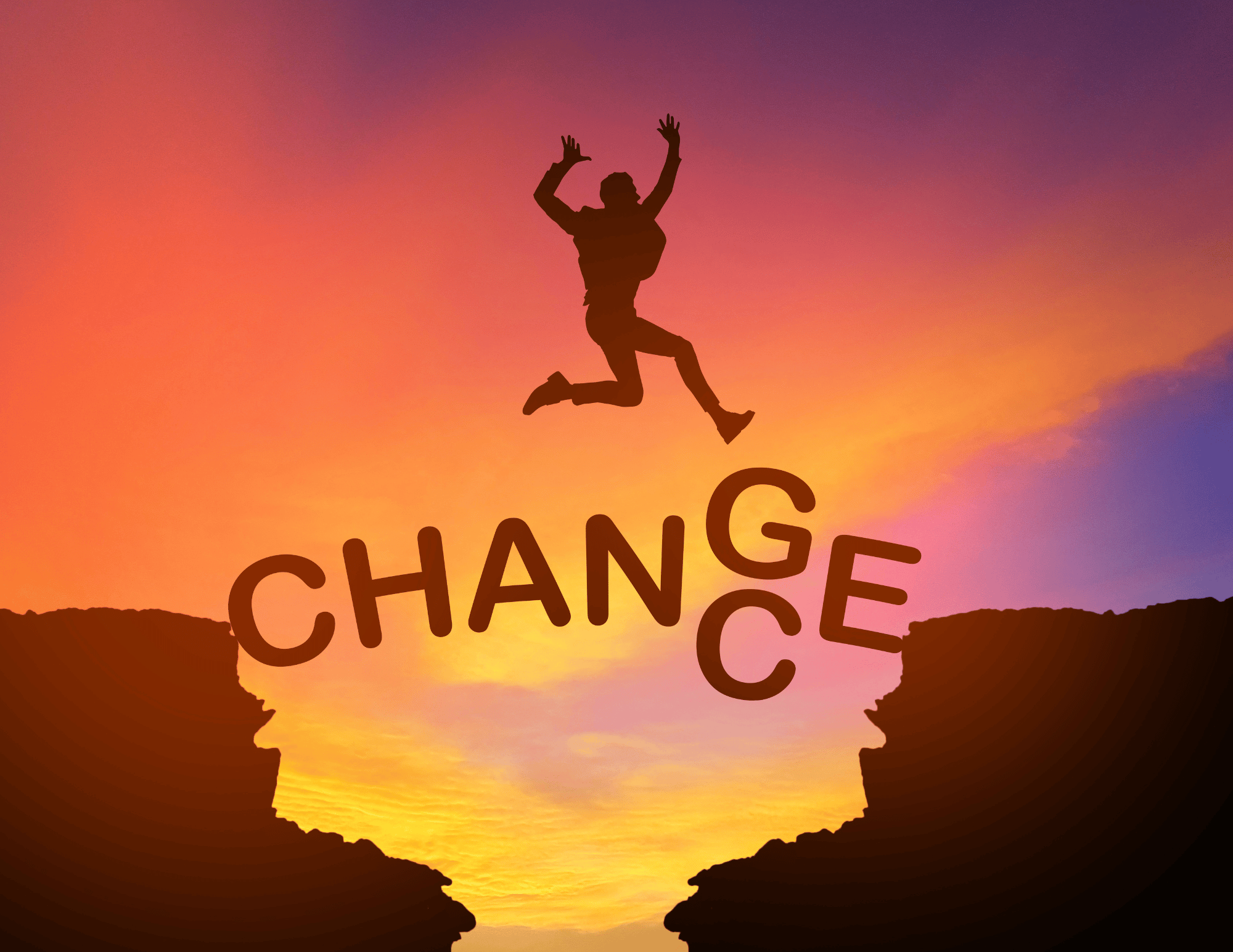
ご褒美の本当の力は、「モノ」ではありません。
それによって生まれる心理的な連鎖です。
1️⃣ ご褒美のために頑張る
2️⃣ 成績が上がって、褒められる
3️⃣ 「自分でもやればできる」と感じる
4️⃣ 親子の会話が前向きになる
5️⃣ 自己肯定感が高まる
6️⃣ 「次は自分のために頑張りたい」と思える
ご褒美は、「他人にやらされる勉強」を「自分で頑張る勉強」に変えていくきっかけになります。
多くの生徒を見てきましたが、この流れこそが自然で、そして現実的に子どもが成長していく姿だと感じています。
ノエクリで見てきた「ご褒美の力」
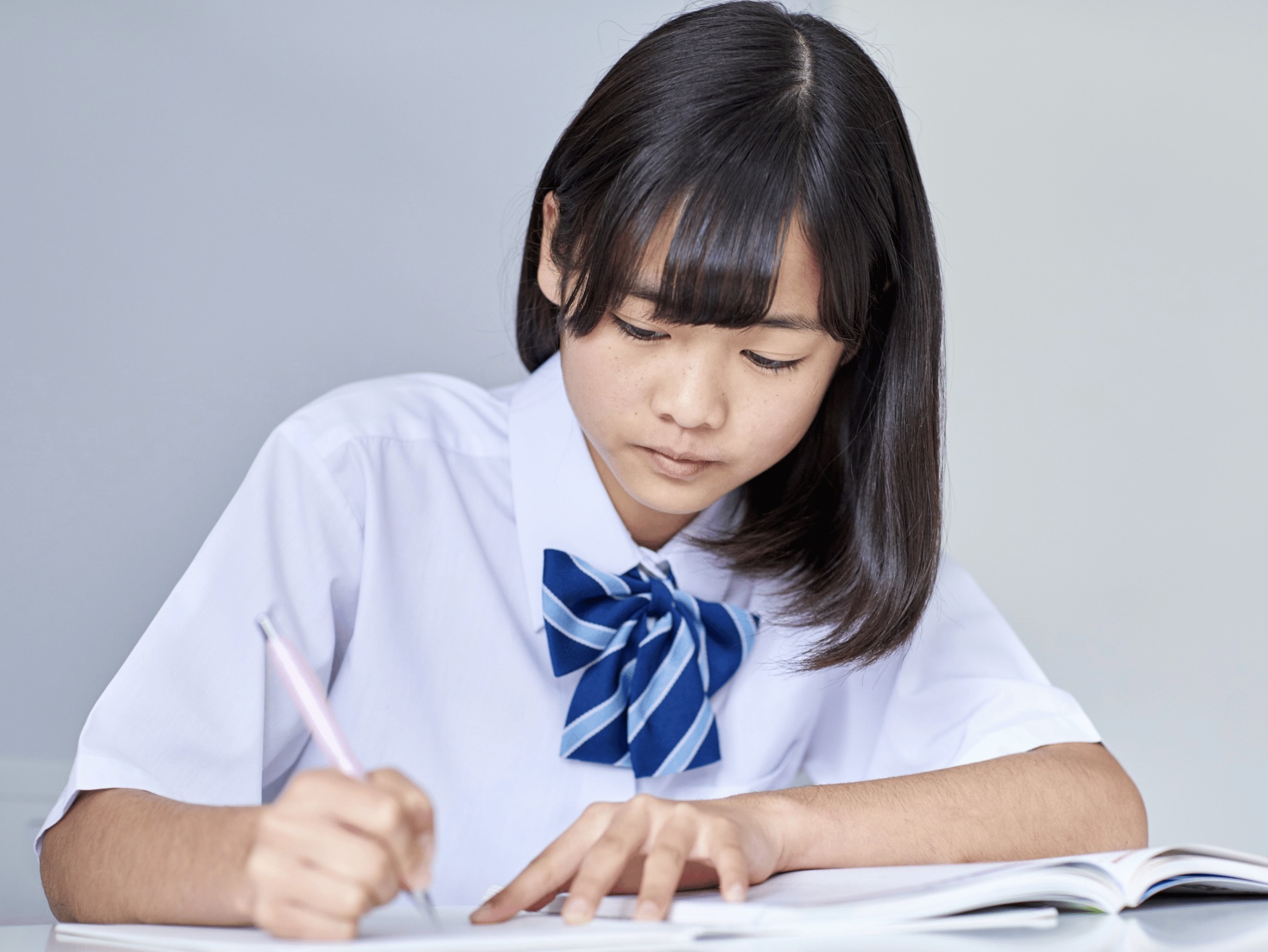
ノエクリに通っている生徒の中にも、最初は「勉強嫌い」な子がいます。
「怒られるのが嫌で来ただけ。」
「お母さんに言われたから。」
そんな子どもたちが、少しずつ表情を変えていくきっかけは、「叱ること」ではなく、「見てあげること」です。
「昨日よりノートがきれいだったね。」
「最後まであきらめなかったね。」
「その考え方、いいね。」
そんな声をかけると、
最初は無表情だった子が、その瞬間、目の奥に「火」が灯るのがわかります。
ある中1の男の子がいました。
最初は課題をサボってばかりで、「お母さんに言われたから来た」と口にしていました。
でも、テストの点数が上がったとき、
「この前、テストの点が良かったから、焼肉に連れて行ってもらった」
「お母さんが嬉しそうだった」
と話してくれました。
それ以降だんだんと、その子の勉強への姿勢が変わり、授業中もよく質問をするようになりました。
子どもを変えたのは、怒りでも厳しさでもなく、「認めてもらえた」という経験でした。
「環境の力」は想像以上に大きい

私は双子として育ちました。
常に隣で同じように頑張る存在がいたことが、何よりの刺激でした。
人は、「空気」に影響を受けると思っています。
一人だと続かないことも、仲間がいれば頑張れる。
ノエクリの教室には、その空気があります。
・真剣に問題に向かう姿
・質問をしながら少しずつ成長していく姿
・それを見守り、励ます講師たち
「誰かと一緒に頑張る」環境は、やる気を長続きさせる最大の要素です。
勉強の習慣は、「環境」から生まれる。
私は、それを毎日、目の前で見ています。
ご褒美は、子どもを伸ばす力になる
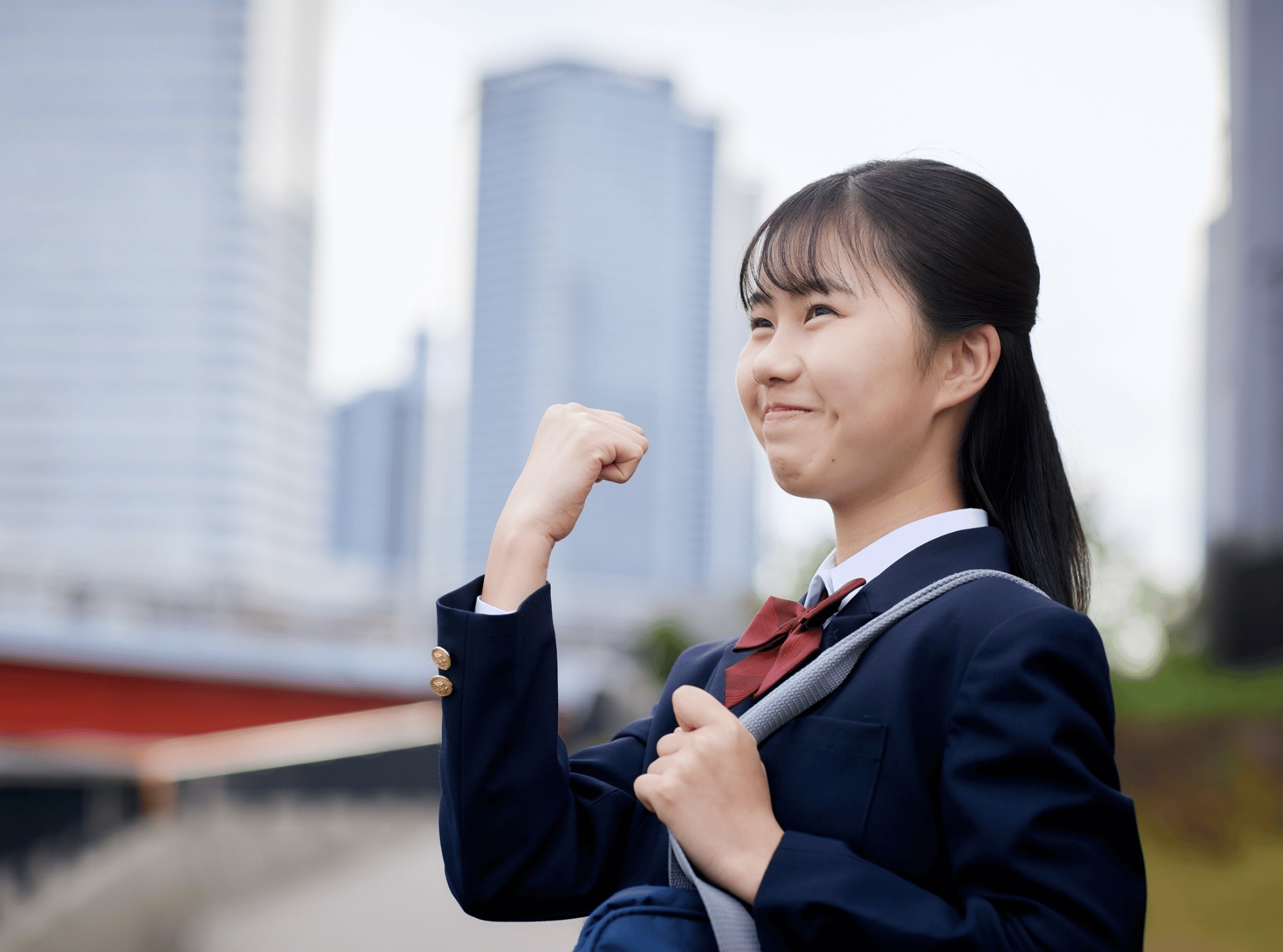
私は、ご褒美を与えることは、決して甘やかしではないと思います。
ご褒美とは、子どもが「また頑張ろう」と思える小さなきっかけになります。
ノエクリでは、
・小さな努力を言葉で認める
・結果より「変化」を褒める
・仲間と励まし合える環境をつくる
これらを大切にしながら、子どもたちが「自分にもできる」という実感を積み重ねていけるよう支えています。
努力が報われる経験を通して、次の挑戦へ踏み出す力を育てていきます。
そして、子どもたちが自分の成長を感じ、「次はもっと頑張りたい」と思える瞬間をつくっています。
その積み重ねが、本当のやる気を育てると信じています。
まとめ|きっかけがあれば、子どもは変われる