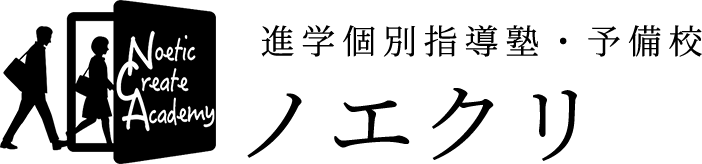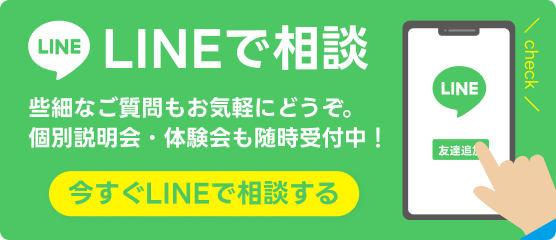【中学3年生】判定に一喜一憂しない!模試を“成績アップの材料”に変える方法【受験生必見!】
2025.9.23 有松校 金沢駅前校
小坂

目次
「模試」とは何なのか?模試結果を成績向上につなげる為に!
みなさんこんにちは!進学個別指導塾ノエクリの小坂です!もうすでに3度目の石川県総合模試を終え、結果を踏まえて皆さん色々思うところがあるかと思います。
そんな中でも、
「毎回模試を受けているのに、なかなか点数が上がらない…」
という悩みを抱える中学3年生はとても多くみられます。
実際に塾でも、
「一生懸命勉強しているのに結果が出ない」
「解いているときはできた気がするのに、点数に結びつかない」
という声をよく聞きます。
しかし、その原因は「勉強不足」ではなく、「努力の方向性」がズレているケースが大半です。
模試の本当の価値は「自分の課題を見つけ、修正すること」にあります。
正しい方法を取り入れるだけで、次の模試から結果が大きく変わる可能性があります。
今回は、模試の成績が伸びない代表的な理由と、その解決策。そして科目ごとの具体的勉強法まで詳しく解説します。
模試成績が伸びない主な原因

① 解き直しをしていない
模試後に成績表を見て「今回はB判定か…」で終わっていませんか?
多くの生徒がやりがちなのは、点数や偏差値を確認しただけで満足し、次にどう活かすかを考えないことです。
しかし模試は、ただ「受ける」ことよりも「解き直す」ことに価値があります。
正答率の低い問題は、多くの受験生にとっても難しいですが、自分が落とした問題は「次も同じパターンで落とす可能性が高い問題」です。
この“自分自身だけの弱点”を解き直しで見つけ出せるかどうかが、成績を伸ばす分岐点になります。
解き直しの際は、解答を丸写しするのではなく「自分の答案を検討し、どの段階で誤ったのか」を確認することが重要です。
そうすることで、知識不足なのか、読み違いなのか、単なるケアレスミスなのかを把握できます。
② 苦手分野を避けてしまっている
「数学の図形は苦手だから後回し」「英語の長文は読む気がしない」――
苦手分野を避けてばかりだと、模試の度に同じ単元で失点を繰り返すことになります。
模試は本番の入試に出そうな内容、範囲を予測して作られています。つまり、模試でやってしまった失点はこのままだと本番でも繰り返す危険性が極めて高いということです。
苦手を放置すると「総合点が伸びない」「志望校判定が上がらない」という結果に直結します。
克服の為には、例え苦しくても自身の弱点を直視し、謙虚にその事実を受け入れることが大切です。
この作業は一人ではとても大変で、また自分に対して甘くなりがちなため、ノエクリでは講師・生徒の学習面談において客観的な視点からこの点を指摘し、生徒と一緒にどのように弱点に取り組むかを相談し、課題設定を行って実行まで確認しております。
時には生徒に対して厳しいことを言うこともまた、生徒に寄り添うことだと私たちは信じております。
③ 時間配分への意識が弱い
模試や入試本番で「最後の問題まで解けなかった」「焦ってケアレスミスを連発した」という経験はありませんか?
その多くは知識不足ではなく、「時間配分の感覚」が身についていないことが原因です。
試験時間は限られているため、すべての問題をじっくり解くことはできません。
重要なのは「得点に結びつく問題を優先する」姿勢です。
時間配分は「大体長文は〇分で解いて・・・」というような曖昧なものではありません。
模試の構成と入試問題の構成は同じなため、例えば国語では、
・漢字は5分、作文は10分、古文は8分で済ます。
・残りの27分のうち、説明文は14分、物語は13分で取り組む。
・説明文を10分程度解いた段階で、14分までに終わらなさそうなら先に次の問題へ進む。
などの、様々なシミュレーションを事前に考えておきましょう。
ノエクリでは、この点に関しても生徒と様々なシミュレーションを行い、本番で慌てない意識作りに取り組んでおります。
成績アップのための具体策
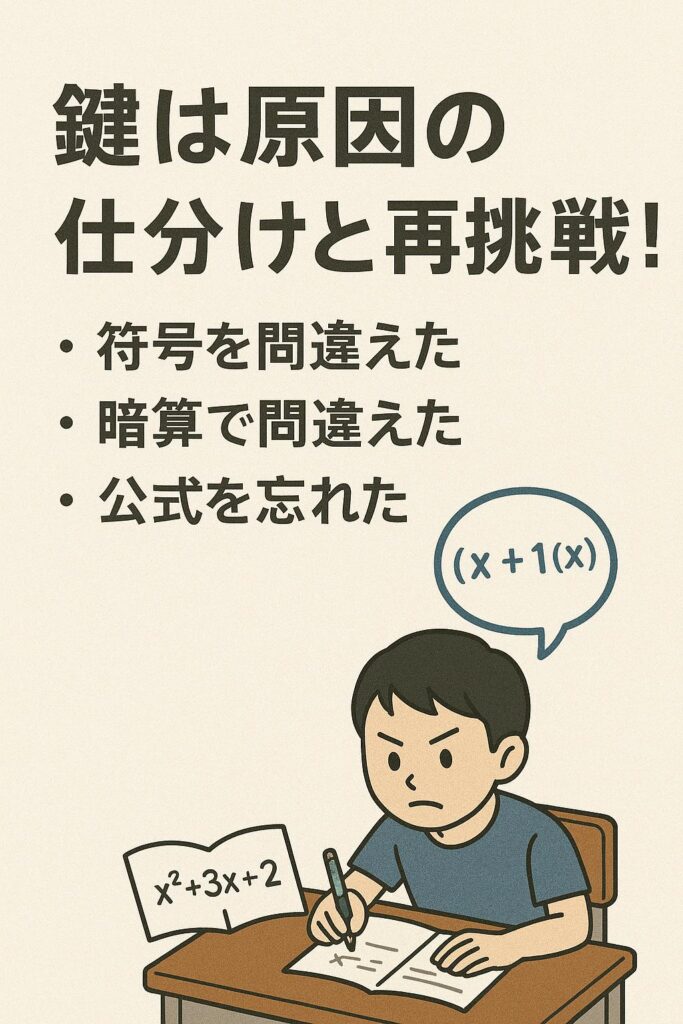
① 模試直後に「分析→復習」
模試を受けたら、その日のうち、または翌日までに分析と復習を行うことが大切です。
記憶が新しいうちに見直すことで、「なぜ解けなかったのか」「どこで間違えたのか」を正確に把握できます。
分析の手順は以下の通りです。
(1)間違えた問題に印をつける。
(2)自分の解答を見直し、誤答の原因を分類する。
- ケアレスミス(符号を落とした、問題文を読み飛ばした)
- 知識不足(公式や単語を覚えていない)
- 理解不足(考え方を根本的に誤っている)
(3)分類ごとに対策を立てる。
- ケアレスミス → 見直し習慣をつける
- 知識不足 → 暗記のやり直し
- 理解不足 → 参考書や解説を使い、基礎に戻って確認する
復習は「答えを写して終わり」ではなく、自分で再度解き切ることが重要です。
② 実際の試験時間を意識した演習
模試や入試は「知識量」だけではなく「時間内に解き切る力」が問われます。
そのため、普段の勉強から“時間を意識する”ことが欠かせません。
上記でも述べた通り、常に時間配分を意識し、想定通りの時間配分で動く練習を積み重ねることが非常に大切です。
③ 「なんで間違えたか」を言語化
模試の復習で最も効果的なのは、間違えた原因を言葉にすることです。
「計算ミスをした」「単語が分からなかった」で終わらせず、より具体的に掘り下げましょう。
・符号を確認しなかった。
・問題文の条件を読み落とした。
・単語の意味を勘違いした。
こうして言語化することで、対策が明確になります。そして、言語化された問題点を下に、
・符号を確認するために最後に必ずチェックする。
・設問に線を引く習慣をつける。
・毎日10語ずつ単語を復習する。
といった具体的な解決策を検討できるのです。
原因をあいまいにしたまま復習しても、同じ間違いを繰り返すだけ。
逆に原因を明確にすれば、具体的な対策により同じミスを防ぎ、次の模試で点数アップを実感できるでしょう。
ここからが勝負!科目別の具体的勉強法
模試後の反省を活かすためには、科目ごとに正しい勉強法を取り入れることが欠かせません。
ここでは、入試で特に差がつく【国語・英語・数学】について具体的な対策を紹介します。
【国語】
- 読解問題は「設問の指示語」に注目
模試で「答えの根拠が分からない」と感じる生徒は多いです。
実は設問の「この」「その」など指示語を追うだけで、本文の答えに直結する箇所を探しやすくなります。 - 意味が分からない言葉は調べる習慣を付けよう
文章を読む中で分からない語を“なんとなく”で読み流すと、文章理解が中途半端になります。
例えば「示唆」「抽象的」「皮肉」といった語句を正しく理解していないと、設問の答えを誤ることもあります。
国語辞典やアプリで調べる習慣をつけるだけで、確実に読解力が強化されます。
【英語】
- 文法は「なぜそうなるか」を理解
形だけを覚えると、少し変化しただけで解けなくなります。
「三単現の -s」は「主語が3人称単数だから」と理由まで理解することが必要です。 - 英作文はテンプレート+組み合わせ
「I think that…」「because…」など、よく使うフレーズを覚え、単語を入れ替える練習を繰り返しましょう。
シンプルな英文でも確実に書けることが得点につながります。 - 長文読解は「設問→本文」の順
問題文を先に読むことで、本文の中で答えに関係する箇所を効率的に探せます。
この順序を習慣化するだけで、時間切れを防ぎやすくなります。
【数学】
- 計算ミスの原因を仕分け
計算ミスを「仕方ない」で終わらせず、原因を具体的に分けましょう。
・符号を落とした → 確認不足
・暗算で間違えた → 手順管理不足
・公式を忘れた → 知識不足
原因を分類することで、改善のための行動が明確になります。 - 解説を読んだら必ず自力で再挑戦
解説を見て理解したつもりでも、いざ自分で解こうとするとできないことは多いです。
「二度解き」を習慣にすることで、考え方のプロセスまで定着します。
特に数学は「解き方を再現できるか」が成績アップのカギです。
結論
模試は「判定を受ける」ためのものではなく、「弱点を知り克服する」ためのものです。
模試直後に必ず分析と復習を行い、時間を意識した演習を積み、間違いの原因を具体的に言語化する。
これを徹底するだけで、模試のたびに着実に点数は伸びていきます。
さらに、国語・英語・数学の正しい勉強法を実践すれば、得点力は大きく変わります。
苦手を克服し、正しい努力を積み重ねることで、志望校合格のための力をつけていきましょう!
投稿者
小坂
有松校舎・金沢駅前校舎の小坂です!
▲▲クリックして小坂のブログ一覧(77ブログ公開中)を見る