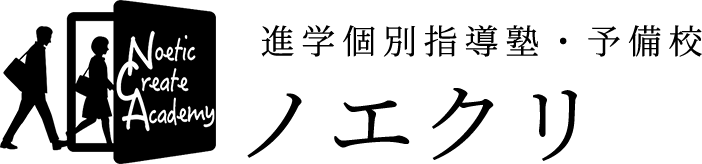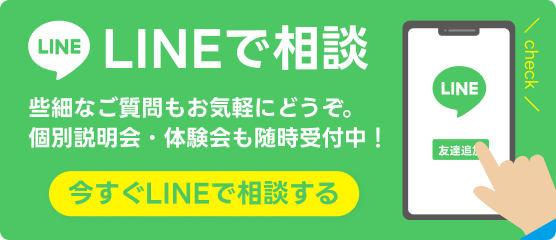富士高生必見!11月進研模試範囲と結果を出す勉強法【高1・高2】
2025.9.22
荷川取
富士市の進学校である富士高校の生徒にとって、11月進研模試は学年の折り返し地点を測る重要な模試です。
ここでの結果は「基礎がどれだけ固まっているか」「大学受験に向けた準備が進んでいるか」を映す鏡になります。
この記事では、11月進研模試の出題範囲予想と、高1・高2別の対策法を具体的に解説します。
目次
11月進研模試 範囲の予想(高1・高2)
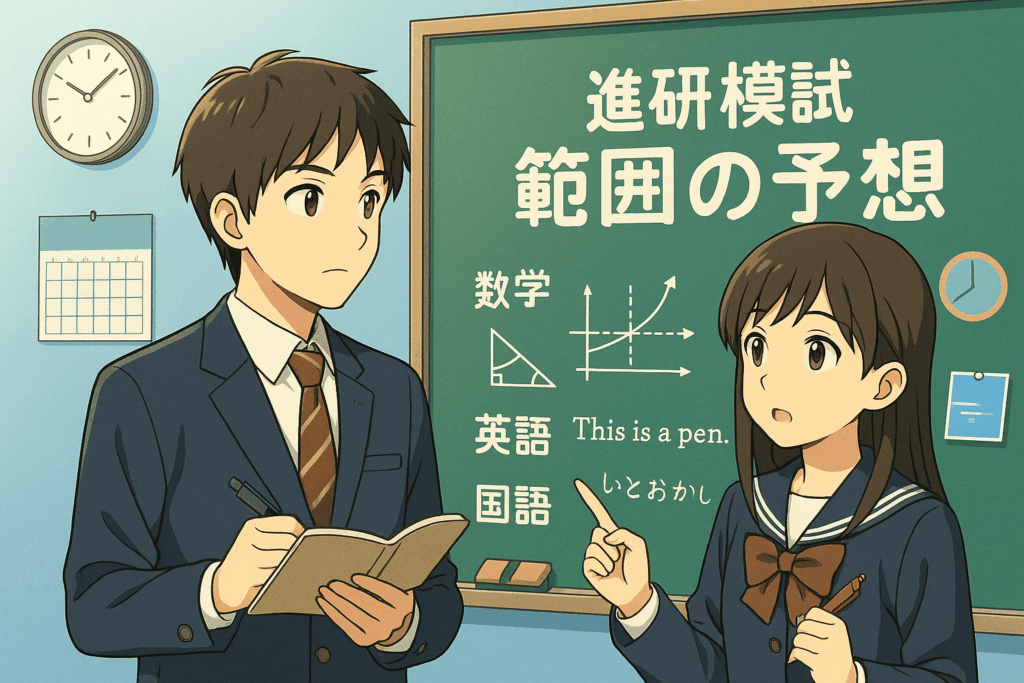
高1の予想範囲
| 教科 | 単元・内容の予想 |
|---|---|
| 数学 | 必答範囲として: ・数と式(因数分解・式の展開・平方根・整式の計算など) ・二次関数(最大・最小・グラフの読み取り・式とグラフの対応) ・場合の数・確率(基本的な確率計算・組み合わせ) 選択範囲として: ・図形と計量(平面図形中心、三角形・四角形の性質、円・相似) ・整数の性質(約数・倍数・素数など) |
| 英語 | 単語・熟語の語彙力、発音アクセント、文法(時制・比較・関係代名詞など基礎文法)、長文読解(文章の主旨把握・設問・接続詞など)、リスニング基礎 |
| 国語 | 現代文:評論・小説の読み取り、接続詞・指示語・要旨把握などの基礎力が問われる。古文:語彙と助動詞・古文の基本文法。漢文:返り点・読み下しの基本。 |
高2の予想範囲
| 教科 | 単元・内容の予想 |
|---|---|
| 数学 | 必答範囲として: ・数学Ⅰ(数と式、関数など全体) ・場合の数と確率(確率計算・統計的要素含む) ・式と証明 ・高次方程式(解の配置など) 選択問題から出題される可能性が高い単元: ・図形と方程式 ・三角関数 ・数列(漸化式以外) ・ベクトル(ただし空間ベクトルは除かれる可能性あり) |
| 理科 | 高2からは理科科目が模試に加わるパターンあり。予想される範囲: ・物理:力学 I(運動の法則・等加速度運動など) ・化学:物質の構成・化学反応と熱・酸と塩基など基礎項目 ・生物:細胞・生殖・発生など基礎部分 |
| 英語 | 語彙・熟語の量を増やす(基礎+難易度や文章レベルアップ) 文法はより幅広く(基礎だけでなく、比較・仮定法など使う問題) 長文読解のレベルアップ(複数段落、構造が複雑なもの) リスニング・発音も継続強化 |
| 国語 | 現代文:設問の根拠を本文に戻って読む習慣・テーマ理解・文章構造把握 古文・漢文:文法単語の確認と読解練習、多くの選択肢問題・記述問題に対応できる力 |
高1生向け|基礎を固めることが最大の武器
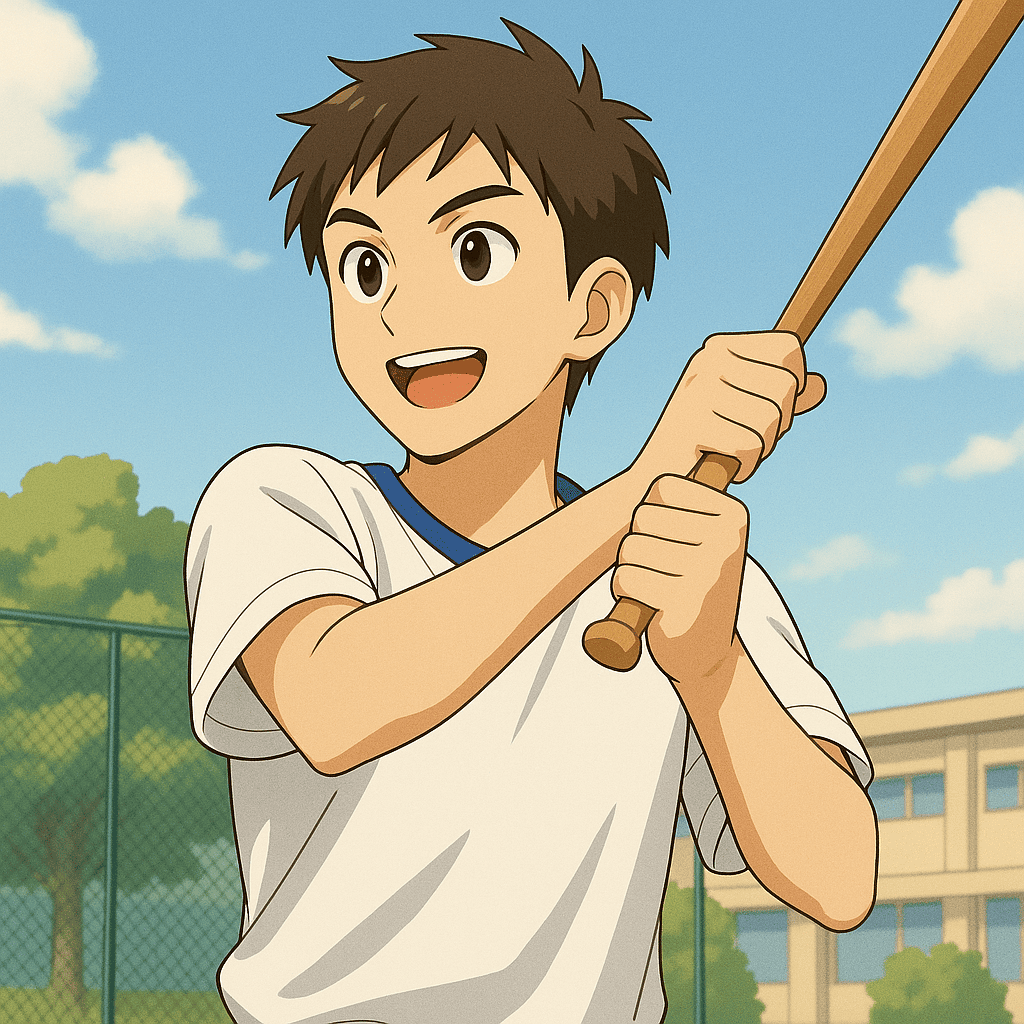
高1生にとって11月の進研模試は、「1学期〜2学期前半までに学んだ内容がどれだけ定着しているか」を確認する大切な場です。
ここで基礎が固まっていないと、高2以降の模試や大学受験本番で大きな差となって表れます。
数学
二次関数、確率、図形の基礎を徹底。特に関数は「場合分け」「式を立てる練習」を繰り返し、文章題に慣れることが大事です。
英語
単語と文法が得点源。この時期は模試といえども語彙力・文法力不足がそのまま得点差につながるので、1週間50語でも継続して覚えること。文法は間違えやすい「時制・仮定法・比較」を重点的に復習しましょう。
国語
現代文は主張に線を引きながら読む練習を。特に傍線部+その前後の「接続詞」「指示語」に注目すると正答率が上がります。古文は「主語の省略」に注意して、古文単語100語レベルを確実に暗記しておきましょう。
👉 難関大を狙う高1生の目標は国数英で偏差値60を安定させること。基礎を“穴のない状態”にするのが何より大事です。
高2生向け|共通テストを意識した実戦練習
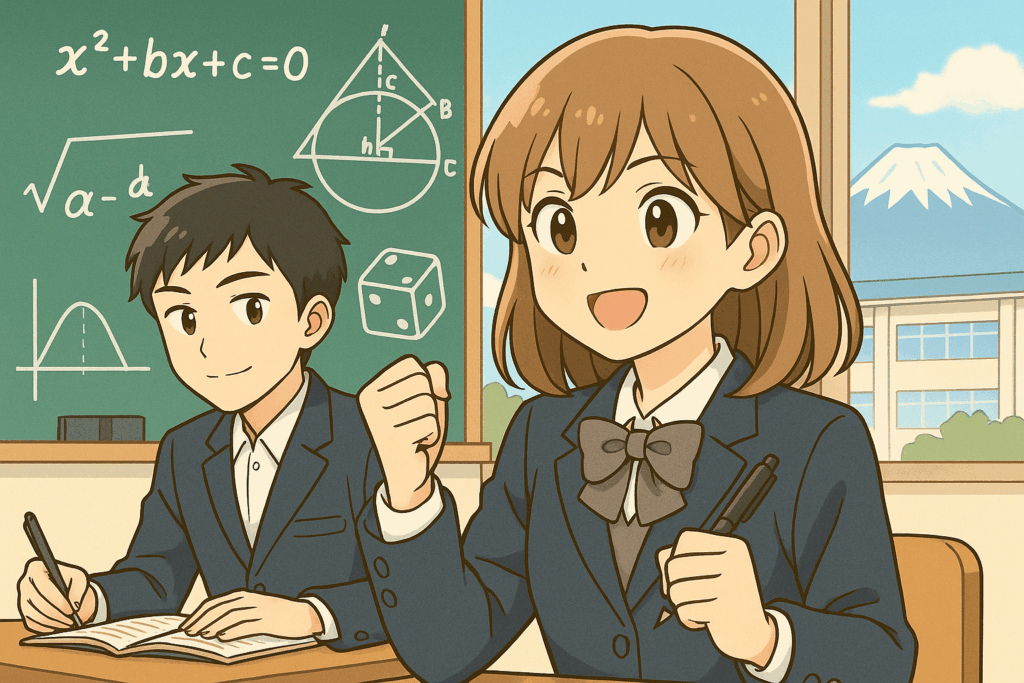
高2の11月模試は「受験学年への準備段階」として極めて重要です。ここでの結果が高3の夏以降の伸びを大きく左右します。
数学
「時間を測って解く」ことを習慣にしましょう。1問にこだわりすぎて最後まで解き切れないのが典型的な失敗です。関数・図形・数列を重点的に復習し、模試形式で実戦感覚を磨いてください。
英語
共通テスト形式に近い長文問題を意識。速読力をつけるために、毎日15分の多読をおすすめします。特に進研模試は語彙レベルが高めなので、英単語帳を1冊決めて集中的に仕上げていきましょう。
国語
古文・漢文の基礎文法を高2のうちに完成させてください。模試の正答率が低い分野は早めに克服しておくと、高3での伸びがスムーズになります。現代文はイコール・対立などの「論理的関係」を徹底した読み方を身につけましょう。
👉 難関大を目指す高2生の目標は 偏差値65突破。ここで“模試=本番練習”と考えて取り組むと、共通テスト・二次試験への橋渡しになります。
模試直前にやるべきこと
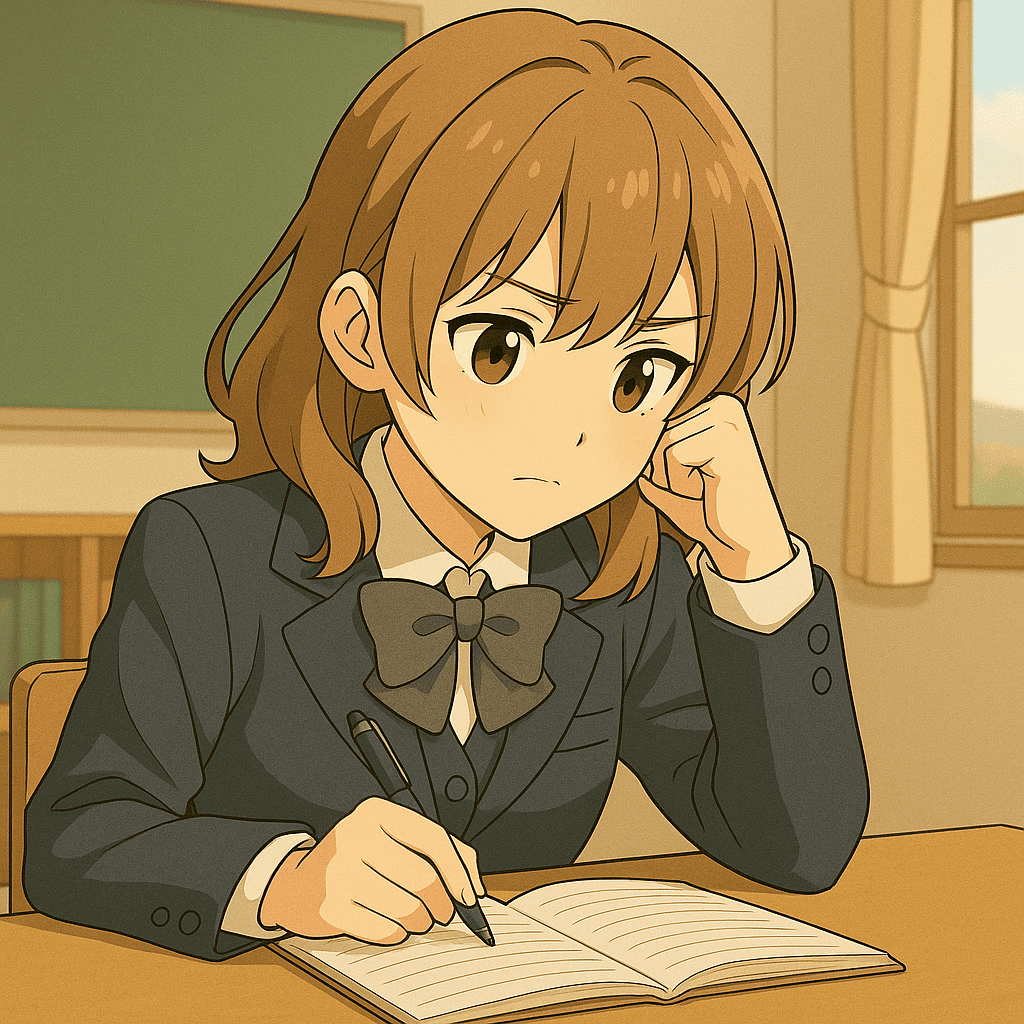
模試直前期は、新しいことを詰め込むよりも「これまで学んだ内容を整理し直し、確実に解ける問題を増やす」ことが最優先です。
英語
・単語帳を1冊に絞り、最初から最後まで“眺めるように確認”する。
・特に苦手な熟語・前置詞・不規則変化は赤シートを使って繰り返しチェック。
・長文問題は新しいものに手を出さず、これまでに解いた長文を「設問の根拠探し」に集中する。
数学
・チャートで「典型問題」を一気に解き直す。
・二次関数なら最大・最小やグラフ交点、確率ならサイコロ・カードなど頻出テーマを重点。
・「1問1分で解けるか?」を基準にスピード感を意識しながら演習すると、本番で慌てなくなる。
国語
・古文は単語100語を一気に見直す。助動詞(き・けり・む・べしなど)を確認しておくと失点防止になる。
・漢文は句形(再読文字・受身・使役)を声に出して確認。読み下しの練習を短時間で繰り返す。
・現代文は短い文章を声に出して読むことで、集中力と読解スピードを本番モードに整える。
👉 ポイントは「1科目=1冊」に絞り、仕上げとして“抜けを潰す”。直前にやったことが本番でそのまま出る、という実感を持てると安心して臨めます。
模試中に意識すべきこと
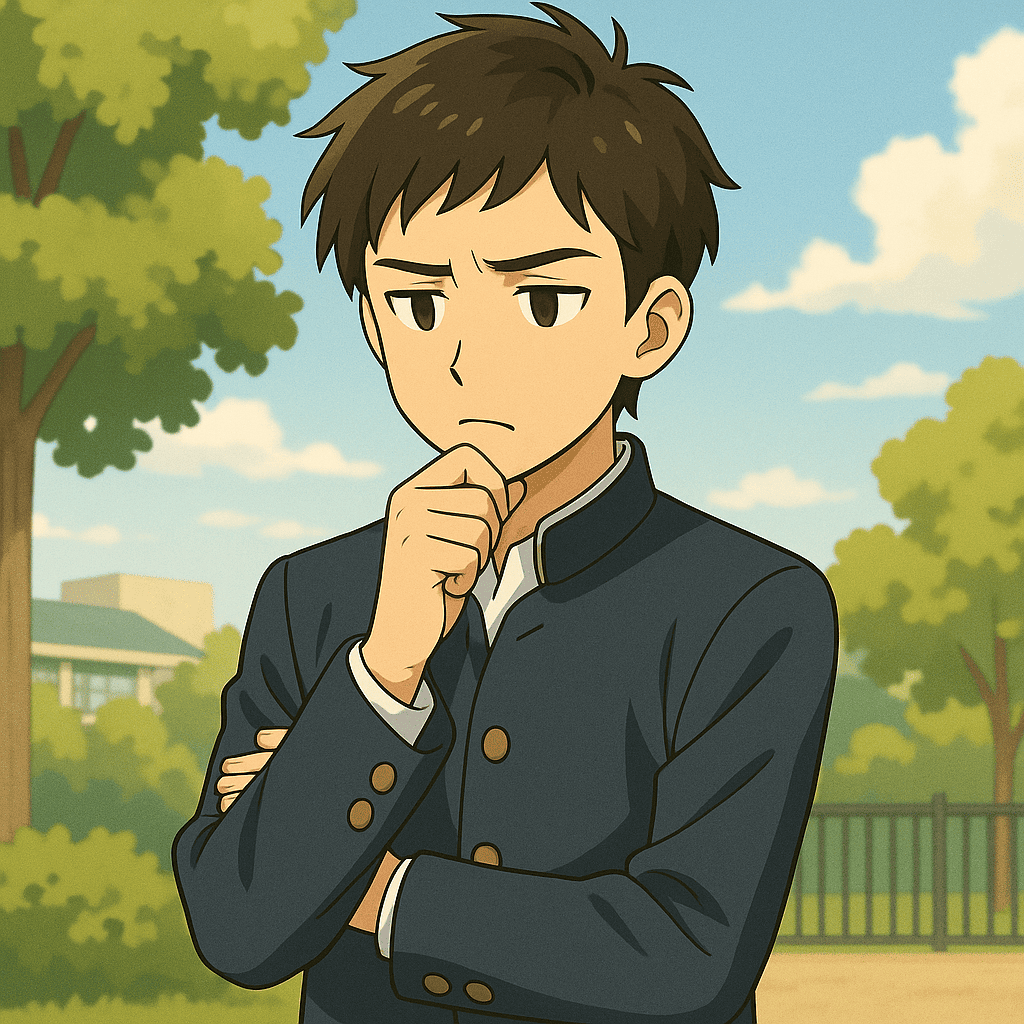
模試本番は「知識量」だけでなく、「時間の使い方」と「心構え」で結果が大きく変わります。
3分考えて解けなければ飛ばす
難問に執着して時間を使い切るのは典型的な失敗。3分考えて糸口が見えなければ、潔く飛ばして次に進む。
→ 飛ばした問題には必ずチェックをつけ、時間が余れば戻る。
小問集合を絶対に落とさない
数学や英語の最初の小問は、合否に直結する得点源。ここを確実に取れれば平均点を上回る確率が高くなる。
→ 「最初の10〜15分で確実に得点を稼ぐ」という意識を持つ。
見直しの時間を残す
最後の5分を「計算ミス」「選択ミス」のチェックに充てること。
・数学は計算過程をざっと見直す。
・英語・国語は選択問題のミスをチェック。
1点の取りこぼしが判定に響くため、最後の見直しこそ最大の得点調整になります。
👉 「満点を狙う」のではなく、「取れる問題を確実に取る」。この戦略が富士高生が模試で結果を出すための必勝法です。
模試後の復習法
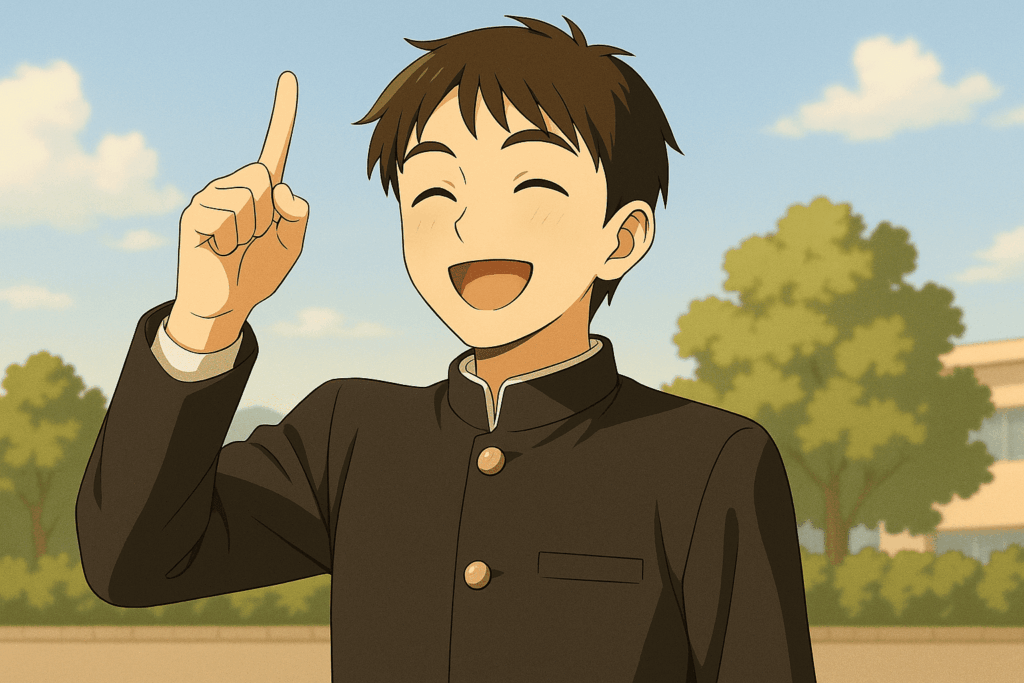
進研模試は、受けっぱなしでは効果が半減します。解き直しと原因分析こそが模試の真価です。
翌日に必ず解き直す
・間違えた問題に△をつけ、翌日に再挑戦。
・記憶が新しいうちにやると「なぜ間違えたか」が鮮明に理解できる。
正答率50%以上の問題を優先
・模試後に配布される「正答率一覧」を確認。
・全国の半分以上が解けた問題を落とすのは致命的。まずはここを100%取れるように復習する。
間違いの原因を分類する
・計算ミス → 焦り/途中式を省いたことが原因か
・知識不足 → 単語・公式の暗記漏れか
・時間切れ → 優先順位やスピード配分に問題があったか
分類することで、次の模試で改善策を具体的に実行できる。
解答・解説を音読する
・国語や英語は、模範解答を音読して「文章の流れ・解答の根拠」を体に染み込ませる。
・数学は途中式までノートに写し、「答案の書き方」を再現できるようにする。
👉 復習は翌日〜1週間以内にやり切ることが鉄則。早めに解き直すほど、11月模試の経験を12月以降の学習に生かせます。
まとめ|11月進研模試を飛躍のきっかけに
富士高生にとって、11月進研模試は単なる定期的なテストではなく、学年の折り返し地点で自分の立ち位置を確認する重要な模試です。
高1生は「基礎力の総点検」がテーマ。二次関数や場合の数など、典型問題を落とさず解けるかどうかが勝負。ここで基礎を固めておくと、高2以降の模試や大学受験で大きな武器になります。
高2生は「共通テストを意識した実戦練習」がテーマ。時間配分を意識しながら模試に臨むことで、受験学年に入ったときの伸びしろが大きく変わります。
さらに、直前期は「新しいことに手を出さず、抜けを潰す」。模試本番では「取れる問題を確実に取る戦略」を徹底。そして模試後は「解き直しと原因分析」を翌日から始める。この 3ステップの流れ を実行することで、模試が「受けて終わり」ではなく「成績を伸ばす起点」に変わります。
👉 11月模試は、7月模試で悔しい思いをした人にとっても挽回のチャンスです。しっかりと準備し、模試を自分の成長につなげることで、大学受験に向けた道筋をより確かなものにしていきましょう。
投稿者
荷川取
富士校舎の校舎長荷川取です!
▲▲クリックして荷川取のブログ一覧(84ブログ公開中)を見る