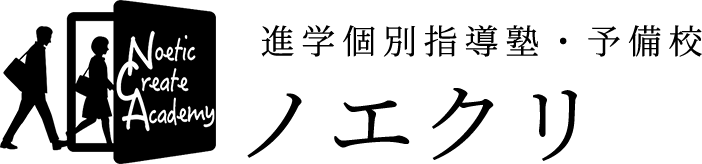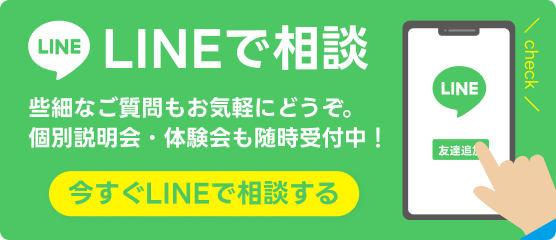2026年共通テスト 数学ⅠA対策|時間配分・出題傾向・時短テクニックを徹底解説
2025.8.6 共通テスト対策講座 大学受験オススメ情報
ノエクリ公式
目次
はじめに|共通テスト数学IAで高得点を取るために、まず知っておくべきこと

2026年度の大学入学共通テストは、これまで以上に「読解力・論理的思考力・数学的リテラシー」が求められる内容になることが予想されます。特に数学IAでは、単なる計算力だけでなく、「何を問われているかを読み解く力」や「条件を整理して選択肢を論理的に選ぶ力」が問われる傾向が、年々強まっています。
本記事では、2026年度共通テスト数学IAの出題傾向・対策方法・頻出単元の攻略法を徹底解説します。過去5年分のデータをもとに、今後出題される可能性の高いテーマや問題形式を予測しながら、9割得点を目指すために何をすべきかを明らかにしていきます。
共通テスト数学IAの基本情報|時間・配点・出題形式を正しく理解しよう
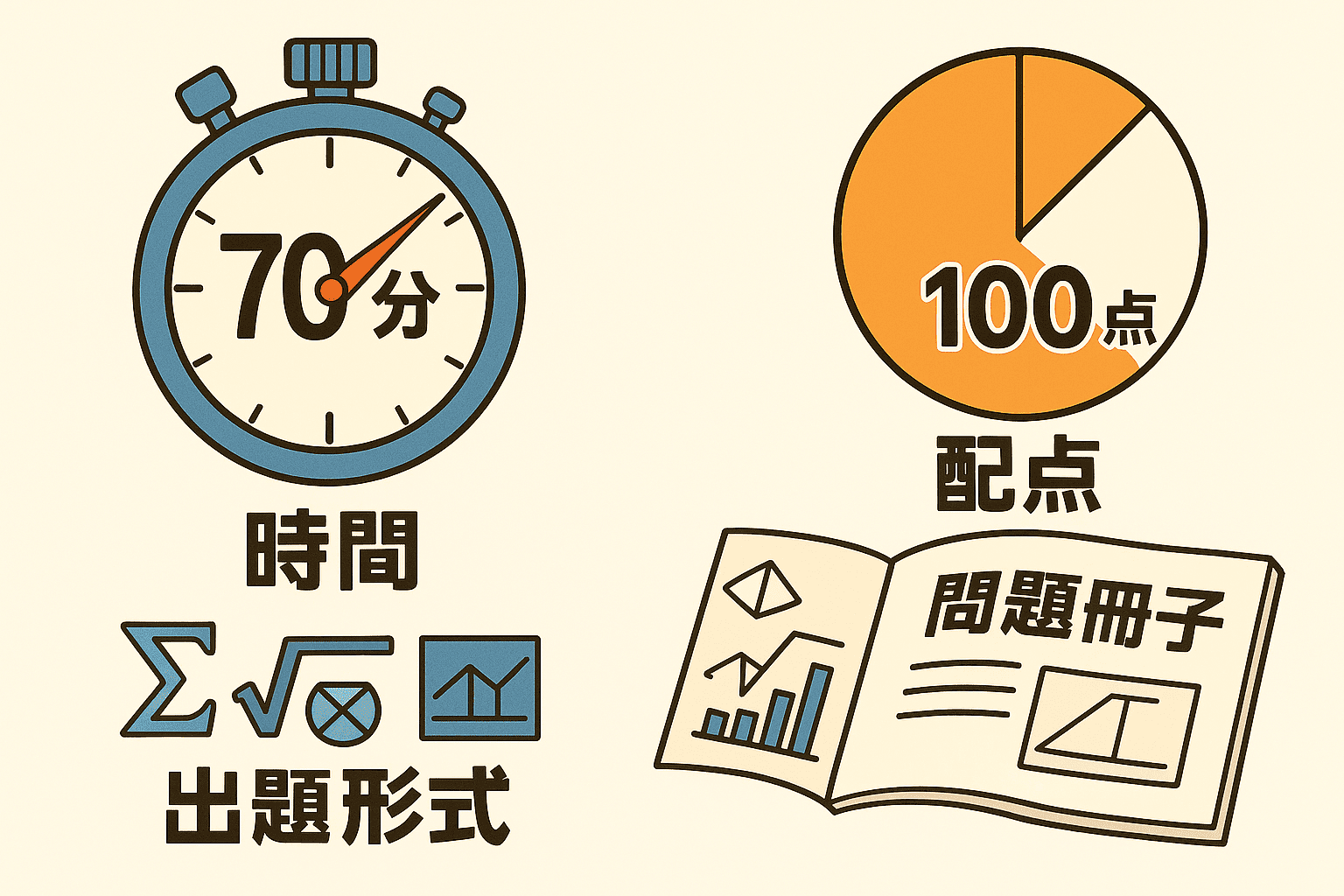
■ 試験の概要(2026年度 共通テスト 数学IA)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験時間 | 70分 |
| 満点 | 100点 |
| 問題数 | 大問4題(すべて必答) |
| 解答形式 | マークシート方式 |
| 実施日 | 2026年1月18日・19日予定(暫定) |
2025年度からの形式変更により、共通テスト数学IAは大問4題・すべて必答となりました。
この変更により、選択問題(第4問・第5問のどちらかを選ぶ)という形式が廃止され、すべての分野をまんべんなく学習しておく必要が生じました。
■ 2025年度(最新)の出題構成とポイント
| 大問 | 出題単元 | 主な内容 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 数と式・図形と計量 | 方程式の解、十分条件・必要条件、円と接線を用いた図形構成 | 30点 |
| 第2問 | 二次関数・データの分析 | 放物線の性質・式決定、仮説検定・散布図からの正誤判定 | 30点 |
| 第3問 | 図形の性質(空間図形) | 五面体の構造、交線・相似、命題の真偽 | 20点 |
| 第4問 | 場合の数と確率 | 景品ゲームを題材にした期待値計算と確率の理解 | 20点 |
■ 時間配分と戦略
70分で大問4題、すべて必答。以下が時間配分の目安となります。
【理想的な時間配分例】

ただし、これはあくまで例に過ぎず、大切なのは練習の中で以下を実践していくことです。
①解ける問題から解くこと
②自分に合った時間配分を見つけること
③各大問の目標時間からマイナス1~2分で解くこと
こうすることで、制限時間内に解く力・安定した得点力が身につきます。
時間が足りない人へ|得点を落とさず時間を短縮するテクニック集
「解けるのに時間が足りない」
「最後の大問がまるまる手つかずだった…」
そんな声が多く聞かれる共通テスト数学IA。70分で大問4題(全て必答)は、想像以上に時間に追われます。
ここでは、得点を落とさずに時間を確保するための実戦的テクニックを紹介します。
■ テクニック①:計算を“途中式付きで最短ルート化”する

【よくあるミス】
✔ 式をすべて丁寧に書いて逆に時間を使いすぎる
✔ 暗算でやって間違えて見直しにも時間を使う
【時短ポイント】
- 途中式は「1段飛ばし」でまとめて書く(例:●●→2a+3a+a → 6a の計算は一段飛ばしで6aだけ書けば十分)
- 暗算ではなく、“見直し可能なメモレベル”で式を残すことで、後戻りが不要に
■ テクニック②:読む前に設問構造をざっくり眺める
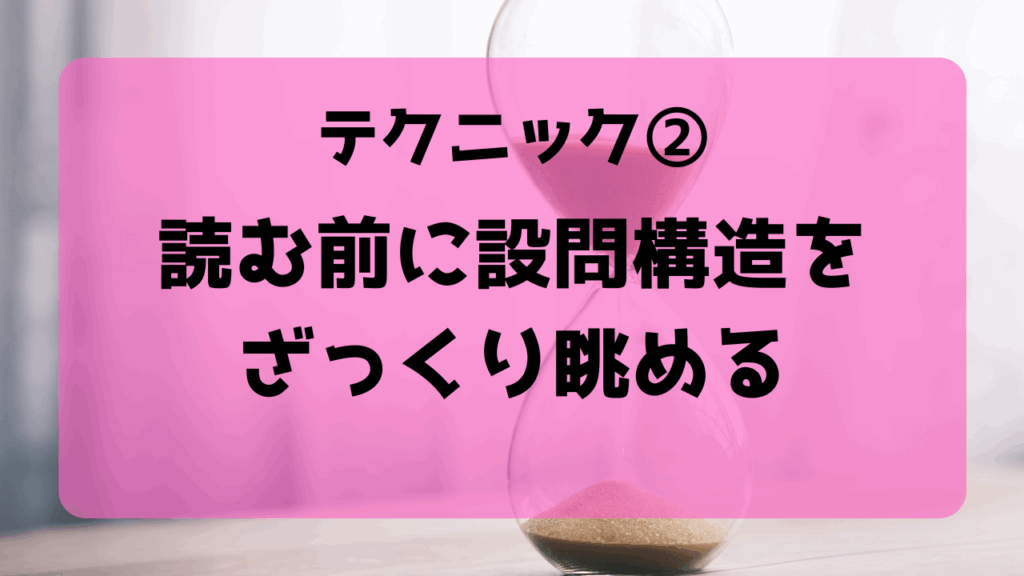
【よくあるミス】
✔ 最初から1文ずつ丁寧に読んでしまい、何が問われるか分からないまま時間を使う
【時短ポイント】
- まず(1)(2)(3)…と設問全体をざっと見る
- 「この問題は何をゴールにしているのか?」「出題者の意図」を掴んでから本文に戻る
→ 意図を持って読むことで、誘導に乗りやすくなり、「何をメモすべきか」が明確になる
■ テクニック③:「選択肢問題」は絞り込みに全力を
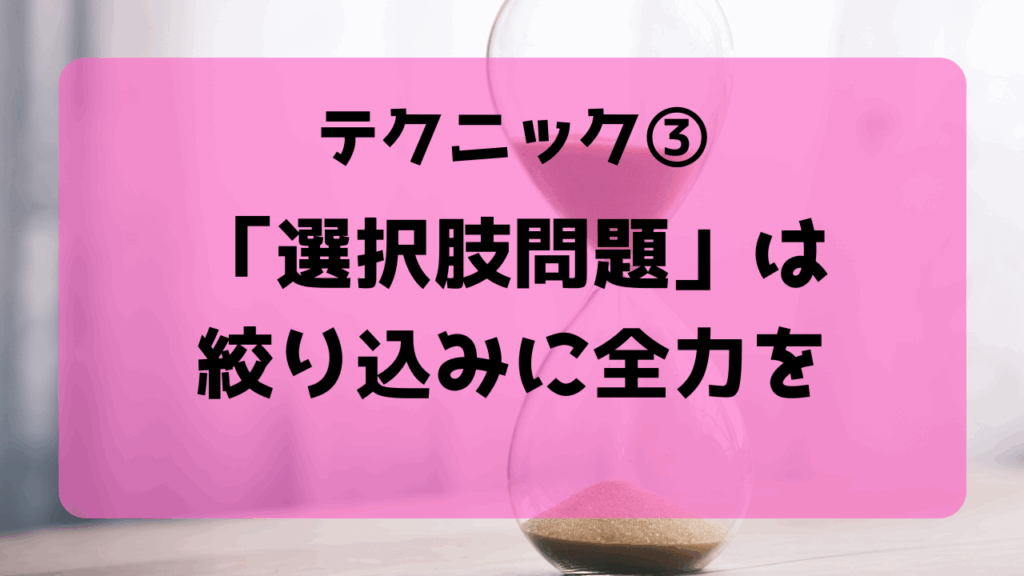
【よくあるミス】
✔ 最初からすべての選択肢を計算して時間を消耗
✔ 自信がなくて全パターン確認してしまう
【時短ポイント】
- 一発で正解を出すのではなく、消去法で「誤り」を潰す戦略
- 特に「単位・符号・値の範囲」などで即消去できる選択肢が多い
- 最終2択に絞れれば、2択×確信度アップ=時間効率UP+正答率UP
■ テクニック④:図形問題は“手書き図”を即作成
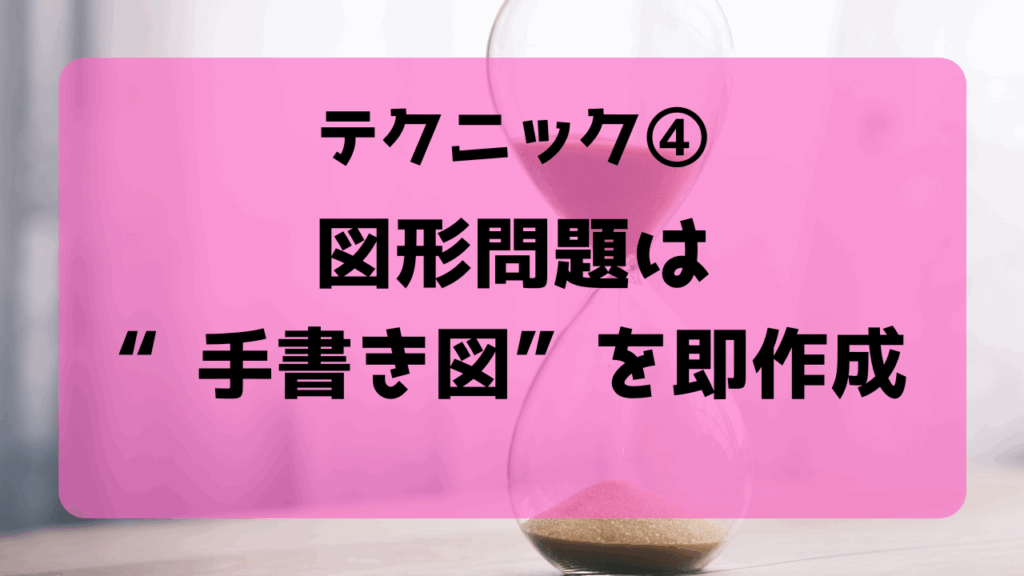
【よくあるミス】
✔ 問題の図だけを目で追い、補助線を引かず思考停止
✔ 頭の中で考えようとして時間ロス
【時短ポイント】
- 与えられた図が見にくい・小さいと感じたら、迷わず自分で描く!
- 図形問題は“図を書く→補助線を引く→数値を整理する”までがワンセット
→ 目に見える状態をつくることで、時間のかかる思考を短縮可能
■ テクニック⑤:時間感覚を意識する“仮のリミット”を設定
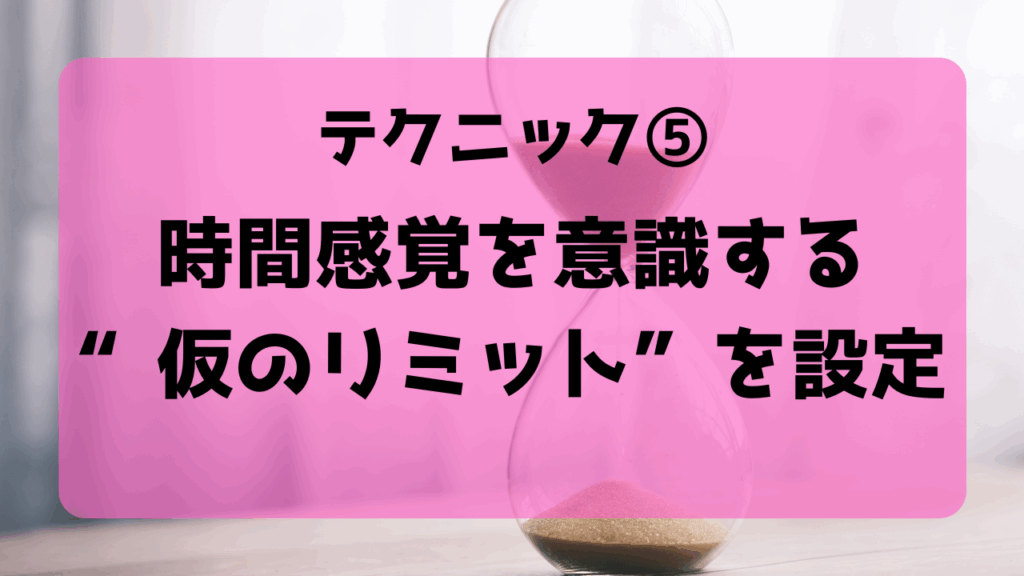
【よくあるミス】
✔ 1つの問題にこだわりすぎて、後半をまるごと失う
✔ 時計を見ても「どのくらい遅れているか」が把握できない
【時短ポイント】
- 目安:1題あたり14〜21分(30点配点の第1・2問は少し多め)
- 12分or18分経過して1題に取り組み中なら、「次の設問で一度飛ばす」判断を
→ 仮のリミットを設けることで、時間感覚が狂うのを防止
■ まとめ:時短は「処理を速くする」より「迷いを減らす」
多くの受験生は、計算スピードよりも“判断や迷いの時間”に多くの時間を使っています。
時短の本質は、以下のような「迷わないためのルールづくり」です。
- 式はこのレベルまで書く
- 誘導はまず全体構造を見る
- 選択肢は消去法から
- 図形は描く、見て考えない
- ○分以上かかったら一度飛ばす
これらを演習段階から徹底すれば、70分という時間を最大限活かせるようになります。
2026年度予測|今年の出題傾向はこう来る!
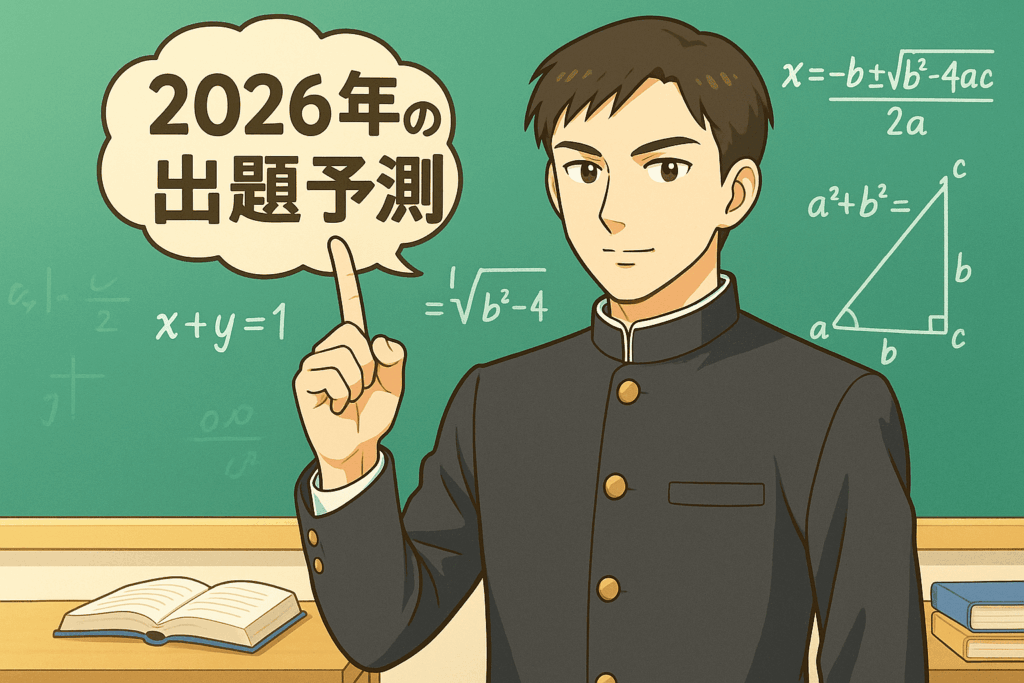
2025年度から大きく形式が変わった共通テスト数学IA。
「大問4題・全問必答」となり、各分野がはっきり分かれた出題に刷新されました。
2026年度もこの出題形式は継続される見込みですが、設問構成やデータの扱い方に変化が生じ、全体として難化する可能性が高いと予想されます。
2025年度の問題を踏まえたうえで、2026年度の出題を以下のように予測します。
■ 第1問:方程式と図形の論理性がさらに問われる?

予想される方向性
- 因数分解や式の値の計算など基本問題は残る。
- 「必要条件・十分条件」や命題の真偽判定など、論理の理解を求める出題が継続。
- 「円と接線」「三角形の成立条件」など、図形的要素を論理的に説明する力が必要。
難化ポイント
- 単純な解法暗記ではなく、「なぜその条件が成り立つのか」を理解していないと誘導に乗れない。
日ごろの勉強法
- 教科書例題や典型問題を解く際、「なぜその解法になるのか」を説明する練習をする。
- 命題や条件に関する問題は、逆・裏・対偶を言葉で書き出し、論理関係を整理する。
- 図形問題は、補助線を引いて「どの定理が使えるか」を即座に見つける訓練を積む。
■ 第2問:複合的処理とデータの読解が深化
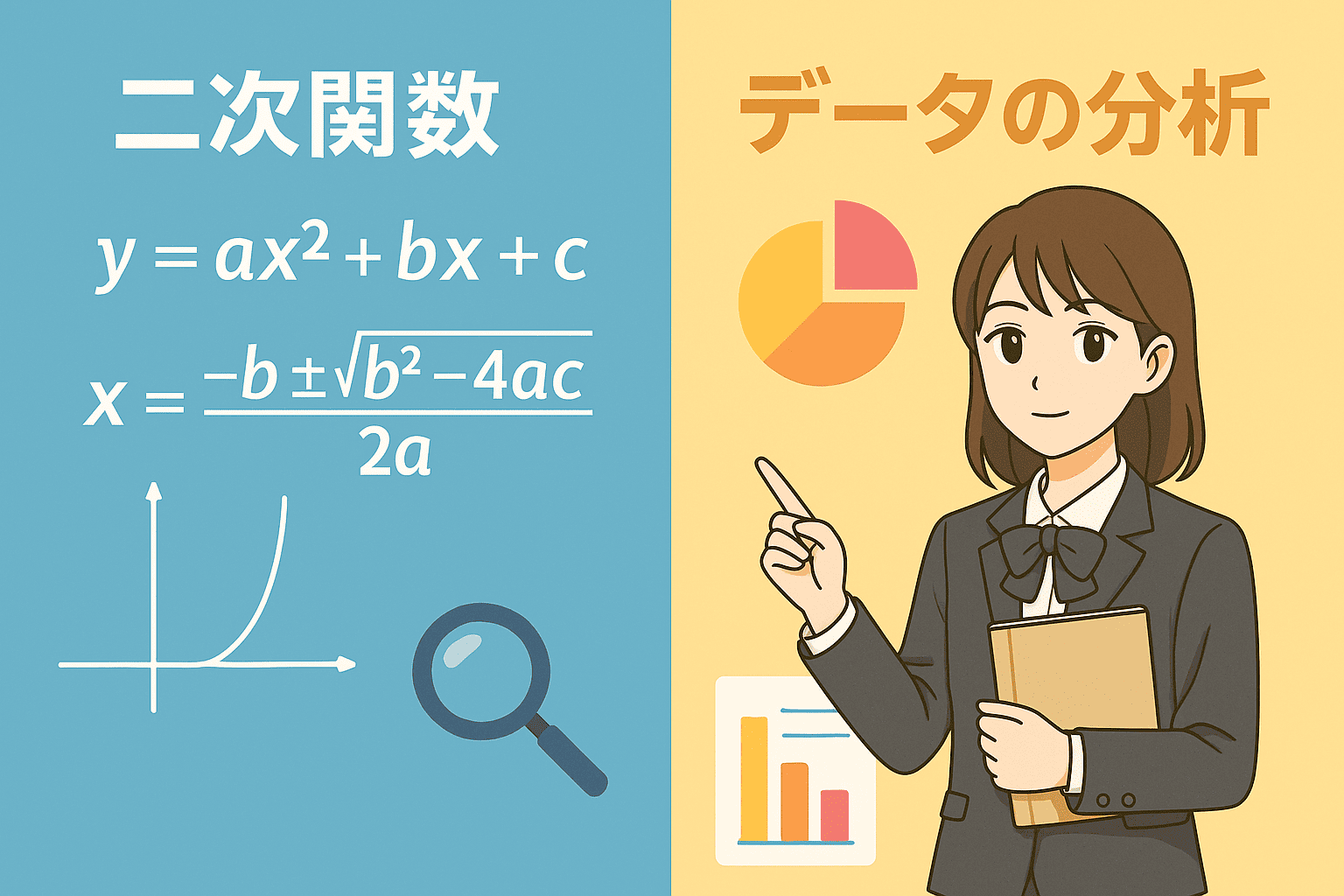
予想される方向性
- 二次関数では放物線の最大・最小、2次不等式を応用的に扱う。
- データの分析では「分散比較」「仮説検定」「外れ値判定」など、2025年度に登場した新傾向が再登場の可能性大。
難化ポイント
- 計算処理だけでなく、グラフや説明文を読解して判断を下す力が必要。
日ごろの勉強法
- 二次関数は「グラフのイメージと式の関係」を意識し、図示して理解を深める。
- データ分析では、教科書の統計問題を使い、散布図や箱ひげ図を自分で描きながら整理する。
- 仮説検定は「母平均が同じかどうかを調べる手順」を、具体例で声に出して説明できるように練習する。
■ 第3問:空間図形における構造理解と命題の論証

予想される方向性
- 五面体や複雑な立体を舞台にした問題が継続。
- 交線や相似など、立体の構造を把握する力が求められる。
難化ポイント
- 「証明の穴埋め」「命題の真偽判定」など論証的な要素が強化される可能性。
日ごろの勉強法
- 空間図形の問題を必ず「手で図を描く」習慣をつける。
- 正方体や五面体などを使った基本問題を、自分で展開図や断面図を描いて解く。
- 命題問題は「正しいときの証明」「間違っているときの反例」を両方考える練習をする。
■ 第4問:確率+期待値の「意味理解」が重要に

予想される方向性
- くじやゲームなど身近な題材で、期待値の意味を問う問題が継続。
- 主催者と参加者という「立場の違い」を考えさせる設問が出やすい。
難化ポイント
- 確率の数値処理は標準的でも、「条件の意味」を誤解すると初手から崩れる。
- 「どの立場で期待値を求めるのか」という読解力が得点の分かれ目に。
日ごろの勉強法
- 期待値の問題を「表」や「ツリー図」で整理する習慣をつける。
- 「主催者側・参加者側」の両視点から期待値を計算する練習をしておく。
- 条件付き確率は、必ず母集団を明確に書き出してから場合分けを進める。
■ 総まとめ:2026年度は“難化傾向”に警戒を
2025年度は「新形式初年度」ということで、典型的な問題配置が中心でした。
しかし、2026年度は 「出題者の誘導の意図を正確にくみ取り、数理的な判断力を発揮できるか」 がさらに強く問われると予想されます。
特に次の2点を意識した学習が欠かせません:
・ただ公式を当てはめるのではなく、「なぜその図形が描かれているのか」「この式はどの条件を表しているのか」といった構造理解が必要。
・見慣れない設定でも、与えられた条件を言葉や数式で整理し、筋道立てて判断できるかが鍵となる。
また、出題形式の変化に対応するために次の演習が有効です:
・頻出分野(場合の数・二次関数・図形など)は基礎を確実に固める
・「文章で条件が書かれた問題」「説明文を伴う設問」に慣れる演習を積む
・新傾向の統計問題(分散の比較・仮説検定)や、空間図形の命題判断を模試・予想問題で繰り返し練習する
どこで差がつく?高得点者が意識する3つのポイント
共通テスト数学IAは、「難問を解けるかどうか」よりも、“落とさない力”と“流れを読む力”で差がつく試験です。
ここでは、実際に8割〜9割以上を安定して取る受験生が実践している3つの視点を紹介します。
① 問題文を“読む”のではなく、“構造をとらえる”
共通テストの特徴は、文章量の多さと条件の複雑さ。
しかし、高得点層はここで「情報を読み飛ばす」のではなく、必要な情報を図や表に置き換えて整理しています。
- □ 良い例:「2つの条件から式を立てて、図形の構造に落とし込む」
- □ 悪い例:「文章を何度も読み返して、どこに何があるか迷子になる」
👉 ポイントは、「読解」ではなく「構造化」。問題文を、図・式・表に変換するトレーニングを日頃から積んでおくことが重要です。
② 「誘導に乗る」意識をもつ
共通テストの数学では、次の問いのヒントが前の設問に隠れていることがほとんどです。
いきなり(3)だけを見て戸惑うのではなく、(1)→(2)→(3)の“流れ”を意識して一体で解くようにしましょう。
- □ ありがちな失点例:「(1)は簡単だったが、(2)から急に難しく感じて空欄に…」
- □ 高得点者の行動:「(1)の答えをヒントに、(2)の条件が“何を求めさせたいのか”を逆算して考える」
👉 誘導の流れに素直に乗りながら、設問の意図を探る読み方を身につけましょう。
③選択肢問題は“即座に”絞り込む
共通テストでは、「どの選択肢が正しいか?」を問う形式が多く出題されます。
このとき大切なのは、“なんとなく正しそう”で選ばないこと。
必ず、単位・符号・値の範囲・解答欄などの観点から、消去法で”即座に”根拠を持って絞り込むことが必要です。
□ 高得点者の思考:「この単位ではありえない」「符号が矛盾している」「範囲外の値だから不適切」など、除外できる理由を積み重ねて残った選択肢を丁寧に比較する。
👉 1つ1つ丁寧に、ではなく、即座に絞り込み+残った選択肢を丁寧に判断することが得点差を生むポイントになります。
まとめ:高得点者は「深い思考」よりも「正確な処理と理解」
共通テスト数学IAで9割を取る受験生が特別なひらめきを使っているわけではありません。
彼らが実践しているのは以下の3点です:
- 問題文を“構造化”する
- 誘導の“意図”を読む
- 選択肢は”即座に”絞り込む
この3つを日頃の演習で意識することで、凡ミスを減らし、安定して高得点が狙えるようになります。
まとめ|形式は固まった、差がつくのは「中身」
2026年度の共通テスト数学IAは、前年と同様に大問4題・全問必答形式で実施される見込みです。
形式が固定された今、問われるのは「中身の理解」と「対応力」です。
✔ 分野ごとの得点戦略がカギ
出題範囲が明確なぶん、どこで点を取るかを決めて準備できるようになりました。
特に第1・第2問で確実に取り、第3・第4問で差をつけましょう。
✔ 難化に備えた「読解・処理力」の強化を
設問の文量や設定が複雑になる傾向があります。
ただ解けるだけでなく、「読み取りながら考える力」が今後さらに重要になります。
✔ 本番形式での演習を早めにスタート
形式に慣れ、時間配分とケアレスミスの感覚を体に染み込ませることが、安定得点への近道です。
地に足のついた基礎力と実戦形式の慣れ。
この2つがあれば、共通テスト数学IAは必ず武器になります。
今から一歩ずつ、戦える土台を作っていきましょう。
投稿者
ノエクリ公式
進学個別指導塾ノエクリの公式アカウントです。
合格速報などのノエクリ最新の情報をお届けします。
▲▲クリックしてノエクリ公式のブログ一覧(106ブログ公開中)を見る