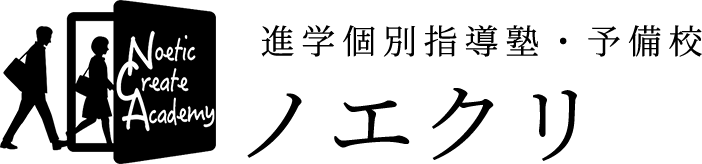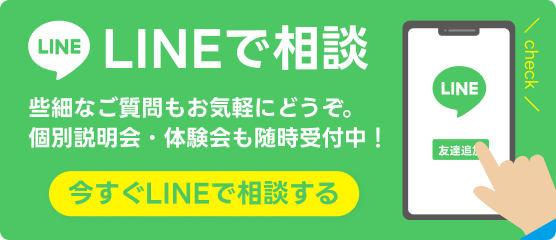得点を最大化するための試験時間の使い方
2025.11.11
清水
こんにちは。
進学個別指導塾ノエクリです。
前回のブログで、試験での時間配分で、簡単にお話をさせて頂きましたので、今回はその部分の実践的なことについてお話していきたいと思います。
前回ブログを読んでない方は、先に読んで頂けたらと思います。
今回は、2025年の京都大学理系数学の問題を使いながら、考えていたことと気をつけたことについてお話していきます。(試験時間は150分です)
step1.問題の概要を把握する(15分)
大問1:小集合の問題となりますが、複素数の問題も定積分の問題なく解けるなと思いました。落ち着いて、解けば大丈夫と感じる内容だと思います。これは、10分~15分で解きたいなと思いました!
※問題なく解けるというのは、解法がすぐに思いついたという意味です!大問2:整数の問題となりますが、私は整数問題を得意にしており、今回の問題も合同式を用いれば、問題なく解けるなと思いました。これも、10分~15分で解きたいなと思いました!
(ただし、整数問題は手を動かし始めると実は思っていたよりも複雑というケースもあるので、想定よりも10分は伸びてもいいとしておく)
※整数問題は、基本的に難しくなる可能性が高いので、普通は、後半に解くのをおススメします!実際今回の問題につきましても、整数問題に慣れていない人や苦手に感じる人にとっては難しい問題だと思いますし、難しいと評価している予備校がほとんどでした!大問3:微分の問題でこちらも問題なく解けるなと思いました。問題の条件に合わせて、大問1と同じように、落ち着いて計算をすれば大丈夫と感じる内容だと思います。これも、10分~15分で解きたいなと思いました!
ここまでの大問1~3までの問題に目を通した時点で、この後難問が来ても十分に時間を確保して解けるなと感じました。問題把握~大問3つを解いても60分で終わるなという感覚です!
大問4:(1)の証明に時間がかかるなと感じ、また、(2)については(1)が出来れば問題なく出来るので、(1)が出来るかが大事!(1)のアプローチに10分は思考して、トータルで25分~30分で解きたいと思いました!
大問5:点Qの座標は、ベクトルを用いて求めていけば、問題なく解けるのではないのかと感じ、点Qを求めた後は、軌跡を求める要領で式変形まで出来れば、そのままいけると思うが、複雑になる可能性もあるので、少し多めに時間を見積もり15分~20分で解くようにしよう!
大問6:問題事象の把握に時間がかかるので、大問1~5をしっかりと解き切った後で、解くことが大切だと感じました。この大問6は、捨て問になっても構わないという精神状態が大切だと思います!
一通り問題をみて、方針を考えた後は、どの手順で解いていくかを考えます!
今回であれば、1→2→3→5→4→6の順で解いていき、4完プラス少しが取れそうで、合格ラインは余裕をもって超えれるなと考えます!
問題を俯瞰してみた時に、おおよそで合格ラインつまり周りのライバルたちがどのくらいとっているのかを考えて解いていくことは、試験時の不安を和らげるためには必要になりますので、是非活用してみてほしいと思います!step2.実際に解いていく!(120分)
ここからstep1ですでに指針を立ててあるので、そこに沿って問題を解いていきます!
実際は、大問4で15分程時間を使って、アプローチの方法を考え、そこが固まれば15分程で解答が完了して、30分程で終えた形となり、それ以外は想定時間より少し短めに終わった形となります。
ただし、大問6は、解法の切り口を考えて、そこから解答作成に時間がかかってしまうので、状況を把握して、遷移図を書いて関係式を立てるまでが出来れば十分だと思います!
step3.見直しの徹底(15分)
どの試験にもいえることですが、ミスをしないことがとても大切です!もちろん、分からない問題を解き続けることも大切ですが、それで完璧に解き切れる保証はありません!だからこそ、点数を確実に取るために、
「計算や式変形は合っているか」
「同値の使い方が間違っていないか」
「議論不足のところがないのか」
など、細かい部分を確認していきます!そうすることで、そのテストでの「点数の最大化」を図ることが出来ます!
最後に
いかがでしょうか。今回は、問題をみた時の所感という部分に焦点を当てて、私が感じる部分について書かせて頂きました。もちろん、前から解いていく方もいると思いますが、それだと余程出来る方でない限り、本来とれる点数よりも低くなる可能性が高いです!
テストという試合を、どのようにしていけばが勝つこと(つまり合格点をとれるのか)に繋がるのかを試験時間全体で考えていくイメージを持ってみて下さい!
はじめから、やみくもに闘っても難しいですよね!ペース配分が大切になり、そこを把握するための最初の15分だと思います!
数学だけでなく、他の科目であっても自分に合った戦略を考えることが大切です!
英語であれば、「長文」もしくは「英文和訳」から解くのか
国語であれば、「現代文」もしくは「古典」から解くのか
物理であれば、「力学」もしくは「電磁気」から解くのか
化学であれば、「理論」もしくは「有機」から解くのか
細かいかもしれませんが、この最初の選択やこういう問題だったら解くなどを細かく決めておくことが合格に向けて大切です!
こんなこと言われてもどうやっていいか分からないと思います!
是非ノエクリを頼って下さい!ノエクリでは、こういった受験の戦略までも一人一人に合わせて考えます!
少しでも気になった方は是非一度お問い合わせください!
投稿者
清水
小松校舎の清水です!
▲▲クリックして清水のブログ一覧(47ブログ公開中)を見る