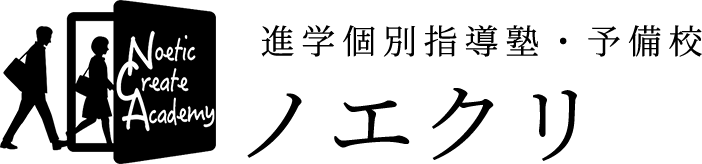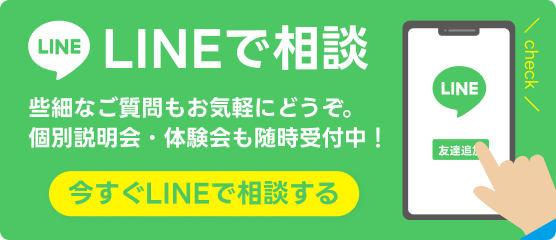【金大附属中学】間違いの“原因”を言語化しよう!理科のミス分析こそ合格のカギ!【中学1・2年】
2025.11.18 有松校 金沢駅前校
小坂

目次
はじめに
皆さんこんにちは!進学個別指導塾ノエクリの小坂です!本日は、附属高校受験を目指す方に向けて、附属高校が求める「理科」の力についてお話し致します!
金大附属中に通うお子さまの保護者の方から、
「理科の点数が安定しない」
「暗記はしているのに問題になると手が止まる」
「どの単元が苦手なのか、親から見てもよく分からない」
といった相談をいただくことは珍しくありません。理科は、社会や国語、英語に比べると“見えにくい弱点”が多いため、保護者の方が学習状況をつかみにくい教科でもあります。
実は、理科は「どれだけ覚えたか」よりも、「どの段階で間違えるか」で伸び方が決まる教科です!特に金大附属高校の理科は、覚えた用語をそのまま答える試験ではなく、観察文や実験結果、資料を読み取り、理由を説明する力を問う構成のため、「ミスの原因」を特定できる生徒ほど得点が安定します!
ノエクリの授業では、問題を解くだけで終わらせず、なぜミスしたのかを生徒と一緒に言葉にしていく双方向授業を柱としています。この“言語化によるミス分析”が、附属高校入試への大きな強みとなります。
金大附属高校の理科は“ミスで差がつく試験”!
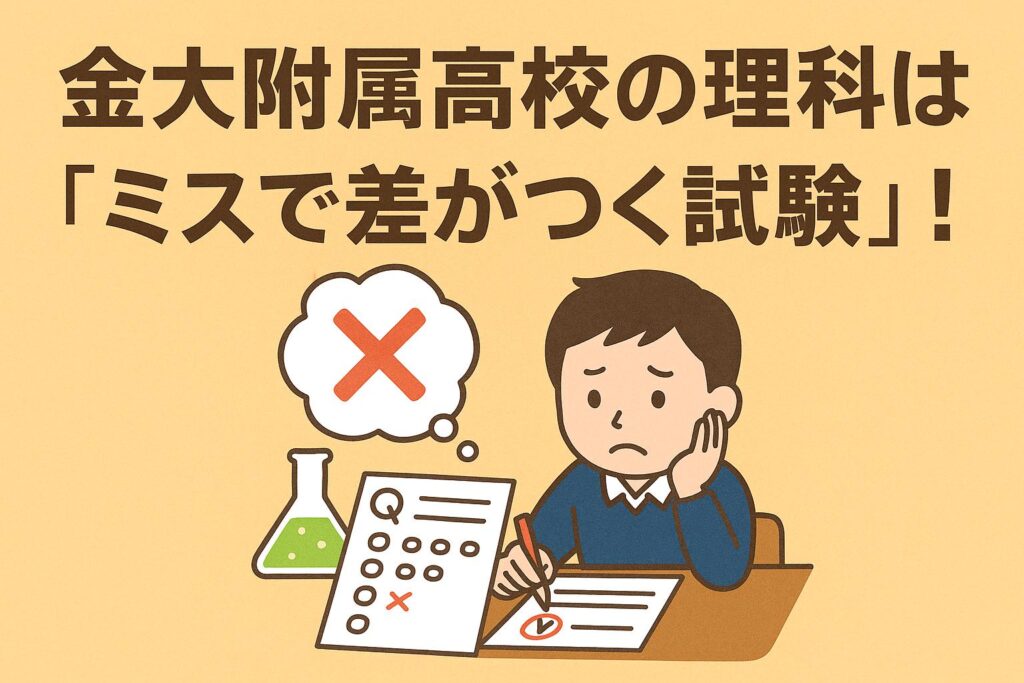
金大附属高校の理科の特徴は、暗記量よりも理解の深さや考察力を見抜くことに重点があります。ミスの構造と結びつけて見ると、その特性が非常に分かりやすく浮かび上がります!
まず、実験や観察の文章量が多く、条件文の読み落としが非常に起きやすいという点があります。「書いてあるのに読んでいないミス」が大きな得点差になるのが附属高校理科の特徴です。また、計算問題では単純な計算ミスよりも、どの公式を使うべきかの判断ミスが多く見られます。公式自体は理解できているのに、状況に応じて適切に選び直せないという“思考のズレ”が起こりやすいのです。
さらに、附属高校の理科はグラフ・図・表の問題が非常に多いことが指摘されています。グラフの傾きの意味、変化の読み取り、単位の扱いなどが不十分なまま解こうとすると、誤った推論をしてしまいます。そして極めつけは「理由を説明する記述問題」です。答えそのものは合っていても、理由の説明が“根拠不足”と判断されれば得点になりません。
つまり、附属高校の理科は、ミスの発生ポイントが明確な教科といえます!そして、そのミスは「暗記量が少ないから」ではなく「思考のどこかが抜け落ちている」ことが原因です!ノエクリの理科指導は、その抜け落ちた思考の段階を特定し、生徒に説明させることで補強する仕組みになっています。
附属中で取れるのに、附属高校入試では失点する理由!

附属中の理科テストは、ワークや教科書の内容理解で点が取りやすい形式です。語句の整理、基本実験の理解、教科書の例題を反復することで得点につながるようになっています。そしてその構造が、「入試で伸び悩む理由」にもなっています。
問題は、附属高校の理科が「見たことのない設定」を多く扱う点です!実際の実験データ、初めて読む観察文、複数条件を比較する表、現実の現象に近い計算問題など、思考の組み立てが必要な問題が並びます。附属中の学習では「語句は覚えている」「図も見たことがある」程度では十分ではなく、次のようなギャップが生まれます。
・知識はあるのに“説明”ができない
・実験の意味が分かっていないので応用が読めない
・公式は知っているが“どれを使うか”の判断ができない
・本文を読むのが雑で、条件を見落とす
・計算はできるのに、単位が整理できていない
これらはすべて“ミスの種類”として分類できます。
ノエクリでは、このギャップを埋めるために「説明→質問→再現」という三段階指導を導入しており、生徒が“自分の言葉で考え直せる”ようにサポートしています。
中学生のうちに身につけたい“ミス分析型”の理科学習!
理科で成績が伸びる子には共通点があります。それは「どの種類のミスが多いか」を自分で説明できることです。逆に、伸びない子は“ミスをミスのまま放置する”傾向があります。中学生のうちに習慣化したい学習法を4つに整理します。
A ミスの種類を分類する習慣
理科のミスは、必ず次のどれかに当てはまります。
・知識のミス
・読み取りのミス
・計算・単位のミス
・公式選択ミス
ノエクリの授業では、問題を解いた後の「振り返り」を必ず行い、生徒自身にミス分類を説明させます。これにより、自分の弱点を“自覚した上で”改善できるようになります。
B 正解より“過程”を見直す
理科は、答えが合っていても途中が曖昧だと入試で失点します。大切なのは、解法の道筋が正しいかどうかです。
ノエクリでは、生徒の途中式・書いた図・メモを見ながら講師が質問し、考え方の流れを確認します。「理由を説明できるか」を毎回チェックすることで、表面的な理解を防ぎます。
C グラフ・図・表の読み取り力を鍛える
理科の失点の8割は、読み取りの浅さから生まれます。グラフの傾きの意味、変化の向き、どの値を比較するかといったポイントは、自然と身につくものではありません。
ノエクリの授業では「このグラフは何を表している?」「この表の一番のポイントは?」と問い、生徒に言語化させています。これが入試問題の安定した読解につながります。
家庭でできるサポート
保護者の方が理科を教える必要はありません。必要なのは、ミスを見つけた時に「どうしてそう思ったの?」と優しく問いかけることです。答えを言わせるのではなく、考え方を言語化させることで、理科の“思考の癖”が改善されていきます。
もし説明に詰まったら、それは弱点が見つかった瞬間です。
ノエクリの授業では、その弱点を授業内で補強し、家庭では保護者の方が問いかけでサポートする。この二枚体制が、附属高校合格に向けて最も効果的です。
まとめ
金大附属高校の理科は、暗記よりも「理由を説明できるか」を本質的に評価する入試です。だからこそ、中学生のうちに“ミスの原因を言語化する習慣”を育てることが何より重要になります。
ノエクリの個別授業は、生徒が自分のミスを見つけ、改善し、再現できるように導く指導です!ワーク反復だけでは伸びない理科を、“ミスを味方につけて伸びる理科”へ変えていく。これが、附属高校合格へもっとも直結する学習法です。
投稿者
小坂
有松校舎・金沢駅前校舎の小坂です!
▲▲クリックして小坂のブログ一覧(77ブログ公開中)を見る